ひとときの暗がり
作:しもたろうに
[website]
![]()

+
高校生になってからこっち、局長は「砂漠の砂鉄」のような扱いを受ける理由を1つずつ消していこう作戦を考え、実際に実行に移していた。
髪型がダサい可能性があると思えば、超勇気を出して学校近くの美容院を予約したこともある。
臭いから嫌われていると不安になった日から、毎日朝、昼、夕、夜としずかちゃんもびっくりな頻度で入浴を繰り返した。
話を合わせられればいいのかと、1ミリも興味の湧かないアホみたいな漫画や薄っぺらで中身のない恋愛ソングに手を出した事もある。
体毛を気にして一本一本毛抜きで抜くようになったのもこの頃だ。
二重まぶたになりたくて、ステックのりでまぶたの皮を張り付けたりもした。
携帯電話もそのひとつ。
当時(2000年くらいの頃)高校生の間では、携帯電話が浸透しつつあった。
頑張れば手に入るけど何もしなければ高嶺の花と言うその絶妙な難易度は、ともすれば持つ事で周りから一目置かれる存在になる可能性を秘めていた。
そして、クラス内ではイケてるグループを筆頭に、約半分位の生徒が携帯電話を持っている状況。
局長は当然不所持だ。
クラス内でまだ持っていない人間が少なくなかった携帯電話を持てば、あのイケてるグループとも接点が持てるのではと言う淡い希望を抱くには十分なポテンシャルがあったと言えるだろう。
ちなみに局長の両親は、学生の立場で携帯電話を持つことには否定的。
そんな両親に対して、局長は高校入学当初からずっと所持したい希望を伝え続けていた。
1年をかけた説得は功を奏し、2月に行われる学年末テストで、学年30位以内に入る事を条件に、局長は遂に携帯電話を持つことを許された。
多少出遅れたが、まだクラス内の半数は携帯電話を持っていない。
今なら、まだ間に合う。
クラスの人気者になれるはずだ。
普段テスト勉強をほとんどやる事がない局長だったが、(煩悩にまみれながら)真面目に取り組んだ結果、この学年末テストで見事258人中28位を取ることに成功したのだ。
約束は守られなければいけない。
早速のその週の日曜日に、母親同伴で近所のドコモショップへ赴き、念願の携帯電話を手に入れた。
自分の部屋に戻り、がさごそとドコモの紙袋から取り出した自分の携帯電話は、何よりもキラキラと光り輝いていた。
次の日の朝。
嬉しすぎて寝不足なのにお目々ぱっちりの状態の局長は、思わず浮かび上がってしまうほどウキウキとした気分で登校した。
誰とアドレスを交換しようか。
「お!お前も携帯買ったのか?」と言われた時、どう返事しようか。
クラスの女子から次々と「アドレス交換しよう」と言われた時、にやけずに対応できるだろうか。
止めどなく楽しい妄想が溢れてくる。
頭の中はお花畑だ。
いつもは重い教室の引き戸も今日だけは軽く感じる。
ガラガラと戸を開け、ゆっくりと教室内を見渡した。
だが、そこにあったのはいつもの日常だった。
挨拶どころか、ほとんどのクラスメイトが一瞥のあと、入ってきたのが局長だと分かるや否や視線を外し元の会話に戻っていく。
これ見よがしに、携帯電話をポケットから取り出し、メールのセンター問い合わせを行ってみた。
当然メールなど溜まっているはずもない。
局長のアドレス帳には現時点で両親の連絡先しか登録されていないのだ。
そもそも誰もこの局長の所作自体、認識すらしていなかった。
朝のウキウキとした気分は一瞬で消し飛ぶ。
「まぁ、そうだよな」
誰にも聞こえないレベルの声量でそうつぶやくと、ほてほてと自分の席まで歩いていき、静かに席に着いた。
原因を見つけては改善してみようと心がける。
だが、当たり前のように何も変わることはない。
その都度、自分自身の存在意義が揺らぎ始め、生きている意味と理由を考える。
自分と言う人間はここに存在しても良いのか。
生きていく事を許されるのか。
存在を否定されてまで、今日を生きる意味がどこにあるのか。
負の自問自答。
その繰り返しがいつまでもいつまでも何度も何度も続く。
そんなどうしようもなく惨めな日常が数十万と積み重なったものが人生なのだろう。
結局のところ、誰からも相手にされないまま静かに死んでいくのだ。
もちろん童貞としてだ。
せめて一度だけでも女とセックスがしたい。
でもそんな願望が叶うはずもないままオナニーに明け暮れるオナニー人生。
右手だけが筋骨隆々となる事を恐れ、3日に一度は左手で行うオナニー人生。
局長は、改めて取り出した携帯電話の点滅するメールアイコンを見つめながら、一人途方もない絶望を感じたのだった。
その日は、週に1度の部活動がある日。
体育館のステージが尋常じゃなく寒いと言う理由により、3学期に入ってから演劇部の練習は部室での台本読みがメインとなっていた。
部室の扉を開ける。
黒崎だけが椅子に座り、高校演劇台本集と言う本をペラペラとめくっていた。
当然守山の姿はもうどこにもない。
「おっす!高井!」
局長の存在に気が付いた黒崎は右手を軽く上げて挨拶した。
そして、そのまま本に目を落とす。
「ども・・・」とだけ返し、所在なく入り口付近の椅子に座った局長は、タクヤが来るのを今か今かと待ちながら、部室の窓から外を眺めていた。
こんな時よくある「今日寒いですね」と言った天候についての当たり障りない会話を局長はなぜか強烈に嫌悪していた。
そんなに話すことがないのなら、無理にどうでも良い会話をする必要などない。
取り合えずで、その場しのぎの会話を行い、乾いた笑いを交わしあう。そんな凡庸な大人にだけはなりたくない。
そんな大人たちを信じられない位冷たい目で軽蔑してやるんだ。
局長は改めて謎の決意をする。
そして、密室に2人、無言の状態が延々と続くこの状態だとしても、「今日は寒いですね」と黒崎には声をかけまい。かける位なら死ぬ!と、心に誓った。
静かに時間が流れていく。
不毛な時間。
まだタクヤは来ない。
局長はふと思い直した。
今日は、話すことがない上で無理やりどうでも良い会話をしなくても良い事に気が付いたのだ。
話したいこと。
そう。物凄く話したい事が局長にはあった。
「・・・あの・・・先輩?」
恐る恐る黒崎に声をかける。
「ん?なに?」
本に目を落としたまま、黒崎が答えた。
「先輩って、携帯持ってましたっけ?」
「持ってるよ。なんで?・・・あ!もしかして、高井君も携帯買ったの?」
その日1日を通して初めて、最も局長が欲していた返答があった。
その言葉を待ってましたとばかりにポケットから、買ったばかりでまだ画面のフィルムも剥がしていない携帯電話を取り出す。
「買いました!」
「おおおおおおおおお!やったぁ!じゃあ、連絡先交換しよ!」
そう言うと黒崎はバックから自分の携帯電話を取り出した。
「赤外線分かる?」
「分かるんですけど、まだやった事なくて・・・」
「そうなんだ。エッとね・・・この黒い所同士をくっつけて・・・」
そう言いながら黒崎は局長に近付いてきて、携帯電話の赤外線通信のやり方を懇切丁寧に説明した。
思ったより近づいてくる。
ふわっと女の子のいい匂いがした。
正直、赤外線通信のやり方なんてどうでも良いとさえ思えるいい匂いだ。
お互いの「黒い部分」同士をくっつけて、情報を送り込むなんて、まるでセックスでもしているかのようではないか。
永遠に続けばいいその時間は「送信完了」の表示と共にあっけなく終了した。
数秒後、「黒崎優実です。よろしくねハート。」と言うメールが送られてきた。
黒崎の顔を見ると、「よろしくね」と言い目を細めて右手でピースマークを作っている。
その日の部活では、黒崎が局長の携帯電話の話を色んな部員に広め、その時携帯電話を持っていた白石、ウルオとも赤外線通信で連絡先を交換した。
まだ携帯電話を所持していないムラヤン、タクヤに対して少しだけ優越感に浸る局長。
部活終了後。
その日の夜。
自室のベッドの上で読み残していた漫画を読んでいた時、それまで全く反応のなかった携帯電話にメールが届いた。
黒崎からだ。
「今日は部活お疲れ様でした。全然守山部長みたいにちゃんとできないけど、頑張ってみるから協力してね。」と書かれていた。
局長にとって人生で初めてのメール返信の時がやってきたのだ。
ドキドキしながら、黒崎の文面に対して返信を考える。
書いては読み直し「この表現は誤解されるかな?」と考えては消す。
何度もそれを繰り返し、「お疲れ様です!オレに出来る事なんかほとんどないと思いますが尽力します!」とメール返信が出来るまでに1時間を要してしまった。
すると数秒で返信が来る。
「高井君は役者も出来るし、面白い話も書けるし、演出監督も出来るし。凄いって。あと、バンドもやっているしね!ホントお願いしますヘコヘコ。」
この文章を数秒のうちに考え、入力して返信してきたと言うのか・・・
女子高生恐るべし。
そして再び繰り返される謎の推敲作業。
この30分から1時間をかけた推敲作業後のメール送信、数秒後のメール着信と言うやり取りは、結局その日の午前4時くらいまで続いた。
局長のメールボックスはタイトルが尋常ではない「Re:」で埋め尽くされた黒崎とのメールでいっぱいになっている。
その光景が何だか嬉しくてしょうがない。
「もう本当に寝なくちゃ。おやすみ~」と言う黒崎の最後のメールになぜか興奮した局長は、そのメールを眺めながらオナニーをして、そのまま眠りについた。
その日から、局長と黒崎はメールを通したやり取りを連日深夜まで行うようになった。
連日と言うのは些か大げさだが、それでも週に2~3日は必ず行っていた。
演劇部内でも守山以外の女子部員とほぼほぼ接点を持っていなかった局長は、正直、黒崎と部活内容以外の会話をした記憶がほとんどない。
それなのに、なぜこんなにメールでのやり取りをしているのか。
全く理解できない。
不思議で仕方がない。
ただ、女の子と夜遅くまでメールしていると言う現実は確実にあった。
それだけは夢ではない。
タイトルが「Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:」のメールで満杯のメールボックスがそれを証明している。
それに対して気持ち悪いニヤニヤが止まらない。
本人はそんなことなど知る由もないが、実はこの「メール」と言うコミュニケーションツールは、意外にも局長の絶望的にダメな部分をうまくフォローできていた。
局長は短絡的。
思ったことをすぐに口にしてしまう。
人が気にしている事や、言ってほしくない事でもなんでもつい口にしてしまう。
しかも天上天下唯我独尊。
自分をとにかく尊大に表現する。
その結果として、しばらくすると誰からも相手にされなくなっていくのは、自明の理だった。
しかし、自分の考えを文章にして客観的に見直し、且つ推敲した上で納得して送信することで、図らずも余計な一言がなくなり、相手の事を慮った普通の会話が出来るようになっていたのだ。
黒崎自身も、これまでの局長のイメージと540度違う、温和で柔らかいメールの文章に対して少なからず違和感を覚えていた。
それでも、メールでの会話のキャッチボールを楽しんでいたのは、黒崎と局長の相性が意外にも良かった事に起因する。
白石やウルオとも連絡先を交換したその日に、何度かメールのやり取りをした。
だだ、数回やり取りしただけで会話が続かずに終わってしまった。
そして、それ以降一切メールのやり取りをしていない。
局長と黒崎が話す内容は音楽、漫画、ゲームなどの話から始まり、学校であったことや、物事の考え方から、オカルト話まで実に多岐に渡っていた。
意外と同じものが好きだったのだが趣味趣向に若干のズレがあり、その若干のズレがお互いにとってこれまで知らなかった新しい側面を補いあう形になった節がある。
自分の好きな分野の新しい側面を知ることが出来ると言う快感が、2人にメールでのやり取りを続けさせていたのだ。
気が付けば2月も終わり、3月になっていた。
携帯電話のパケット料金がメールだけとは思えない限界突破した金額になっていたため、少し自重するようにはなったものの、その日も黒崎からメールが届いた。
それをベッドに横になりながら確認する局長。
「そう言えば、もう少しで卒業式だね。守山部長とも会えなくなっちゃうのさびしくない?」
数週間の訓練の結果、さほど返信に時間がかからなくなっていた局長はそのメールに対して早速返信を打つ。
「あぁ・・・そう言えば、もうそんな時期か。早いなぁ。」
この頃には、黒崎の提案で局長は黒崎に対して敬語を使わなくなっていた。
「なんか守山部長は局長の事、気に入ってたよね。あれ、なんでなんだろう。」
黒崎も局長の提案で、「高井君」ではなく「局長」と呼ぶようになっていた。
「気に入られてたかな?どうなんだろう・・・」
「付喪神の時とかでも、もちろんあの話面白かったけど、これやろうよ!って凄い説得されたんだよ。あたしが書いた本の時なんか、割と冷たく没にされたのにさぁ。」
「そうなの?てっきり先輩と部長は仲良しなんだとばっかり思ってた。」
「別に仲悪いって事はないけど、あの人結構男と女で対応変わるんだよ。気付いてなかった?」
「まぢで?全然気が付かなかった。」
「まぁ、局長鈍感ぽいしな。でも、あたしたちと局長たち4人・・・と言うか特に局長を近づけたくなかった節は絶対あったと思う。ホントはあたしだって可愛い一年生男子を愛でたかったんだ。でも、今年1年はほとんど絡みなかったでしょ。」
意外な話だった。
局長は自分の存在がこの世の全ての女から唾棄されるべきものだと信じて疑わない。
演劇部内でもそれは当然。
そんな中で、守山だけは局長に対して普通に接してくれている。
そう信じていたのだ。
「確かに絡みなかったけど、愛でたかったんだ。」
「当たり前だよ。あたしも一応年頃の女だからね。男子を愛でたいさ。」
「てっきり嫌われてるもんだとばっかり思ってた。」
「嫌うほど局長の事知らないし。知らない人の事をいきなり嫌いになる奴なんていないって。って言うか、今、別に普通にメールしてるでしょ。嫌いならそんなメールとかしないし。」
目の前の世界がぐわんぐわんと音を立てて廻り始める。
黒崎から送られてくるメールの文面を読むたび、局長は自身の既成概念がガラガラと崩れていく事を感じた。
如何に他人の心情に対して無頓着で、自身の思い込みだけで物事を判断していたのか。
それでいて自分以外のすべての人間を否定し、自分だけが特別な人間だと強く強く思い込んでいたのか。
自分に関心を向けない人間に対してなど、誰しも関心を持つことはできない。
もしかしたら、ただそれだけの事だったのかもしれない。
そしてそれは決して「嫌い」「嫌悪」と言う感情と同一ではないのだ。
「チョッと今、オレ結構な衝撃受けてるんだけど・・・」
「(笑)」
局長は、自分の感情を持っていく場所が分からないまま、黒崎とのメールのやり取りを続けた。
「って言うか、局長さ。部長の事どう思ってた?」
「どうって・・・?」
「守山部長は単純に男と女で扱いに差があるって感じだし、局長の事は気に入ってたとは思うけど面白い後輩って感じかな。でも、局長の方は割と満更でもなかったように見えたからさ。」
「まぁ、オレの書いた物語褒めてくれたし、バンドのライブとかもめっちゃ来てくれたからなぁ。」
「いやいやそう言う意味じゃなくて・・・」
「??なんかオレ話理解できてない?オレは、部長と一緒に居て嫌な気分はしなかったけど・・・」
「そう言うのをさ、『好き』って言うんじゃない?」
「は?」
「今日はもう寝る!おやすみ!ちなみに卒業式は3月9日だからね!」
「おい!いや!チョッと待て!」
それ以降、黒崎からの返信はなかった。
黒崎からの唐突な指摘。
局長は何度も何度もメールボックスを遡り、黒崎とのやり取りを読み直した。
「好き・・・?好き?好き?って・・・すき?SUKIIIIIII?!」
遅い朝日が昇りつつある午前6時。
心の奥底に閉じ込めていた感情を無理やりこじ開けられでもしたのだろうか。
なぜか強烈な心臓の鼓動が止まらない。
ドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキ土器ドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキ土器ドキドキドキドキドキドキドキ土器怒気ドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキDOKIDOKIドキドキドキドキドキドキドキドキ・・・
自分の人生において「好き」と言う単語が登場する事態など、よもやあるはずが無いと妄信していた16歳の早春夜明け。
卒業式は、7日後に迫っていた。
髪型がダサい可能性があると思えば、超勇気を出して学校近くの美容院を予約したこともある。
臭いから嫌われていると不安になった日から、毎日朝、昼、夕、夜としずかちゃんもびっくりな頻度で入浴を繰り返した。
話を合わせられればいいのかと、1ミリも興味の湧かないアホみたいな漫画や薄っぺらで中身のない恋愛ソングに手を出した事もある。
体毛を気にして一本一本毛抜きで抜くようになったのもこの頃だ。
二重まぶたになりたくて、ステックのりでまぶたの皮を張り付けたりもした。
携帯電話もそのひとつ。
当時(2000年くらいの頃)高校生の間では、携帯電話が浸透しつつあった。
頑張れば手に入るけど何もしなければ高嶺の花と言うその絶妙な難易度は、ともすれば持つ事で周りから一目置かれる存在になる可能性を秘めていた。
そして、クラス内ではイケてるグループを筆頭に、約半分位の生徒が携帯電話を持っている状況。
局長は当然不所持だ。
クラス内でまだ持っていない人間が少なくなかった携帯電話を持てば、あのイケてるグループとも接点が持てるのではと言う淡い希望を抱くには十分なポテンシャルがあったと言えるだろう。
ちなみに局長の両親は、学生の立場で携帯電話を持つことには否定的。
そんな両親に対して、局長は高校入学当初からずっと所持したい希望を伝え続けていた。
1年をかけた説得は功を奏し、2月に行われる学年末テストで、学年30位以内に入る事を条件に、局長は遂に携帯電話を持つことを許された。
多少出遅れたが、まだクラス内の半数は携帯電話を持っていない。
今なら、まだ間に合う。
クラスの人気者になれるはずだ。
普段テスト勉強をほとんどやる事がない局長だったが、(煩悩にまみれながら)真面目に取り組んだ結果、この学年末テストで見事258人中28位を取ることに成功したのだ。
約束は守られなければいけない。
早速のその週の日曜日に、母親同伴で近所のドコモショップへ赴き、念願の携帯電話を手に入れた。
自分の部屋に戻り、がさごそとドコモの紙袋から取り出した自分の携帯電話は、何よりもキラキラと光り輝いていた。
次の日の朝。
嬉しすぎて寝不足なのにお目々ぱっちりの状態の局長は、思わず浮かび上がってしまうほどウキウキとした気分で登校した。
誰とアドレスを交換しようか。
「お!お前も携帯買ったのか?」と言われた時、どう返事しようか。
クラスの女子から次々と「アドレス交換しよう」と言われた時、にやけずに対応できるだろうか。
止めどなく楽しい妄想が溢れてくる。
頭の中はお花畑だ。
いつもは重い教室の引き戸も今日だけは軽く感じる。
ガラガラと戸を開け、ゆっくりと教室内を見渡した。
だが、そこにあったのはいつもの日常だった。
挨拶どころか、ほとんどのクラスメイトが一瞥のあと、入ってきたのが局長だと分かるや否や視線を外し元の会話に戻っていく。
これ見よがしに、携帯電話をポケットから取り出し、メールのセンター問い合わせを行ってみた。
当然メールなど溜まっているはずもない。
局長のアドレス帳には現時点で両親の連絡先しか登録されていないのだ。
そもそも誰もこの局長の所作自体、認識すらしていなかった。
朝のウキウキとした気分は一瞬で消し飛ぶ。
「まぁ、そうだよな」
誰にも聞こえないレベルの声量でそうつぶやくと、ほてほてと自分の席まで歩いていき、静かに席に着いた。
原因を見つけては改善してみようと心がける。
だが、当たり前のように何も変わることはない。
その都度、自分自身の存在意義が揺らぎ始め、生きている意味と理由を考える。
自分と言う人間はここに存在しても良いのか。
生きていく事を許されるのか。
存在を否定されてまで、今日を生きる意味がどこにあるのか。
負の自問自答。
その繰り返しがいつまでもいつまでも何度も何度も続く。
そんなどうしようもなく惨めな日常が数十万と積み重なったものが人生なのだろう。
結局のところ、誰からも相手にされないまま静かに死んでいくのだ。
もちろん童貞としてだ。
せめて一度だけでも女とセックスがしたい。
でもそんな願望が叶うはずもないままオナニーに明け暮れるオナニー人生。
右手だけが筋骨隆々となる事を恐れ、3日に一度は左手で行うオナニー人生。
局長は、改めて取り出した携帯電話の点滅するメールアイコンを見つめながら、一人途方もない絶望を感じたのだった。
その日は、週に1度の部活動がある日。
体育館のステージが尋常じゃなく寒いと言う理由により、3学期に入ってから演劇部の練習は部室での台本読みがメインとなっていた。
部室の扉を開ける。
黒崎だけが椅子に座り、高校演劇台本集と言う本をペラペラとめくっていた。
当然守山の姿はもうどこにもない。
「おっす!高井!」
局長の存在に気が付いた黒崎は右手を軽く上げて挨拶した。
そして、そのまま本に目を落とす。
「ども・・・」とだけ返し、所在なく入り口付近の椅子に座った局長は、タクヤが来るのを今か今かと待ちながら、部室の窓から外を眺めていた。
こんな時よくある「今日寒いですね」と言った天候についての当たり障りない会話を局長はなぜか強烈に嫌悪していた。
そんなに話すことがないのなら、無理にどうでも良い会話をする必要などない。
取り合えずで、その場しのぎの会話を行い、乾いた笑いを交わしあう。そんな凡庸な大人にだけはなりたくない。
そんな大人たちを信じられない位冷たい目で軽蔑してやるんだ。
局長は改めて謎の決意をする。
そして、密室に2人、無言の状態が延々と続くこの状態だとしても、「今日は寒いですね」と黒崎には声をかけまい。かける位なら死ぬ!と、心に誓った。
静かに時間が流れていく。
不毛な時間。
まだタクヤは来ない。
局長はふと思い直した。
今日は、話すことがない上で無理やりどうでも良い会話をしなくても良い事に気が付いたのだ。
話したいこと。
そう。物凄く話したい事が局長にはあった。
「・・・あの・・・先輩?」
恐る恐る黒崎に声をかける。
「ん?なに?」
本に目を落としたまま、黒崎が答えた。
「先輩って、携帯持ってましたっけ?」
「持ってるよ。なんで?・・・あ!もしかして、高井君も携帯買ったの?」
その日1日を通して初めて、最も局長が欲していた返答があった。
その言葉を待ってましたとばかりにポケットから、買ったばかりでまだ画面のフィルムも剥がしていない携帯電話を取り出す。
「買いました!」
「おおおおおおおおお!やったぁ!じゃあ、連絡先交換しよ!」
そう言うと黒崎はバックから自分の携帯電話を取り出した。
「赤外線分かる?」
「分かるんですけど、まだやった事なくて・・・」
「そうなんだ。エッとね・・・この黒い所同士をくっつけて・・・」
そう言いながら黒崎は局長に近付いてきて、携帯電話の赤外線通信のやり方を懇切丁寧に説明した。
思ったより近づいてくる。
ふわっと女の子のいい匂いがした。
正直、赤外線通信のやり方なんてどうでも良いとさえ思えるいい匂いだ。
お互いの「黒い部分」同士をくっつけて、情報を送り込むなんて、まるでセックスでもしているかのようではないか。
永遠に続けばいいその時間は「送信完了」の表示と共にあっけなく終了した。
数秒後、「黒崎優実です。よろしくねハート。」と言うメールが送られてきた。
黒崎の顔を見ると、「よろしくね」と言い目を細めて右手でピースマークを作っている。
その日の部活では、黒崎が局長の携帯電話の話を色んな部員に広め、その時携帯電話を持っていた白石、ウルオとも赤外線通信で連絡先を交換した。
まだ携帯電話を所持していないムラヤン、タクヤに対して少しだけ優越感に浸る局長。
部活終了後。
その日の夜。
自室のベッドの上で読み残していた漫画を読んでいた時、それまで全く反応のなかった携帯電話にメールが届いた。
黒崎からだ。
「今日は部活お疲れ様でした。全然守山部長みたいにちゃんとできないけど、頑張ってみるから協力してね。」と書かれていた。
局長にとって人生で初めてのメール返信の時がやってきたのだ。
ドキドキしながら、黒崎の文面に対して返信を考える。
書いては読み直し「この表現は誤解されるかな?」と考えては消す。
何度もそれを繰り返し、「お疲れ様です!オレに出来る事なんかほとんどないと思いますが尽力します!」とメール返信が出来るまでに1時間を要してしまった。
すると数秒で返信が来る。
「高井君は役者も出来るし、面白い話も書けるし、演出監督も出来るし。凄いって。あと、バンドもやっているしね!ホントお願いしますヘコヘコ。」
この文章を数秒のうちに考え、入力して返信してきたと言うのか・・・
女子高生恐るべし。
そして再び繰り返される謎の推敲作業。
この30分から1時間をかけた推敲作業後のメール送信、数秒後のメール着信と言うやり取りは、結局その日の午前4時くらいまで続いた。
局長のメールボックスはタイトルが尋常ではない「Re:」で埋め尽くされた黒崎とのメールでいっぱいになっている。
その光景が何だか嬉しくてしょうがない。
「もう本当に寝なくちゃ。おやすみ~」と言う黒崎の最後のメールになぜか興奮した局長は、そのメールを眺めながらオナニーをして、そのまま眠りについた。
その日から、局長と黒崎はメールを通したやり取りを連日深夜まで行うようになった。
連日と言うのは些か大げさだが、それでも週に2~3日は必ず行っていた。
演劇部内でも守山以外の女子部員とほぼほぼ接点を持っていなかった局長は、正直、黒崎と部活内容以外の会話をした記憶がほとんどない。
それなのに、なぜこんなにメールでのやり取りをしているのか。
全く理解できない。
不思議で仕方がない。
ただ、女の子と夜遅くまでメールしていると言う現実は確実にあった。
それだけは夢ではない。
タイトルが「Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:」のメールで満杯のメールボックスがそれを証明している。
それに対して気持ち悪いニヤニヤが止まらない。
本人はそんなことなど知る由もないが、実はこの「メール」と言うコミュニケーションツールは、意外にも局長の絶望的にダメな部分をうまくフォローできていた。
局長は短絡的。
思ったことをすぐに口にしてしまう。
人が気にしている事や、言ってほしくない事でもなんでもつい口にしてしまう。
しかも天上天下唯我独尊。
自分をとにかく尊大に表現する。
その結果として、しばらくすると誰からも相手にされなくなっていくのは、自明の理だった。
しかし、自分の考えを文章にして客観的に見直し、且つ推敲した上で納得して送信することで、図らずも余計な一言がなくなり、相手の事を慮った普通の会話が出来るようになっていたのだ。
黒崎自身も、これまでの局長のイメージと540度違う、温和で柔らかいメールの文章に対して少なからず違和感を覚えていた。
それでも、メールでの会話のキャッチボールを楽しんでいたのは、黒崎と局長の相性が意外にも良かった事に起因する。
白石やウルオとも連絡先を交換したその日に、何度かメールのやり取りをした。
だだ、数回やり取りしただけで会話が続かずに終わってしまった。
そして、それ以降一切メールのやり取りをしていない。
局長と黒崎が話す内容は音楽、漫画、ゲームなどの話から始まり、学校であったことや、物事の考え方から、オカルト話まで実に多岐に渡っていた。
意外と同じものが好きだったのだが趣味趣向に若干のズレがあり、その若干のズレがお互いにとってこれまで知らなかった新しい側面を補いあう形になった節がある。
自分の好きな分野の新しい側面を知ることが出来ると言う快感が、2人にメールでのやり取りを続けさせていたのだ。
気が付けば2月も終わり、3月になっていた。
携帯電話のパケット料金がメールだけとは思えない限界突破した金額になっていたため、少し自重するようにはなったものの、その日も黒崎からメールが届いた。
それをベッドに横になりながら確認する局長。
「そう言えば、もう少しで卒業式だね。守山部長とも会えなくなっちゃうのさびしくない?」
数週間の訓練の結果、さほど返信に時間がかからなくなっていた局長はそのメールに対して早速返信を打つ。
「あぁ・・・そう言えば、もうそんな時期か。早いなぁ。」
この頃には、黒崎の提案で局長は黒崎に対して敬語を使わなくなっていた。
「なんか守山部長は局長の事、気に入ってたよね。あれ、なんでなんだろう。」
黒崎も局長の提案で、「高井君」ではなく「局長」と呼ぶようになっていた。
「気に入られてたかな?どうなんだろう・・・」
「付喪神の時とかでも、もちろんあの話面白かったけど、これやろうよ!って凄い説得されたんだよ。あたしが書いた本の時なんか、割と冷たく没にされたのにさぁ。」
「そうなの?てっきり先輩と部長は仲良しなんだとばっかり思ってた。」
「別に仲悪いって事はないけど、あの人結構男と女で対応変わるんだよ。気付いてなかった?」
「まぢで?全然気が付かなかった。」
「まぁ、局長鈍感ぽいしな。でも、あたしたちと局長たち4人・・・と言うか特に局長を近づけたくなかった節は絶対あったと思う。ホントはあたしだって可愛い一年生男子を愛でたかったんだ。でも、今年1年はほとんど絡みなかったでしょ。」
意外な話だった。
局長は自分の存在がこの世の全ての女から唾棄されるべきものだと信じて疑わない。
演劇部内でもそれは当然。
そんな中で、守山だけは局長に対して普通に接してくれている。
そう信じていたのだ。
「確かに絡みなかったけど、愛でたかったんだ。」
「当たり前だよ。あたしも一応年頃の女だからね。男子を愛でたいさ。」
「てっきり嫌われてるもんだとばっかり思ってた。」
「嫌うほど局長の事知らないし。知らない人の事をいきなり嫌いになる奴なんていないって。って言うか、今、別に普通にメールしてるでしょ。嫌いならそんなメールとかしないし。」
目の前の世界がぐわんぐわんと音を立てて廻り始める。
黒崎から送られてくるメールの文面を読むたび、局長は自身の既成概念がガラガラと崩れていく事を感じた。
如何に他人の心情に対して無頓着で、自身の思い込みだけで物事を判断していたのか。
それでいて自分以外のすべての人間を否定し、自分だけが特別な人間だと強く強く思い込んでいたのか。
自分に関心を向けない人間に対してなど、誰しも関心を持つことはできない。
もしかしたら、ただそれだけの事だったのかもしれない。
そしてそれは決して「嫌い」「嫌悪」と言う感情と同一ではないのだ。
「チョッと今、オレ結構な衝撃受けてるんだけど・・・」
「(笑)」
局長は、自分の感情を持っていく場所が分からないまま、黒崎とのメールのやり取りを続けた。
「って言うか、局長さ。部長の事どう思ってた?」
「どうって・・・?」
「守山部長は単純に男と女で扱いに差があるって感じだし、局長の事は気に入ってたとは思うけど面白い後輩って感じかな。でも、局長の方は割と満更でもなかったように見えたからさ。」
「まぁ、オレの書いた物語褒めてくれたし、バンドのライブとかもめっちゃ来てくれたからなぁ。」
「いやいやそう言う意味じゃなくて・・・」
「??なんかオレ話理解できてない?オレは、部長と一緒に居て嫌な気分はしなかったけど・・・」
「そう言うのをさ、『好き』って言うんじゃない?」
「は?」
「今日はもう寝る!おやすみ!ちなみに卒業式は3月9日だからね!」
「おい!いや!チョッと待て!」
それ以降、黒崎からの返信はなかった。
黒崎からの唐突な指摘。
局長は何度も何度もメールボックスを遡り、黒崎とのやり取りを読み直した。
「好き・・・?好き?好き?って・・・すき?SUKIIIIIII?!」
遅い朝日が昇りつつある午前6時。
心の奥底に閉じ込めていた感情を無理やりこじ開けられでもしたのだろうか。
なぜか強烈な心臓の鼓動が止まらない。
ドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキ土器ドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキ土器ドキドキドキドキドキドキドキ土器怒気ドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキDOKIDOKIドキドキドキドキドキドキドキドキ・・・
自分の人生において「好き」と言う単語が登場する事態など、よもやあるはずが無いと妄信していた16歳の早春夜明け。
卒業式は、7日後に迫っていた。

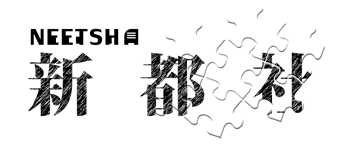

しもたろうに 先生に励ましのお便りを送ろう!!
〒みんなの感想を読む