ひとときの暗がり
作:しもたろうに
[website]
![]()
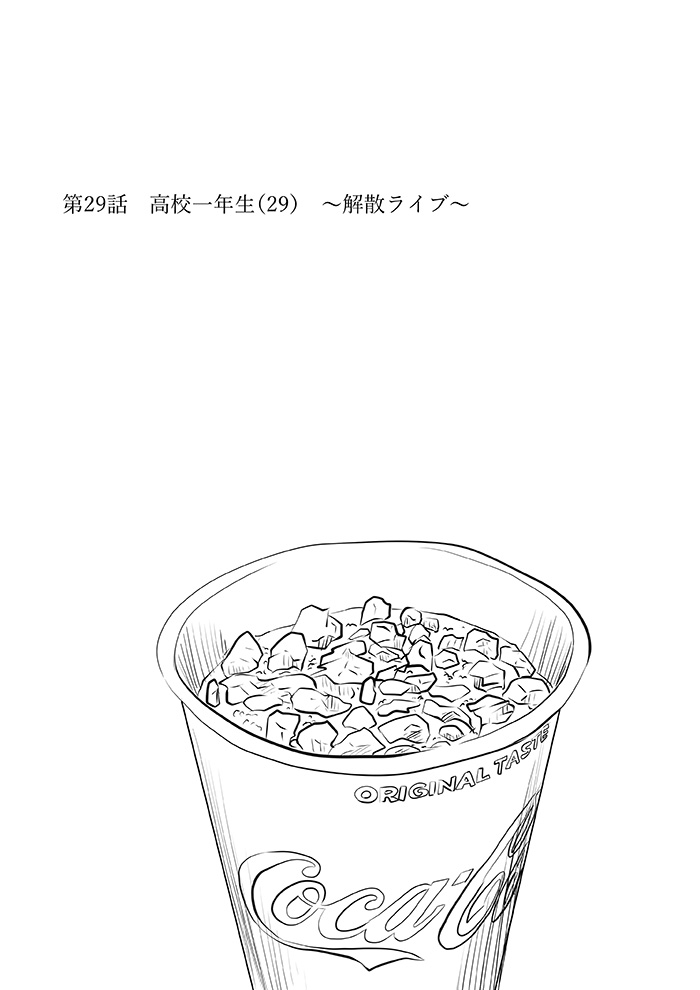
+
年が明けた。
その日は吹雪にも近い強い風が吹き、雪が舞い踊るように降っていた。
こんもり雪の積もったトイレ裏はさすがに寒すぎたため、タクヤと局長の2人は「これは無理。絶対死ぬ」と互いに意思確認をし、いそいそと演劇部の部室に逃げ込んだ。
部室内で他愛もない話をしながら、弁当箱を出したとき、ガラっと扉が開いた。
そこに立っていたのは、ムラヤンだった。
「??え?どうしたの?」
突然の事に驚く局長。
「いや…と言うか、どうしてお2人がここに?」
ムラヤンも戸惑っているようだ。
しばらくするとウルオがやってきた。
局長、タクヤと同じくクラスに居場所のない2人は、実は普段から演劇部の部室で昼を過ごしていたのだ。
たまたまこの日、局長とタクヤが大雪で部室に逃げ込んだため、図らずも4人が顔を合わすことになってしまった。
「あれぇ…」
ウルオが少し困ったような表情をしつつ、部室の中に入ってくる。
「珍しい人達がいるね…」
何だか気まずい時間が流れる。
無言…
無言…
無言…
…………
………………
………………………
「あのさぁ…」
その空気を破るようにタクヤが話し始めた。
「ムラヤンのいるトコで、こんな事言うのも気が引けるんだけど、丁度いいかなと思って…実はこの前のクリスマスライブの後、YAMAHA楽器の吉岡さんから声かけられてさ…」
「え?ライブの話?」
食い気味にウルオが訊ねる。
「まぁ、そうと言えばそうなんだけど、チョッと待て。」
ウルオを制止したタクヤは一息ついて、話を続けた。
「その時、吉岡さんに正直に話したんだよ。今、バンドは休止中でしばらくはライブに出られないって…そしたら、吉岡さんが最後に一度だけライブに出ないって。解散ライブをさ。」
「いや、別に解散ってわけじゃないんだけど。」
局長的には、その部分だけは突っ込まずにいられない。
「そうなんだけど、まぁ、学生バンドなんて休止したらそのまんまの場合が多いからな。」
タクヤは椅子に座り直し、ムラヤンの方を向いて意を決したように話し始めた。
「ムラヤン。この前の事は100%局長が悪かったと思う。」
「オレだけか!??」
立ち上がる局長。
「ムラヤンの辞めると言う話も当然だと思うんだ。でも、最後に1度だけケジメの意味で、ライブやらないか。その後は絶対ムラヤンを誘う事はないから。」
タクヤの話を聞いたムラヤンは、誰と目を合わせる訳でもなく視線を落とし、静かにバックから弁当箱を取り出し、おもむろに食べ始めた。
…
………
………………
「条件があるよ。」
義理堅く、責任感が強い。
そんなムラヤンは、真摯な姿勢で謝ってくれたタクヤに対して不義理を働くことなど到底出来るはずもない。
食べながらムラヤンは最後のライブに参加するための3つの条件を告げた。
これが絶対に最後である事。
事前にメロディーが分かるようにコピー曲をする事。
練習への参加を強制しない事。
タクヤはそれを全て快諾し最後に「ありがとう。ムラヤン。」と握手を求めた。
ムラヤンもそれに応える。
「おおお!もう一回ライブできるんだね!」
心なしか嬉しそうなウルオ。
「え…?もう決定?」
いつの間にか、コピー曲での解散ライブが決まってしまった事に戸惑う局長。
「け~ってい!」
タクヤはニヤニヤとしながら局長を見た。
「せめて、「スーパーフィニッシュ」はやらない。」
自分が蚊帳の外になっていることが不満な局長は、少しでも自分の意志が入り込むようにそう提案した。
前回、ハコフグの人に褒められた15秒ほどの短いシータライブ定番の曲だ。
「まぁ、それは大丈夫だからいいよ。」
ムラヤンはしぶしぶそれを承諾。
その時、再びガラッと部室の扉が開いた。
「声が聞こえてきたから覗いてみた…ん…だけど……あ!…あけましておめでとうございます。」
部室の中を覗き込み、ペコリと頭を下げたのは守山明美だった。
ジャンヌダルクの映画を見に行って以来だ。
「部長じゃないですか!お久しぶりです。」
「もう部長じゃないけどね…」
「いや、いつになってもオレにとっては部長ですよ。」
タクヤと守山はそう言って2人でケラケラ笑っている。
無思慮な2人は、あの日のことなど何もなかったように当たり前に会話を交わしている。
「あけましておめでとうございます!」
「おめでとうございます。」
ウルオとムラヤンも挨拶をする。
まだかなりあの日の事を引きずっていた局長だけが、何だか気まずいままでいた。
「高井君もおめでとうございます。」
改めて、ペコリと頭を下げた守山。
「おめでとうございます…」
やっとそれだけ口にすることが出来た。
ニュース第一高校では、3年生は受験のため2学期後半から授業はなくなり、別に毎日出席する必要がない。
守山は、総文祭が終わったあとからは基本的には学校の図書室で勉強をし、昼休みだけ局長たちのいるトイレ裏にやってくると言う日々を過ごしていた。
12月後半に入ったあたりから最後の追い込みで、学校自体に来なくなっていた。
あの日以降学校(と言うか、トイレ裏)に来なくなったことを局長が気にしていると勘付いた守山は、自身を取り巻く現状について必要以上に詳しく話した。
最後に「でもお陰で志望校A判定出たんだ。」と告げ、左手でピースマークを作って見せた。
「今日は、その判定を聞きに久々に学校に来たんだよ。そしたら、部室から声が聞こえるからさ…」
タイミングが良いのか、悪いのか良く分からない。
ただタクヤはここぞとばかりに邪な心意気で「実は今、次のライブの話をしていたんです」と守山に告げた。
「えええ!凄い!あたしもやっと少し余裕が出来てきたから、行きたい行きたい!何日?」
「そう言えば、何日なんだ?」
局長がタクヤに尋ねる。
「1月23日。再来週の日曜日だな。」
「お前!それ、あと2週間チョイしかないじゃないか!」
「まぁ、今回はコピー曲だし大丈夫だろ?」
ムラヤンが「うんうん」と深くうなずいている。
「一応、今回でシータは最後なんですよ!」
ウルオが一言付け加える。
「え…バンド辞めるの。」
守山が戸惑う。
「ムラヤンがボーカル辞めることになって…バンドは解散しないんですけど、一応、これ以降については未定と言うか…」
「そうなんだ…」
守山はそうつぶやくと、暗い表情で俯いてしまった。
「いや、まぁ絶対に今回で最後ってわけじゃあないので!な!局長。」
タクヤが無理から元気そうに局長の肩を組んだ。
「先の事なんか分かんないですよ。ただ、オレもやめる気はなくて、今も新曲書いたりしてるし。」
局長は、守山の表情を見て不意に出まかせを言った。
本当は、新曲なんてあれ以来1曲も書いていない。
「いや、そうじゃなくて…実はね…その…志望校の入試試験が24日なんだ。受験するために23日は京都に居るんだよね…最後のライブなのに行けないよぉ…」
守山が受けようとしていたニュース大学は京都にあり、朝から始まる入学試験の為には、前日ホテルで宿泊する必要があったのだ。
「入試諦めて、別の大学行こうか…」
「いやいやいやいや…部長!そこは、入試受けてくださいよ!オレらのライブなんてほんとどうでも良いので。」
守山の発言に対して、タクヤが強く是正した。
「だって、シータは最後なんでしょ。」
「だから、最後かどうかも分からないし…せっかくA判定出たんでしょ。」
流石の局長もここはタクヤと同意見だった。
「残念だなぁ…」
誰がどう見ても分かるように、あからさまに守山は落ち込んでいる。
「あ…!そうだ!実は、今回でムラヤンが一旦辞めるので、これまでの音源をまとめた作品集みたいなのを作ってるんですよ。部長にはそれをプレゼントしますよ!」
「お前!そんなもの作ってたのか?」
タクヤが驚いたような顔で局長を見る。
もちろんその場しのぎの出まかせだ。
そんなもの作っているわけがない。
局長は何となく、沈み込んでいる守山の表情を見て、少しでも元気になってほしくてしょうがなかったのだ。
「凄い!そんなものがあるの?」
「はい。タイトルは「朝日が目に染みた赤フン達」と言います。」
これも出まかせだった。
「じゃあ…今回はそれで我慢するよ。」
守山はしぶしぶ納得し「お邪魔しましたぁ~」と言いクルッと1回転した後、ペコリと頭を下げ部室を後にした。
その日の部活で、黒崎たちにもライブの事を話した。
黒崎、白石、藤本、赤城たちはライブを見に行くことを、もちろん快諾した。
残された時間は2週間。
文化祭で演奏したGLAYのコピー曲をメインにセットリストを組んだ。
文化祭に参加していなかった啓司は「期間が短すぎる」とぶつぶつ文句を言っていたが、久々のコピー曲演奏については楽しそうにしているようだった。
楽譜通りに弾く事に何の魅力も感じない局長にとって、10月の時のような熱狂や酔狂は何もない。
2週間はあっという間に過ぎていった。
そして当日。
ライブ会場は、何の因果か「付喪神」公演を行った市民会館だった。
これで最後と言う感慨も何もないまま、ライブは開幕し、シータメンバーはそのライブ自体を無難にこなしていく。
これまで、どのライブでも感じていたような達成感と喪失感は全くなかった。
こんな形でシータの活動は終わってしまって良いのか。
局長はライブ中、何度も何度も自問自答を繰り返した。
ライブ最後の曲は、初めてシータを結成した中学校の文化祭で演奏した思い出の曲「GLAY」の「HOWEVER」。
だがしかし、それに対しても何も思う事はない。
今回は演奏後のインタビューのようなものもない普通のライブイベント。
勿論解散することについて、公に発表する機会などあるはずもない。
1バンドとして出演し、当たり障りのない、よく言えば無難な、悪く言えば誰の記憶にも残らない演奏で、ひっそりと最後のライブは終わった。
曲がりなりにも1年6か月活動し、定期的にライブ出演もできるようになってきた。
とは言え、高校生だけのへっぽこバンドの活動休止など、当人たち以外にとってはその日の昼食で何を食べるか以下のどうでも良い話題でしかない。
そうやって、誰にも知られず当人たちの胸の中にだけ残り、消えていくバンドはこの世界に星の数ほど存在している。
シータもその露あくたのひとつでしかないのだ。
「さらば、わが青春の日々」と言う事など到底憚れるような淡くぬるいバンド活動は、この日当たり前のように終了を告げた。
控室の戻ると、「お疲れぇ~っす」と他のバンドのメンバーから声を掛けられる。
「お先っす」と返すタクヤ。
「ほんとにこれで最後に。」
局長に小声で念を押すムラヤンに対して「分かってるよ。今日はお疲れ。」と返した。
「チョッと良いか?」
局長が椅子に座るか座らないかと言うタイミングで、タクヤが声をかけてきた。
「何?」
「外…いいか?」
「何だよ。誰かレイプでもするのか?」
「良く分かったな。」
ロビーの自動販売機の前に局長を連れてきたタクヤは「何か飲む?」と言いつつ局長がいつも飲んでいるリアルゴールドのボタンを押した。
「おごり?!いただきまぁ~す。」
無言で、リアルゴールドの入った紙コップを手渡すタクヤ。
何もしゃべらない。
「いや、ほんとに何なんだよ。」
局長は少し苛立ちながら、リアルゴールドを口に含みドカッとソファーに座った。
タクヤは座りもしないで、そのまま局長を見つめる。
「おい!ホントに…」
「マイノリティーボックスってバンド知ってるよな。」
やっとタクヤが口を開く。
「あぁ、よく一緒になる皆さんだよね。オレにはあのバンドの音楽性はあんまり良く分からないけど…それがどうしたの?」
「オレさぁ…あのバンドでベースやる事になった。」
それは突然のタクヤの告白だった。
「あのバンドでベースをやる事になった?」
その告白に少なからず動揺した局長は、オウム返しをする事しか出来ない。
「…それは…サポート?」
恐る恐るタクヤに尋ねる。
「最初はそのつもりだったんだけど、年末年始と音合わせしてるうちに意気投合してさぁ。…ボーカルの明石君に誘われて…」
罰が悪そうに足を何度も交差させ、頭をぼりぼりかきながらタクヤは「…正式にメンバーになる事になった。」と局長に告げた。
「そっか…」
一息つくために、局長はリアルゴールドを口に含んだ。
静かな市民会館のロビーでは、時計の秒針のコツコツと言う音さえもはっきり聞こえる。
局長は炭酸の刺激がいつもに増してチクチクと感じるなと考えながら、まるで他人事のようにタクヤからの説明を聞いていた。
その日は吹雪にも近い強い風が吹き、雪が舞い踊るように降っていた。
こんもり雪の積もったトイレ裏はさすがに寒すぎたため、タクヤと局長の2人は「これは無理。絶対死ぬ」と互いに意思確認をし、いそいそと演劇部の部室に逃げ込んだ。
部室内で他愛もない話をしながら、弁当箱を出したとき、ガラっと扉が開いた。
そこに立っていたのは、ムラヤンだった。
「??え?どうしたの?」
突然の事に驚く局長。
「いや…と言うか、どうしてお2人がここに?」
ムラヤンも戸惑っているようだ。
しばらくするとウルオがやってきた。
局長、タクヤと同じくクラスに居場所のない2人は、実は普段から演劇部の部室で昼を過ごしていたのだ。
たまたまこの日、局長とタクヤが大雪で部室に逃げ込んだため、図らずも4人が顔を合わすことになってしまった。
「あれぇ…」
ウルオが少し困ったような表情をしつつ、部室の中に入ってくる。
「珍しい人達がいるね…」
何だか気まずい時間が流れる。
無言…
無言…
無言…
…………
………………
………………………
「あのさぁ…」
その空気を破るようにタクヤが話し始めた。
「ムラヤンのいるトコで、こんな事言うのも気が引けるんだけど、丁度いいかなと思って…実はこの前のクリスマスライブの後、YAMAHA楽器の吉岡さんから声かけられてさ…」
「え?ライブの話?」
食い気味にウルオが訊ねる。
「まぁ、そうと言えばそうなんだけど、チョッと待て。」
ウルオを制止したタクヤは一息ついて、話を続けた。
「その時、吉岡さんに正直に話したんだよ。今、バンドは休止中でしばらくはライブに出られないって…そしたら、吉岡さんが最後に一度だけライブに出ないって。解散ライブをさ。」
「いや、別に解散ってわけじゃないんだけど。」
局長的には、その部分だけは突っ込まずにいられない。
「そうなんだけど、まぁ、学生バンドなんて休止したらそのまんまの場合が多いからな。」
タクヤは椅子に座り直し、ムラヤンの方を向いて意を決したように話し始めた。
「ムラヤン。この前の事は100%局長が悪かったと思う。」
「オレだけか!??」
立ち上がる局長。
「ムラヤンの辞めると言う話も当然だと思うんだ。でも、最後に1度だけケジメの意味で、ライブやらないか。その後は絶対ムラヤンを誘う事はないから。」
タクヤの話を聞いたムラヤンは、誰と目を合わせる訳でもなく視線を落とし、静かにバックから弁当箱を取り出し、おもむろに食べ始めた。
…
………
………………
「条件があるよ。」
義理堅く、責任感が強い。
そんなムラヤンは、真摯な姿勢で謝ってくれたタクヤに対して不義理を働くことなど到底出来るはずもない。
食べながらムラヤンは最後のライブに参加するための3つの条件を告げた。
これが絶対に最後である事。
事前にメロディーが分かるようにコピー曲をする事。
練習への参加を強制しない事。
タクヤはそれを全て快諾し最後に「ありがとう。ムラヤン。」と握手を求めた。
ムラヤンもそれに応える。
「おおお!もう一回ライブできるんだね!」
心なしか嬉しそうなウルオ。
「え…?もう決定?」
いつの間にか、コピー曲での解散ライブが決まってしまった事に戸惑う局長。
「け~ってい!」
タクヤはニヤニヤとしながら局長を見た。
「せめて、「スーパーフィニッシュ」はやらない。」
自分が蚊帳の外になっていることが不満な局長は、少しでも自分の意志が入り込むようにそう提案した。
前回、ハコフグの人に褒められた15秒ほどの短いシータライブ定番の曲だ。
「まぁ、それは大丈夫だからいいよ。」
ムラヤンはしぶしぶそれを承諾。
その時、再びガラッと部室の扉が開いた。
「声が聞こえてきたから覗いてみた…ん…だけど……あ!…あけましておめでとうございます。」
部室の中を覗き込み、ペコリと頭を下げたのは守山明美だった。
ジャンヌダルクの映画を見に行って以来だ。
「部長じゃないですか!お久しぶりです。」
「もう部長じゃないけどね…」
「いや、いつになってもオレにとっては部長ですよ。」
タクヤと守山はそう言って2人でケラケラ笑っている。
無思慮な2人は、あの日のことなど何もなかったように当たり前に会話を交わしている。
「あけましておめでとうございます!」
「おめでとうございます。」
ウルオとムラヤンも挨拶をする。
まだかなりあの日の事を引きずっていた局長だけが、何だか気まずいままでいた。
「高井君もおめでとうございます。」
改めて、ペコリと頭を下げた守山。
「おめでとうございます…」
やっとそれだけ口にすることが出来た。
ニュース第一高校では、3年生は受験のため2学期後半から授業はなくなり、別に毎日出席する必要がない。
守山は、総文祭が終わったあとからは基本的には学校の図書室で勉強をし、昼休みだけ局長たちのいるトイレ裏にやってくると言う日々を過ごしていた。
12月後半に入ったあたりから最後の追い込みで、学校自体に来なくなっていた。
あの日以降学校(と言うか、トイレ裏)に来なくなったことを局長が気にしていると勘付いた守山は、自身を取り巻く現状について必要以上に詳しく話した。
最後に「でもお陰で志望校A判定出たんだ。」と告げ、左手でピースマークを作って見せた。
「今日は、その判定を聞きに久々に学校に来たんだよ。そしたら、部室から声が聞こえるからさ…」
タイミングが良いのか、悪いのか良く分からない。
ただタクヤはここぞとばかりに邪な心意気で「実は今、次のライブの話をしていたんです」と守山に告げた。
「えええ!凄い!あたしもやっと少し余裕が出来てきたから、行きたい行きたい!何日?」
「そう言えば、何日なんだ?」
局長がタクヤに尋ねる。
「1月23日。再来週の日曜日だな。」
「お前!それ、あと2週間チョイしかないじゃないか!」
「まぁ、今回はコピー曲だし大丈夫だろ?」
ムラヤンが「うんうん」と深くうなずいている。
「一応、今回でシータは最後なんですよ!」
ウルオが一言付け加える。
「え…バンド辞めるの。」
守山が戸惑う。
「ムラヤンがボーカル辞めることになって…バンドは解散しないんですけど、一応、これ以降については未定と言うか…」
「そうなんだ…」
守山はそうつぶやくと、暗い表情で俯いてしまった。
「いや、まぁ絶対に今回で最後ってわけじゃあないので!な!局長。」
タクヤが無理から元気そうに局長の肩を組んだ。
「先の事なんか分かんないですよ。ただ、オレもやめる気はなくて、今も新曲書いたりしてるし。」
局長は、守山の表情を見て不意に出まかせを言った。
本当は、新曲なんてあれ以来1曲も書いていない。
「いや、そうじゃなくて…実はね…その…志望校の入試試験が24日なんだ。受験するために23日は京都に居るんだよね…最後のライブなのに行けないよぉ…」
守山が受けようとしていたニュース大学は京都にあり、朝から始まる入学試験の為には、前日ホテルで宿泊する必要があったのだ。
「入試諦めて、別の大学行こうか…」
「いやいやいやいや…部長!そこは、入試受けてくださいよ!オレらのライブなんてほんとどうでも良いので。」
守山の発言に対して、タクヤが強く是正した。
「だって、シータは最後なんでしょ。」
「だから、最後かどうかも分からないし…せっかくA判定出たんでしょ。」
流石の局長もここはタクヤと同意見だった。
「残念だなぁ…」
誰がどう見ても分かるように、あからさまに守山は落ち込んでいる。
「あ…!そうだ!実は、今回でムラヤンが一旦辞めるので、これまでの音源をまとめた作品集みたいなのを作ってるんですよ。部長にはそれをプレゼントしますよ!」
「お前!そんなもの作ってたのか?」
タクヤが驚いたような顔で局長を見る。
もちろんその場しのぎの出まかせだ。
そんなもの作っているわけがない。
局長は何となく、沈み込んでいる守山の表情を見て、少しでも元気になってほしくてしょうがなかったのだ。
「凄い!そんなものがあるの?」
「はい。タイトルは「朝日が目に染みた赤フン達」と言います。」
これも出まかせだった。
「じゃあ…今回はそれで我慢するよ。」
守山はしぶしぶ納得し「お邪魔しましたぁ~」と言いクルッと1回転した後、ペコリと頭を下げ部室を後にした。
その日の部活で、黒崎たちにもライブの事を話した。
黒崎、白石、藤本、赤城たちはライブを見に行くことを、もちろん快諾した。
残された時間は2週間。
文化祭で演奏したGLAYのコピー曲をメインにセットリストを組んだ。
文化祭に参加していなかった啓司は「期間が短すぎる」とぶつぶつ文句を言っていたが、久々のコピー曲演奏については楽しそうにしているようだった。
楽譜通りに弾く事に何の魅力も感じない局長にとって、10月の時のような熱狂や酔狂は何もない。
2週間はあっという間に過ぎていった。
そして当日。
ライブ会場は、何の因果か「付喪神」公演を行った市民会館だった。
これで最後と言う感慨も何もないまま、ライブは開幕し、シータメンバーはそのライブ自体を無難にこなしていく。
これまで、どのライブでも感じていたような達成感と喪失感は全くなかった。
こんな形でシータの活動は終わってしまって良いのか。
局長はライブ中、何度も何度も自問自答を繰り返した。
ライブ最後の曲は、初めてシータを結成した中学校の文化祭で演奏した思い出の曲「GLAY」の「HOWEVER」。
だがしかし、それに対しても何も思う事はない。
今回は演奏後のインタビューのようなものもない普通のライブイベント。
勿論解散することについて、公に発表する機会などあるはずもない。
1バンドとして出演し、当たり障りのない、よく言えば無難な、悪く言えば誰の記憶にも残らない演奏で、ひっそりと最後のライブは終わった。
曲がりなりにも1年6か月活動し、定期的にライブ出演もできるようになってきた。
とは言え、高校生だけのへっぽこバンドの活動休止など、当人たち以外にとってはその日の昼食で何を食べるか以下のどうでも良い話題でしかない。
そうやって、誰にも知られず当人たちの胸の中にだけ残り、消えていくバンドはこの世界に星の数ほど存在している。
シータもその露あくたのひとつでしかないのだ。
「さらば、わが青春の日々」と言う事など到底憚れるような淡くぬるいバンド活動は、この日当たり前のように終了を告げた。
控室の戻ると、「お疲れぇ~っす」と他のバンドのメンバーから声を掛けられる。
「お先っす」と返すタクヤ。
「ほんとにこれで最後に。」
局長に小声で念を押すムラヤンに対して「分かってるよ。今日はお疲れ。」と返した。
「チョッと良いか?」
局長が椅子に座るか座らないかと言うタイミングで、タクヤが声をかけてきた。
「何?」
「外…いいか?」
「何だよ。誰かレイプでもするのか?」
「良く分かったな。」
ロビーの自動販売機の前に局長を連れてきたタクヤは「何か飲む?」と言いつつ局長がいつも飲んでいるリアルゴールドのボタンを押した。
「おごり?!いただきまぁ~す。」
無言で、リアルゴールドの入った紙コップを手渡すタクヤ。
何もしゃべらない。
「いや、ほんとに何なんだよ。」
局長は少し苛立ちながら、リアルゴールドを口に含みドカッとソファーに座った。
タクヤは座りもしないで、そのまま局長を見つめる。
「おい!ホントに…」
「マイノリティーボックスってバンド知ってるよな。」
やっとタクヤが口を開く。
「あぁ、よく一緒になる皆さんだよね。オレにはあのバンドの音楽性はあんまり良く分からないけど…それがどうしたの?」
「オレさぁ…あのバンドでベースやる事になった。」
それは突然のタクヤの告白だった。
「あのバンドでベースをやる事になった?」
その告白に少なからず動揺した局長は、オウム返しをする事しか出来ない。
「…それは…サポート?」
恐る恐るタクヤに尋ねる。
「最初はそのつもりだったんだけど、年末年始と音合わせしてるうちに意気投合してさぁ。…ボーカルの明石君に誘われて…」
罰が悪そうに足を何度も交差させ、頭をぼりぼりかきながらタクヤは「…正式にメンバーになる事になった。」と局長に告げた。
「そっか…」
一息つくために、局長はリアルゴールドを口に含んだ。
静かな市民会館のロビーでは、時計の秒針のコツコツと言う音さえもはっきり聞こえる。
局長は炭酸の刺激がいつもに増してチクチクと感じるなと考えながら、まるで他人事のようにタクヤからの説明を聞いていた。

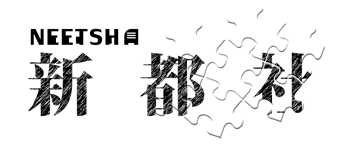

しもたろうに 先生に励ましのお便りを送ろう!!
〒みんなの感想を読む