ひとときの暗がり
作:しもたろうに
[website]
![]()

+
「シータの皆さん、お願いします。」
先程と同じスタッフが控室に入り、声をかけてきた。
「行くか…」
タクヤがベースにストラップをつけ、肩にかけながら声をかける。
「ちょ…あと1回だけシューティングオブハートやって…」
「もう時間だって…あとはなるようになるさ。」
そう言って準備をし始めた局長を横目に「もう知らないよ」とムラヤンは諦めた表情で呟いた。
なぜか意気揚々とステージに向かう局長と死刑宣告を受けたかのように重い足取りのムラヤン。
その後ろから、タクヤと啓司が無言でついていく。
ウルオは、スティックを忘れていたことを思い出し、控室に小走りで戻っていった。
ステージ袖に行くと「では、お願いします!」とそのままステージへ促された。
先程のリハと比べて、何だかステージが大きく感じる。
パチパチパチとまばらな拍手が起きる中、ステージ上で、スタンバイを始めるメンバー。
ドラムセットのスネアはやはり高くなっていた。
「まただよ…」
ウルオは諦めたように、リハーサルと同じように調整を行う。
客席の方を見た局長の目に、ステージ最前列に並んでいる演劇部の面々が写った。
赤城や藤本まで来てくれているようだ。
後ろまでははっきり見えないが、相当の席が埋まっている。
吉岡は600人位と言っていたが、流石にそこまでの人数ではないだろう。
そう信じたい。
それでも、前回のライブと比べるべくもないほどの人の視線がステージに向けられていた。
ウルオが「出来たよ」と話すと、意を決したようにムラヤンが大きく息を吸った。
「皆さん。おはようございます!シータでございます!」
客電が消え、ステージのライトがパッとついた。
先程とは違い大きな拍手が起きる。
「こんな沢山の人の前で歌ったことないので緊張してます。失敗しても許してください。」
「大丈夫だよぉ!落ち着いて!」
ステージに寄りかかっている赤城が大きな声で叫んだ。
「ありがとうございます!では、まず1曲目聞いてください。新曲です。ランナウェイ。」
ウルオのちっちっちっちと言うリズムから16ビートが刻まれる。
前回と違い、はっきり意識が残っていた局長は落ち着いて鍵盤に指を置いた。
リハーサルと同じように自分の弾くフレーズはしっかりとモニター用アンプを通して自分の耳に入ってくる。
不協和音にならないように慎重に、それでいて体全身でリズムを取りながら演奏を続けた。
間奏に入り啓司のギターソロに入るか入らないかと言うタイミングで突如「ぎゃあああああああああああああああ!」と言う声が聞こえドラムがストップした。
局長は驚いてウルオの方を見た。
「足が…足がツった…」
ここ最近酷使され続けたウルオの右足が、緊張も相まって思いっきりツってしまったようだ。
啓司はチョッと狼狽えながらそのままギターソロを弾き続けた。
それを見て、タクヤも演奏を続ける。
演奏が止まらなかったため、ウルオは決意したように足の激痛に耐えながら必死で姿勢を戻そうとした。
局長にはそのウルオの姿がなぜかどうしようもなく滑稽に見え、つい「ぎゃはははははははは!!」と爆笑してしまった。
ハモリの為に局長の前に置かれていたマイクがその声をしっかりと拾い、啓司のギターソロにあわせて客席に鳴り響く。
その笑い声の最後に合わせたかのように、ウルオは痛みに耐えつつドラム演奏を再開した。
たまたま絶妙なタイミングだったため、そのまま演奏を続けることができ、奇跡的に無事演奏しきることが出来たのだ。
「ありがとうございました。」とムラヤンが挨拶すると、客席からは盛大な拍手。
「ピューピュー」と指笛を吹いてる人もいた。
2曲目は問題の「シューティングオブハート」。
事前に局長がイメージカラーとして「赤」を伝えていたため、ステージ上が真っ赤になる。
「2曲目行きます。シューティングオブハート。」
ムラヤンのその声で、ちっちっちっちウルオはカウントを取り始めた。
ウルオは足が痛むのだろう、いつもにましてよれよれのリズムだ。
他のメンバーもそれぞれ自信なさげな演奏をしている。
ボーカルが入るタイミングになった。
だがしかし、ムラヤンは歌わない。
局長はこの段階で重大なミスに気が付いた。
ちゃんと演奏を聴いたこともなかったムラヤンは、そもそもどこまでが前奏でどこからボーカルが入るのか知る由もなかったのだ。
メロディーがどうのこうの以前の話だった。
そんな状態で歌えるわけがない。
ただ、今は演奏を続けるしかない。
局長は全てを諦めて演奏を続けた。
そしてサビに入る。
タクヤは、タイミングを見て、自分で考えたハモリ部分だけを歌う。
それでも、もちろんムラヤンは何も歌えない。
往年のルナシーRYOUICHIの如くマイクに手を置いてはいる。
何かを歌おうとはしているのだろう。
だが歌わない。
いや、歌えない。
振りだけをしている状態が続いた。
間奏に入ったタイミングでムラヤンは突然「wow~wow~」と謎の合いの手を入れ始めた。
歌う事を諦めたムラヤンは、アップテンポな演奏に合いの手を入れることで、何となくやり過ごそうとしたのだ。
局長はこれ以上ムラヤンが歌わないだろうことを考え、急遽ギターソロ後の最後のサビで、本来考えていた演奏を行わずに、メロディーラインをそのまま弾いた。
そのメロディーラインを聴いたムラヤンはサビであることを理解し、サビの「君のピュアなハートをバンディット」の部分だけを歌うことが出来た。
そしてまた「wow~wow~」と続ける。
結局、タクヤ初のオリジナル曲「シューティングオブハート」は実に不本意な形のまま発表されることになってしまった。
次の曲「始まりの終末~ファーストエンド」。
局長のアルペジオから始まり、次第に激しい演奏になっていくという編曲。
緊張しながら、局長は最初のアルペジオ部分を弾いていく。
演奏中ステージ前に居た守山の顔を見た。
満足げにリズムを取っている。
自分の作った曲が演奏されていることに気が付いたのだろう。
局長がよそ見していて不協和音が出てしまったこと以外は、ある程度しっかり練習していたため問題なく演奏出来た。
そして繰り返される盛大な拍手。
「先程から新曲ですと紹介してましたが、実は、今日やる曲は全て新曲なんです。」
ムラヤンのMCに客席からは「おおおおおおおおおおおおおおおおお!」と言う声と「もともと全部知らねぇよ!」と言う煽りが同時上がる。
「そして次の曲は、なんと僕も知らない新曲です。聞いてください。街灯の光。」
そう言うと、客席からは「ドッ」と笑いが起きた。
洒落たMCだと思われたのだろう。
ただそれは、ムラヤンにとって切実な真実でしかない。
局長は先程の「シューティングオブハート」の事を考え、練習していた自分のパートを捨て、最初からメロディーラインを弾いた。
ムラヤンはそれに合わせて「wow~wow~」とさっきと同じ合いの手を入れる。
当然メロディーラインを歌う気はないようだ。
ミディアムテンポの「街灯の光」を局長はグリーンのイメージで照明さんに伝えていたため、ムラヤンだけに緑のピンスポが当たった。
真っ暗なステージで、緑色に浮かび上がるムラヤン。
メロディーラインが分からないムラヤンの悲し気な「wow~wow~」がとても抒情的な雰囲気を醸し出していた。
練習通り全員がずれたまま演奏していたので、演奏が終わった後も局長だけは終わっておらず、そのままメロディラインを弾き続けた。
それが実にしっとりとしたアンニュイな終わりを演出した・・・様だ。
今日一番の拍手が起こる。
「え…え~と…ありがとうございました。次で最後の曲になります。」
少し戸惑いつつ、ムラヤンがそう言うと「いやだぁ!」「もっとやって」とお約束のレスポンスが返ってきた。
「ありがとうございます。このまましっとりと歌います。最後の曲「約束の場所で」。」
この曲も局長のアルペジオから始まる。
前回、無理やりアップテンポに変えて演奏した「森を抜けた先にある闇」を本来のバラードに戻し、歌詞を書き換え譜割を修正して出来上がった「約束の場所で」。
シータ唯一のバラードナンバーだ。
ムラヤンもこの曲はしっかりメロディラインを把握している。
問題なく演奏しきったあと、本当の最後の曲。
お決まりの「スーパーフィニッシュ」。
15秒ほどの激しい前奏のあと「え?終わり?」とムラヤンが異常に嘘くさい演技でつぶやき、「ありがとうございましたぁあああああ!!」と叫んだ。
その声を契機に、シータのメンバーは全員逃げるようにステージからはけていった。
大きな拍手、「ピューピュー」と指笛が聞こえる中、メンバー5人は本当に走りながらステージ袖に駆け込む。
ステージ袖に来ると待機していたスタッフが「リーダーの人、インタビューインタビュー」と小声で何度か繰り返している。
「お前行ってこい!」
タクヤが局長を押し出した。
「またオレ?」
「頑張れ!リーダー。」
ウルオがまだ痛い右足を引きずりながら拍手している。
局長がステージに再び戻ると、ミニスカートに生足のお姉さんがマイクをもってステージ下手に立っていた。
ライブの司会をするお姉さんは極端なミニスカート履かなければいけないルールでもあるのだろうか。
ステージ下からは確実にパンツ丸見えだな。どうせ見せパンだろうけど…などと考えながら、局長はそのお姉さんのもとへ。
「お疲れさまでしたぁ。」
「あ…ありがとうございます。」
「今回全部新曲と言う事だったんですが、このライブの為に作られたんですか?」
唐突に始まるインタビューに少し狼狽えながら局長は答える。
「あ…ええ…そんな感じです。でも、全然時間がなくて、ちゃんと演奏できませんでした。」
「ええ?本当ですか?なんか凄く良かったですよ。」
「そうですか…?…全然思ってた感じにできなかったんですけど…」
「今回シータの皆さんには、注目の新人バンドと言う事で出演してもらったんですが…」
「そう言えば、何か、そう言う事言われた気が…します。…嬉しいですけど、僕たちはこんなすごい所で演奏出来る感じじゃなかったです。…何かすみません。」
「いえいえ。今日朝から色んなバンドの曲を聞いてきましたけど、ワンフレーズだけ歌う不思議なインスト曲があったり、途中でドラムを止めて笑い声をきっかけに再開したり、チョッと一味違うと言うか…流石注目の新人バンドって感じでしたよ!」
「イン…スト曲…?!」
「インスト曲って演奏力もかなりいるでしょう?なかなか手を出しにくいと思うんですよね。特に4曲目とか、抒情的ですごく良かったです。」
「あ…あれ、街灯の光って曲なんですけど…」
「物悲しい雰囲気にぴったりの曲名ですね。インスト曲で、あのイメージを出すのは相当苦労されたんじゃないですか。」
「え…え~と…少し歌ってたのでインスト曲…えぇ~と…インスト曲…あれはインスト曲…なのかな…・?」
「え…?あれ?…あ、いや、そういう認識じゃなかったんですか?すみません…」
「いやいや、あれはインスト曲で良いと思います。」
「そうなんですか。」
「はい。もうバリバリのインスト曲です。」
「これからもライブとか続けられるんでしょうか。」
「一応その予定です。」
「そうなんですね。また素敵な演奏を聴かせてくださいね。シータの皆さんでした。」
パチパチとまばらなは拍手が起こった。
「良かったよぉ!」と言う守山の声が聞こえた気がした。
ヨロヨロとステージから廊下に降りていき、ぼやけた頭をブンブン振りながら控室に向かう。
控室を開けると、演劇部の面々が来ていた。
「演劇とはまた違ってかっこよかった!」
テンション高く話しかける白石に、タクヤは「いや、どうなんだろう」と満更でもなさそうな表情で答えていた。
「いや、足がピーンってなんったんですけど、頑張って最後までやりましたよ!」
「あれ、演出じゃなかったんだ?」
「急にドラムが止まったからビックリしたけど僕まで止まっちゃあいけないと思って、弾き続けたんだ。」
啓司とウルオはライブ最中に足がツった事を武勇伝の様に、藤本、赤城と楽しそうに語っている。
「あ!高井君。お疲れ様。」
インタビュー後そのまま控室に直行していた守山が、戻ってきた局長に気が付き声をかけた。
「あぁ、今回も来てくれてありがとうございます。何か、前回は来てくれたのに最後お礼言えなかったし…」
「いやいや。それより、私の曲使ってくれたんだね。ありがとう!」
「良い曲だったのに、編曲うまくできなくてすみません…」
「全然!そんな事ないよ。まさか、一つはインストになるとは思わなかったけど…」
「インスト…」
局長は少し複雑な表情でムラヤンを見た。
ムラヤンは疲れ切った顔で椅子に座っている。
「今回の曲、部長が作ったんですか?」
黒崎は驚いたように尋ねてきた。
「3曲目と4曲目、ファーストエンドと街灯の光って曲がそうですよ。」
局長は説明した。
「いいなぁ~あたしも曲とか作って、こんな大きなステージで歌いたいな。」
「くーちゃんもバンドやったらいいのに。絶対見に行くよ!」
「部長ホントですか。あたしもバンド組みたくなってきた。部長いっしょにやりません?」
「え~あたしは無理だよぉ。」
守山と黒崎は局長をよそに2人で盛り上がり始めた。
その様子を見た局長は、「ふ~」とため息をついて奥の椅子に腰かける。
横でうなだれているムラヤンが小声で「これが限界です」とつぶやいた。
「実は思ってた以上に面白い事になってたよ。また、詳しくは今度話す。取り合えずお疲れ様。」
局長がそう言うと、ムラヤンの頭の上には「?」が10個ほど浮かんだ。
雑然と盛り上がる控室内を見渡し、やっと局長も少しずつ実感が湧いてきた。
何とかホールライブを終えることが出来たようだ。
どう考えても無理やりなスケジュールを演劇と同時進行でこなしながら、新曲5曲30分のライブをやり切った。
結果云々以前にやり遂げたと言う達成感がふんわりと局長をまとい始めていた。
ただ、安堵と同時に、今日のライブの為に一日練習が出来なかった「付喪神」が果たして完成するのかと言う次の課題が否応なしにも浮かんでくる。
ライブが終わった事を労いたい。
でも、総文祭までは糸を切らすわけにはいかない。
2つの思考が脳内を、まるでメリーゴーランドの様に音を出して無限に回り続けた。
くるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくる狂くる狂くるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくる狂狂狂狂狂狂狂狂…
そんな局長の様子を見ていたタクヤは、そっと局長の肩に手を置いて「今日はもう休もうぜ」と声をかけた。
ステージでは昼休憩中のエキシビジョンとして、主催会社「ハコフグ」スタッフで結成されたバンド「ハコフグオールスターズ」がセックスマシンガンズの「みかんのうた」を演奏している。
「みかんのうた」を尻目に、シータメンバーと演劇部の面々は会場を後にした。
近くにある有名なうどん屋「おかせん」で食事とした後、そのまま解散。
演劇部の面々は、テンション高くそのままカラオケに行くようだ。
局長はそんな気分にはなれないまま、静かに帰路についた。
他のシータメンバーも同じようだ。
背負っているキーボードがいつもよりずっしりと肩に食い込んでいるような気がした。
その日、家に帰った局長は10月に入って初めてゆっくり眠った。
12時間以上寝たはずが、体感時間は1秒にも満たない深い深い睡眠だった。
先程と同じスタッフが控室に入り、声をかけてきた。
「行くか…」
タクヤがベースにストラップをつけ、肩にかけながら声をかける。
「ちょ…あと1回だけシューティングオブハートやって…」
「もう時間だって…あとはなるようになるさ。」
そう言って準備をし始めた局長を横目に「もう知らないよ」とムラヤンは諦めた表情で呟いた。
なぜか意気揚々とステージに向かう局長と死刑宣告を受けたかのように重い足取りのムラヤン。
その後ろから、タクヤと啓司が無言でついていく。
ウルオは、スティックを忘れていたことを思い出し、控室に小走りで戻っていった。
ステージ袖に行くと「では、お願いします!」とそのままステージへ促された。
先程のリハと比べて、何だかステージが大きく感じる。
パチパチパチとまばらな拍手が起きる中、ステージ上で、スタンバイを始めるメンバー。
ドラムセットのスネアはやはり高くなっていた。
「まただよ…」
ウルオは諦めたように、リハーサルと同じように調整を行う。
客席の方を見た局長の目に、ステージ最前列に並んでいる演劇部の面々が写った。
赤城や藤本まで来てくれているようだ。
後ろまでははっきり見えないが、相当の席が埋まっている。
吉岡は600人位と言っていたが、流石にそこまでの人数ではないだろう。
そう信じたい。
それでも、前回のライブと比べるべくもないほどの人の視線がステージに向けられていた。
ウルオが「出来たよ」と話すと、意を決したようにムラヤンが大きく息を吸った。
「皆さん。おはようございます!シータでございます!」
客電が消え、ステージのライトがパッとついた。
先程とは違い大きな拍手が起きる。
「こんな沢山の人の前で歌ったことないので緊張してます。失敗しても許してください。」
「大丈夫だよぉ!落ち着いて!」
ステージに寄りかかっている赤城が大きな声で叫んだ。
「ありがとうございます!では、まず1曲目聞いてください。新曲です。ランナウェイ。」
ウルオのちっちっちっちと言うリズムから16ビートが刻まれる。
前回と違い、はっきり意識が残っていた局長は落ち着いて鍵盤に指を置いた。
リハーサルと同じように自分の弾くフレーズはしっかりとモニター用アンプを通して自分の耳に入ってくる。
不協和音にならないように慎重に、それでいて体全身でリズムを取りながら演奏を続けた。
間奏に入り啓司のギターソロに入るか入らないかと言うタイミングで突如「ぎゃあああああああああああああああ!」と言う声が聞こえドラムがストップした。
局長は驚いてウルオの方を見た。
「足が…足がツった…」
ここ最近酷使され続けたウルオの右足が、緊張も相まって思いっきりツってしまったようだ。
啓司はチョッと狼狽えながらそのままギターソロを弾き続けた。
それを見て、タクヤも演奏を続ける。
演奏が止まらなかったため、ウルオは決意したように足の激痛に耐えながら必死で姿勢を戻そうとした。
局長にはそのウルオの姿がなぜかどうしようもなく滑稽に見え、つい「ぎゃはははははははは!!」と爆笑してしまった。
ハモリの為に局長の前に置かれていたマイクがその声をしっかりと拾い、啓司のギターソロにあわせて客席に鳴り響く。
その笑い声の最後に合わせたかのように、ウルオは痛みに耐えつつドラム演奏を再開した。
たまたま絶妙なタイミングだったため、そのまま演奏を続けることができ、奇跡的に無事演奏しきることが出来たのだ。
「ありがとうございました。」とムラヤンが挨拶すると、客席からは盛大な拍手。
「ピューピュー」と指笛を吹いてる人もいた。
2曲目は問題の「シューティングオブハート」。
事前に局長がイメージカラーとして「赤」を伝えていたため、ステージ上が真っ赤になる。
「2曲目行きます。シューティングオブハート。」
ムラヤンのその声で、ちっちっちっちウルオはカウントを取り始めた。
ウルオは足が痛むのだろう、いつもにましてよれよれのリズムだ。
他のメンバーもそれぞれ自信なさげな演奏をしている。
ボーカルが入るタイミングになった。
だがしかし、ムラヤンは歌わない。
局長はこの段階で重大なミスに気が付いた。
ちゃんと演奏を聴いたこともなかったムラヤンは、そもそもどこまでが前奏でどこからボーカルが入るのか知る由もなかったのだ。
メロディーがどうのこうの以前の話だった。
そんな状態で歌えるわけがない。
ただ、今は演奏を続けるしかない。
局長は全てを諦めて演奏を続けた。
そしてサビに入る。
タクヤは、タイミングを見て、自分で考えたハモリ部分だけを歌う。
それでも、もちろんムラヤンは何も歌えない。
往年のルナシーRYOUICHIの如くマイクに手を置いてはいる。
何かを歌おうとはしているのだろう。
だが歌わない。
いや、歌えない。
振りだけをしている状態が続いた。
間奏に入ったタイミングでムラヤンは突然「wow~wow~」と謎の合いの手を入れ始めた。
歌う事を諦めたムラヤンは、アップテンポな演奏に合いの手を入れることで、何となくやり過ごそうとしたのだ。
局長はこれ以上ムラヤンが歌わないだろうことを考え、急遽ギターソロ後の最後のサビで、本来考えていた演奏を行わずに、メロディーラインをそのまま弾いた。
そのメロディーラインを聴いたムラヤンはサビであることを理解し、サビの「君のピュアなハートをバンディット」の部分だけを歌うことが出来た。
そしてまた「wow~wow~」と続ける。
結局、タクヤ初のオリジナル曲「シューティングオブハート」は実に不本意な形のまま発表されることになってしまった。
次の曲「始まりの終末~ファーストエンド」。
局長のアルペジオから始まり、次第に激しい演奏になっていくという編曲。
緊張しながら、局長は最初のアルペジオ部分を弾いていく。
演奏中ステージ前に居た守山の顔を見た。
満足げにリズムを取っている。
自分の作った曲が演奏されていることに気が付いたのだろう。
局長がよそ見していて不協和音が出てしまったこと以外は、ある程度しっかり練習していたため問題なく演奏出来た。
そして繰り返される盛大な拍手。
「先程から新曲ですと紹介してましたが、実は、今日やる曲は全て新曲なんです。」
ムラヤンのMCに客席からは「おおおおおおおおおおおおおおおおお!」と言う声と「もともと全部知らねぇよ!」と言う煽りが同時上がる。
「そして次の曲は、なんと僕も知らない新曲です。聞いてください。街灯の光。」
そう言うと、客席からは「ドッ」と笑いが起きた。
洒落たMCだと思われたのだろう。
ただそれは、ムラヤンにとって切実な真実でしかない。
局長は先程の「シューティングオブハート」の事を考え、練習していた自分のパートを捨て、最初からメロディーラインを弾いた。
ムラヤンはそれに合わせて「wow~wow~」とさっきと同じ合いの手を入れる。
当然メロディーラインを歌う気はないようだ。
ミディアムテンポの「街灯の光」を局長はグリーンのイメージで照明さんに伝えていたため、ムラヤンだけに緑のピンスポが当たった。
真っ暗なステージで、緑色に浮かび上がるムラヤン。
メロディーラインが分からないムラヤンの悲し気な「wow~wow~」がとても抒情的な雰囲気を醸し出していた。
練習通り全員がずれたまま演奏していたので、演奏が終わった後も局長だけは終わっておらず、そのままメロディラインを弾き続けた。
それが実にしっとりとしたアンニュイな終わりを演出した・・・様だ。
今日一番の拍手が起こる。
「え…え~と…ありがとうございました。次で最後の曲になります。」
少し戸惑いつつ、ムラヤンがそう言うと「いやだぁ!」「もっとやって」とお約束のレスポンスが返ってきた。
「ありがとうございます。このまましっとりと歌います。最後の曲「約束の場所で」。」
この曲も局長のアルペジオから始まる。
前回、無理やりアップテンポに変えて演奏した「森を抜けた先にある闇」を本来のバラードに戻し、歌詞を書き換え譜割を修正して出来上がった「約束の場所で」。
シータ唯一のバラードナンバーだ。
ムラヤンもこの曲はしっかりメロディラインを把握している。
問題なく演奏しきったあと、本当の最後の曲。
お決まりの「スーパーフィニッシュ」。
15秒ほどの激しい前奏のあと「え?終わり?」とムラヤンが異常に嘘くさい演技でつぶやき、「ありがとうございましたぁあああああ!!」と叫んだ。
その声を契機に、シータのメンバーは全員逃げるようにステージからはけていった。
大きな拍手、「ピューピュー」と指笛が聞こえる中、メンバー5人は本当に走りながらステージ袖に駆け込む。
ステージ袖に来ると待機していたスタッフが「リーダーの人、インタビューインタビュー」と小声で何度か繰り返している。
「お前行ってこい!」
タクヤが局長を押し出した。
「またオレ?」
「頑張れ!リーダー。」
ウルオがまだ痛い右足を引きずりながら拍手している。
局長がステージに再び戻ると、ミニスカートに生足のお姉さんがマイクをもってステージ下手に立っていた。
ライブの司会をするお姉さんは極端なミニスカート履かなければいけないルールでもあるのだろうか。
ステージ下からは確実にパンツ丸見えだな。どうせ見せパンだろうけど…などと考えながら、局長はそのお姉さんのもとへ。
「お疲れさまでしたぁ。」
「あ…ありがとうございます。」
「今回全部新曲と言う事だったんですが、このライブの為に作られたんですか?」
唐突に始まるインタビューに少し狼狽えながら局長は答える。
「あ…ええ…そんな感じです。でも、全然時間がなくて、ちゃんと演奏できませんでした。」
「ええ?本当ですか?なんか凄く良かったですよ。」
「そうですか…?…全然思ってた感じにできなかったんですけど…」
「今回シータの皆さんには、注目の新人バンドと言う事で出演してもらったんですが…」
「そう言えば、何か、そう言う事言われた気が…します。…嬉しいですけど、僕たちはこんなすごい所で演奏出来る感じじゃなかったです。…何かすみません。」
「いえいえ。今日朝から色んなバンドの曲を聞いてきましたけど、ワンフレーズだけ歌う不思議なインスト曲があったり、途中でドラムを止めて笑い声をきっかけに再開したり、チョッと一味違うと言うか…流石注目の新人バンドって感じでしたよ!」
「イン…スト曲…?!」
「インスト曲って演奏力もかなりいるでしょう?なかなか手を出しにくいと思うんですよね。特に4曲目とか、抒情的ですごく良かったです。」
「あ…あれ、街灯の光って曲なんですけど…」
「物悲しい雰囲気にぴったりの曲名ですね。インスト曲で、あのイメージを出すのは相当苦労されたんじゃないですか。」
「え…え~と…少し歌ってたのでインスト曲…えぇ~と…インスト曲…あれはインスト曲…なのかな…・?」
「え…?あれ?…あ、いや、そういう認識じゃなかったんですか?すみません…」
「いやいや、あれはインスト曲で良いと思います。」
「そうなんですか。」
「はい。もうバリバリのインスト曲です。」
「これからもライブとか続けられるんでしょうか。」
「一応その予定です。」
「そうなんですね。また素敵な演奏を聴かせてくださいね。シータの皆さんでした。」
パチパチとまばらなは拍手が起こった。
「良かったよぉ!」と言う守山の声が聞こえた気がした。
ヨロヨロとステージから廊下に降りていき、ぼやけた頭をブンブン振りながら控室に向かう。
控室を開けると、演劇部の面々が来ていた。
「演劇とはまた違ってかっこよかった!」
テンション高く話しかける白石に、タクヤは「いや、どうなんだろう」と満更でもなさそうな表情で答えていた。
「いや、足がピーンってなんったんですけど、頑張って最後までやりましたよ!」
「あれ、演出じゃなかったんだ?」
「急にドラムが止まったからビックリしたけど僕まで止まっちゃあいけないと思って、弾き続けたんだ。」
啓司とウルオはライブ最中に足がツった事を武勇伝の様に、藤本、赤城と楽しそうに語っている。
「あ!高井君。お疲れ様。」
インタビュー後そのまま控室に直行していた守山が、戻ってきた局長に気が付き声をかけた。
「あぁ、今回も来てくれてありがとうございます。何か、前回は来てくれたのに最後お礼言えなかったし…」
「いやいや。それより、私の曲使ってくれたんだね。ありがとう!」
「良い曲だったのに、編曲うまくできなくてすみません…」
「全然!そんな事ないよ。まさか、一つはインストになるとは思わなかったけど…」
「インスト…」
局長は少し複雑な表情でムラヤンを見た。
ムラヤンは疲れ切った顔で椅子に座っている。
「今回の曲、部長が作ったんですか?」
黒崎は驚いたように尋ねてきた。
「3曲目と4曲目、ファーストエンドと街灯の光って曲がそうですよ。」
局長は説明した。
「いいなぁ~あたしも曲とか作って、こんな大きなステージで歌いたいな。」
「くーちゃんもバンドやったらいいのに。絶対見に行くよ!」
「部長ホントですか。あたしもバンド組みたくなってきた。部長いっしょにやりません?」
「え~あたしは無理だよぉ。」
守山と黒崎は局長をよそに2人で盛り上がり始めた。
その様子を見た局長は、「ふ~」とため息をついて奥の椅子に腰かける。
横でうなだれているムラヤンが小声で「これが限界です」とつぶやいた。
「実は思ってた以上に面白い事になってたよ。また、詳しくは今度話す。取り合えずお疲れ様。」
局長がそう言うと、ムラヤンの頭の上には「?」が10個ほど浮かんだ。
雑然と盛り上がる控室内を見渡し、やっと局長も少しずつ実感が湧いてきた。
何とかホールライブを終えることが出来たようだ。
どう考えても無理やりなスケジュールを演劇と同時進行でこなしながら、新曲5曲30分のライブをやり切った。
結果云々以前にやり遂げたと言う達成感がふんわりと局長をまとい始めていた。
ただ、安堵と同時に、今日のライブの為に一日練習が出来なかった「付喪神」が果たして完成するのかと言う次の課題が否応なしにも浮かんでくる。
ライブが終わった事を労いたい。
でも、総文祭までは糸を切らすわけにはいかない。
2つの思考が脳内を、まるでメリーゴーランドの様に音を出して無限に回り続けた。
くるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくる狂くる狂くるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくる狂狂狂狂狂狂狂狂…
そんな局長の様子を見ていたタクヤは、そっと局長の肩に手を置いて「今日はもう休もうぜ」と声をかけた。
ステージでは昼休憩中のエキシビジョンとして、主催会社「ハコフグ」スタッフで結成されたバンド「ハコフグオールスターズ」がセックスマシンガンズの「みかんのうた」を演奏している。
「みかんのうた」を尻目に、シータメンバーと演劇部の面々は会場を後にした。
近くにある有名なうどん屋「おかせん」で食事とした後、そのまま解散。
演劇部の面々は、テンション高くそのままカラオケに行くようだ。
局長はそんな気分にはなれないまま、静かに帰路についた。
他のシータメンバーも同じようだ。
背負っているキーボードがいつもよりずっしりと肩に食い込んでいるような気がした。
その日、家に帰った局長は10月に入って初めてゆっくり眠った。
12時間以上寝たはずが、体感時間は1秒にも満たない深い深い睡眠だった。

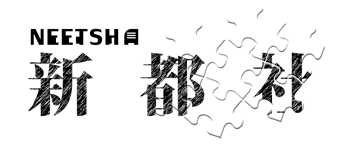

しもたろうに 先生に励ましのお便りを送ろう!!
〒みんなの感想を読む