ひとときの暗がり
作:しもたろうに
[website]
![]()

+
荷物を持つことが嫌い。
いつもは財布だけポケットに突っ込んで手ぶらでやってる局長が、今日は普段使用しているチョッと高い方のYAMAHAキーボードを専用のケースに入れ、肩に担いでやってきた。
超絶地方都市「宇多津」にある「ゆ~ぷらざ」と言う名のホール会場でのライブ当日。
シータのメンバーは、わずか1ヶ月しかない圧倒的に短い時間の中、更に演劇部の超絶活発な活動を同時並行で行いつつ、5曲の新曲を作ると言う無謀としか言えない挑戦をした。
そして、その挑戦は見事に失敗に終わった。
シータの曲作りの方法を今一度説明しよう。
シータでは、作曲者が楽譜とコード進行をメンバーに渡し、それぞれが自分のイメージするパートを個別に制作し、全員が集まったタイミングで「せ~の!」で合わせてみると言う実に歪な方法を採用していた。
その結果、非常にチグハグな構成になる場合が多い。
そもそも自分の作ってきたパートのみしか把握していない上に別パートに耳を傾ける余裕などないため、ドラムが演奏終了したのにまだギターは終了していない、ギターソロ中にキーボードだけが最後のサビを弾き始めると言った本来なら有り得ないような現象も頻発していた。
ライブ当日までに何とか完成したのは「ランナウェイ」「約束の場所で」「始まりの終末~ファーストエンド」の3曲のみ。
「シューティングオブハート」は一度だけ全パートが最後同じタイミングで終わる事ができたが、「街灯の光」に至ってはついに一度もぴったり合う事なく当日を迎えていた。
もう一つ問題がある。
演奏陣がそもそもまともに演奏できていない訳で、ボーカルのムラヤンは「シューティングオブハート」と「街灯の光」を今日に至るまで一度もちゃんと歌っていなかったのだ。
それどころか、楽譜が読めず、楽器が演奏できないムラヤンを放置して編曲作業を行っていたため、ボーカルのムラヤンがメロディーラインを全く把握できてないと言う途轍もない危機的状況に陥っていた。
苦肉の策として、本番までの時間でムラヤンにメロディーラインを教えるため、局長がキーボードを持参したのだ。
もはや無謀を通り越して、勇者としか言えないような英断の元、シータメンバーは「ゆ~ぷらざ」に集合した。
前回のライブとは違い場所も遠いため、今回は全員が親の送迎での会場入りだ。
会場は想像以上に大きかった。
これが1000人キャパのホール。
客席とステージの高低差が15㎝くらいしかない狭く汚いライブハウスとは訳が違う。
だが、シータのメンバーは幸か不幸か、ホールの大きさに気後れはしていないかった。
全員が考えていたのは「そもそも今日のライブが成立するのか」と言う別の意味での緊張感だった。
「おはよう!みんなの控室はこっちだよ。」
会場に入ると、YAMAHA楽器の吉岡が声をかけてきた。
流石にこれだけのホールになると、控室もしっかり整備されている。
各バンドが時間をずらして会場入りするように調整することで、基本的に1バンドに控室が1部屋与えられると言う、へっぽこ高校生ド素人バンドには有り得ない待遇だった。
控室に入ったシータのメンバーは早速各々が自分の楽器を手に、自分のパート練習を始める。
ここにきてもまだ全員で音を合わせるわけでもなく、個人練習を行う。
それが、シータと言うバンドなのだ。
局長はムラヤンに歌詞カードを渡し「今からメロディー弾くから覚えてね。まずは、復習。『ランナウェイ』から。」と言い、小さめの音で演奏を始めた。
今日び、テレビ番組の企画でも絶対やらないような無茶ぶりをムラヤンに対して強いる局長。
「流石に無理ですよ。」とつぶやきながらも、必死で局長の弾くメロディーを覚えようとするムラヤン。
今日までに何度か演奏に合わせて歌っていた「ランナウェイ」「始まりの終末~ファーストエンド」「約束の場所で」は何とかなりそうだったが、残りの2曲はやはり覚えきる事さえ難しい。
繰り返し繰り返し演奏し続ける局長。
必死でその譜割を頭に叩きこもうとするムラヤン。
「リハお願いします~」
少しすると、おそらく今日のイベントを主催する「ハコフグ」のスタッフだろう人が、控室をのぞき込み声をかける。
「廊下出て、真っ直ぐ行ったところからステージ袖に入れますので!」
促されるまま、ステージへ向かうシータのメンバー。
今回、1日通してのイベントでシータは午前中5番目の出演だった。
ステージ袖に上がると、どこかで見たことのある何重に鋲が並んでいるのか分からない恐ろしく長いブレスレットをしたモヒカンの男が、髪を振り乱して謎の言語を叫んでいた。
「マイノリティーボックス?!」
タクヤが声を上げた。
前回の「ティーンズライブフェスタ」で共演したマイノリティーボックス。
何の因果か、今回もシータの前出番のようだ。
相変わらずリハーサルを全力でこなし、ヘロヘロになっているマイノリティーボックスは、舞台袖にいたシータのメンバーに対してすれ違いざまに「お先ッス」とだけ呟いた。
とんでもないデジャブを感じつつ、シータのメンバーはそのままステージへ。
ステージ立った局長は絶句した。
どこまでも続く客席。
何と2階席らしきものまで見える。
それはかつて経験したことのない途轍もない光景だった。
こんなでっかいステージで自分の弾いた音が本当にちゃんと流れるのか?
局長は、少しだけやり方を勉強したシンセサイザーの設定を触りつつ、音色をミックスして作り、試しにボリュームを上げて弾いてみた。
ぴぃいいいいいん。
単音が客席に響く。
前回のライブハウスのようなくぐもった音でない。
聞いたこともないようなクリアな音だ。
そのクリアな音が、客席に不思議な感じで反響し吸い込まれていった。
「ううぅうおおおいいえええええ…」
声にもならないような嗚咽が漏れる。
今になって、尋常ではない緊張が襲ってきた。
自分たちのようなバンドが果たしてこんな大きいホールで演奏して良いのだろうか。
局長は、本来なら数か月前に逡巡すべき事柄について今更考え始めた。
2回目だからか、さすがに前回より早くセッティングは完了した。
ウルオだけは、相変わらず異常にスネアが高くセットされていたドラムセットの調節に苦戦している。
「お待たせ!出来ましたぜぃ!」
ウルオのその声を合図に、ムラヤンが「出来ました」とマイクを通して話す。
「では、触りの部分だけで良いのでお願いします!」
ウルオが「ランナウェイで良い?」と問いかけ、局長とタクヤがそれぞれ頷く。
イントロ部分の16ビートをウルオが叩き始める。
モニター用のアンプから聞こえる自分の演奏した音は、これまでにない位しっかりと聞こえた。
そして、演奏中にどんどんキレイにミキシングされていく。
そのクオリティに局長は感激していた。
「こんなことが起こっていいのか?!!」
自分の作った曲が、まるでCD音源のようにさえ聞こえた。
同時に自分たちの技術の拙さも露呈していたのだが、そんな事に気が付く事が出来るはずもない。
自分の弾いたフレーズがキレイな音になって耳に入ってくることにひたすら感激するのみ。
サビ前まで演奏した段階で「ハイ。ありがとうございました。」と声をかけられた。
今回は、照明効果もあるらしく、その後、照明担当の人からセットリストと、曲のイメージカラーを尋ねられた。
「1曲目ランナウェイはブルー系…」と局長のイメージしていたカラーを説明していく。
「良い感じで盛り上げますので、パフォーマンス頑張ってください!」
さわやかな笑顔でそう言うと、照明担当のお兄さんは戻っていった。
「おい。何かすごいな…」
タクヤが興奮気味に局長に話しかけてくる。
「これは…逆にヤバくないかな…」
局長は、今になって怖気づいていた。
何が逆なのかは誰にも分からない。
新人バンド以外のリハーサルは前日に行われていたようで、当日のリハーサルはシータで最後だった。
控室に戻り、引き続きムラヤンにメロディーラインを叩きこんでいると、9時30分になり演奏が聞こえ始めた。
イベントが始まったのだろう。
午前中出演するバンドの持ち時間は1バンド30分。
シータの出番は11時30分からだ。
タクヤ、ウルオ、啓司はそれぞれ必死で、自分のパートの練習をしている。
局長はムラヤンにメロディーラインを詰め込んでいる。
控室のドアが少しだけ開いて守山が中を覗き込んだが、全員が集中していたため、そのことに気が付いた者は誰もいなかった。
いつもは財布だけポケットに突っ込んで手ぶらでやってる局長が、今日は普段使用しているチョッと高い方のYAMAHAキーボードを専用のケースに入れ、肩に担いでやってきた。
超絶地方都市「宇多津」にある「ゆ~ぷらざ」と言う名のホール会場でのライブ当日。
シータのメンバーは、わずか1ヶ月しかない圧倒的に短い時間の中、更に演劇部の超絶活発な活動を同時並行で行いつつ、5曲の新曲を作ると言う無謀としか言えない挑戦をした。
そして、その挑戦は見事に失敗に終わった。
シータの曲作りの方法を今一度説明しよう。
シータでは、作曲者が楽譜とコード進行をメンバーに渡し、それぞれが自分のイメージするパートを個別に制作し、全員が集まったタイミングで「せ~の!」で合わせてみると言う実に歪な方法を採用していた。
その結果、非常にチグハグな構成になる場合が多い。
そもそも自分の作ってきたパートのみしか把握していない上に別パートに耳を傾ける余裕などないため、ドラムが演奏終了したのにまだギターは終了していない、ギターソロ中にキーボードだけが最後のサビを弾き始めると言った本来なら有り得ないような現象も頻発していた。
ライブ当日までに何とか完成したのは「ランナウェイ」「約束の場所で」「始まりの終末~ファーストエンド」の3曲のみ。
「シューティングオブハート」は一度だけ全パートが最後同じタイミングで終わる事ができたが、「街灯の光」に至ってはついに一度もぴったり合う事なく当日を迎えていた。
もう一つ問題がある。
演奏陣がそもそもまともに演奏できていない訳で、ボーカルのムラヤンは「シューティングオブハート」と「街灯の光」を今日に至るまで一度もちゃんと歌っていなかったのだ。
それどころか、楽譜が読めず、楽器が演奏できないムラヤンを放置して編曲作業を行っていたため、ボーカルのムラヤンがメロディーラインを全く把握できてないと言う途轍もない危機的状況に陥っていた。
苦肉の策として、本番までの時間でムラヤンにメロディーラインを教えるため、局長がキーボードを持参したのだ。
もはや無謀を通り越して、勇者としか言えないような英断の元、シータメンバーは「ゆ~ぷらざ」に集合した。
前回のライブとは違い場所も遠いため、今回は全員が親の送迎での会場入りだ。
会場は想像以上に大きかった。
これが1000人キャパのホール。
客席とステージの高低差が15㎝くらいしかない狭く汚いライブハウスとは訳が違う。
だが、シータのメンバーは幸か不幸か、ホールの大きさに気後れはしていないかった。
全員が考えていたのは「そもそも今日のライブが成立するのか」と言う別の意味での緊張感だった。
「おはよう!みんなの控室はこっちだよ。」
会場に入ると、YAMAHA楽器の吉岡が声をかけてきた。
流石にこれだけのホールになると、控室もしっかり整備されている。
各バンドが時間をずらして会場入りするように調整することで、基本的に1バンドに控室が1部屋与えられると言う、へっぽこ高校生ド素人バンドには有り得ない待遇だった。
控室に入ったシータのメンバーは早速各々が自分の楽器を手に、自分のパート練習を始める。
ここにきてもまだ全員で音を合わせるわけでもなく、個人練習を行う。
それが、シータと言うバンドなのだ。
局長はムラヤンに歌詞カードを渡し「今からメロディー弾くから覚えてね。まずは、復習。『ランナウェイ』から。」と言い、小さめの音で演奏を始めた。
今日び、テレビ番組の企画でも絶対やらないような無茶ぶりをムラヤンに対して強いる局長。
「流石に無理ですよ。」とつぶやきながらも、必死で局長の弾くメロディーを覚えようとするムラヤン。
今日までに何度か演奏に合わせて歌っていた「ランナウェイ」「始まりの終末~ファーストエンド」「約束の場所で」は何とかなりそうだったが、残りの2曲はやはり覚えきる事さえ難しい。
繰り返し繰り返し演奏し続ける局長。
必死でその譜割を頭に叩きこもうとするムラヤン。
「リハお願いします~」
少しすると、おそらく今日のイベントを主催する「ハコフグ」のスタッフだろう人が、控室をのぞき込み声をかける。
「廊下出て、真っ直ぐ行ったところからステージ袖に入れますので!」
促されるまま、ステージへ向かうシータのメンバー。
今回、1日通してのイベントでシータは午前中5番目の出演だった。
ステージ袖に上がると、どこかで見たことのある何重に鋲が並んでいるのか分からない恐ろしく長いブレスレットをしたモヒカンの男が、髪を振り乱して謎の言語を叫んでいた。
「マイノリティーボックス?!」
タクヤが声を上げた。
前回の「ティーンズライブフェスタ」で共演したマイノリティーボックス。
何の因果か、今回もシータの前出番のようだ。
相変わらずリハーサルを全力でこなし、ヘロヘロになっているマイノリティーボックスは、舞台袖にいたシータのメンバーに対してすれ違いざまに「お先ッス」とだけ呟いた。
とんでもないデジャブを感じつつ、シータのメンバーはそのままステージへ。
ステージ立った局長は絶句した。
どこまでも続く客席。
何と2階席らしきものまで見える。
それはかつて経験したことのない途轍もない光景だった。
こんなでっかいステージで自分の弾いた音が本当にちゃんと流れるのか?
局長は、少しだけやり方を勉強したシンセサイザーの設定を触りつつ、音色をミックスして作り、試しにボリュームを上げて弾いてみた。
ぴぃいいいいいん。
単音が客席に響く。
前回のライブハウスのようなくぐもった音でない。
聞いたこともないようなクリアな音だ。
そのクリアな音が、客席に不思議な感じで反響し吸い込まれていった。
「ううぅうおおおいいえええええ…」
声にもならないような嗚咽が漏れる。
今になって、尋常ではない緊張が襲ってきた。
自分たちのようなバンドが果たしてこんな大きいホールで演奏して良いのだろうか。
局長は、本来なら数か月前に逡巡すべき事柄について今更考え始めた。
2回目だからか、さすがに前回より早くセッティングは完了した。
ウルオだけは、相変わらず異常にスネアが高くセットされていたドラムセットの調節に苦戦している。
「お待たせ!出来ましたぜぃ!」
ウルオのその声を合図に、ムラヤンが「出来ました」とマイクを通して話す。
「では、触りの部分だけで良いのでお願いします!」
ウルオが「ランナウェイで良い?」と問いかけ、局長とタクヤがそれぞれ頷く。
イントロ部分の16ビートをウルオが叩き始める。
モニター用のアンプから聞こえる自分の演奏した音は、これまでにない位しっかりと聞こえた。
そして、演奏中にどんどんキレイにミキシングされていく。
そのクオリティに局長は感激していた。
「こんなことが起こっていいのか?!!」
自分の作った曲が、まるでCD音源のようにさえ聞こえた。
同時に自分たちの技術の拙さも露呈していたのだが、そんな事に気が付く事が出来るはずもない。
自分の弾いたフレーズがキレイな音になって耳に入ってくることにひたすら感激するのみ。
サビ前まで演奏した段階で「ハイ。ありがとうございました。」と声をかけられた。
今回は、照明効果もあるらしく、その後、照明担当の人からセットリストと、曲のイメージカラーを尋ねられた。
「1曲目ランナウェイはブルー系…」と局長のイメージしていたカラーを説明していく。
「良い感じで盛り上げますので、パフォーマンス頑張ってください!」
さわやかな笑顔でそう言うと、照明担当のお兄さんは戻っていった。
「おい。何かすごいな…」
タクヤが興奮気味に局長に話しかけてくる。
「これは…逆にヤバくないかな…」
局長は、今になって怖気づいていた。
何が逆なのかは誰にも分からない。
新人バンド以外のリハーサルは前日に行われていたようで、当日のリハーサルはシータで最後だった。
控室に戻り、引き続きムラヤンにメロディーラインを叩きこんでいると、9時30分になり演奏が聞こえ始めた。
イベントが始まったのだろう。
午前中出演するバンドの持ち時間は1バンド30分。
シータの出番は11時30分からだ。
タクヤ、ウルオ、啓司はそれぞれ必死で、自分のパートの練習をしている。
局長はムラヤンにメロディーラインを詰め込んでいる。
控室のドアが少しだけ開いて守山が中を覗き込んだが、全員が集中していたため、そのことに気が付いた者は誰もいなかった。

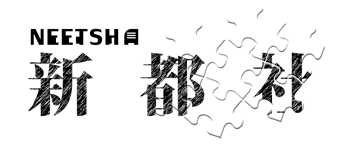

しもたろうに 先生に励ましのお便りを送ろう!!
〒みんなの感想を読む