ひとときの暗がり
作:しもたろうに
[website]
![]()

+
部活の時間、局長の書いた演劇用の台本「付喪神」は各部員によって回し読みされた結果、無事採用されることになった。
ただし、どうしても演劇の経験が少ない局長の書いたものだった事もあり、守山による加筆修正が条件とされた。
せっかくやる気を出した局長の書いてきたものを否定しないようにと言う、今でいう忖度に似た空気感が演劇部内に流れていたことは否めない。
それであっても、どうしてもダメなものはダメ。
その意味で(あくまでも及第点だったとしても)「付喪神」は採用に足るだけのクオリティーではあった。
週明けまでに、守山によって加筆修正が行われ、そして、月曜日から総文祭に向けた「付喪神」の練習が始まることになった。
局長は自分の作った作品に人の手が入る事に対して嫌悪感を持ってはいたが、それについて強く否定できる立場でもない事は分かっている。
しぶしぶではあるが、その条件を受け入れた。
兎にも角にも局長の作り出した物語が初めて、公に発表されることになったのだ。
その事を考えると、どうしたってニヤニヤが止まらない。
ニヤニヤと気持ち悪い笑みを浮かべながらの下校となった。
その日の夜。
台本執筆が一区切りした局長は、先日守山からもらったMDをコンポにセットしていた。
自分の作品を認めてくれた守山の作った曲を自分が没にすることなど出来るはずがない。
採用するしかない。
しかし、それでもどうしても自分として許せないものだったらどうしよう。
タクヤが好きなaikoのような曲調だったらどうしよう。
そんな不安を抱えながら、再生ボタンを押した。
デモテープは、ピアノの単音でメロディーラインだけが淡々と流れるだけのものだった。
努めて冷静にそのメロディーラインを聴く。
その単調なメロディーラインだけでどう判断するべきなのか。
メロディーはマイナー調で重暗いイメージだった。
かなり局長が好きなメロディーだったことは間違いない。
まずはホッと一安心。
次に、そのメロディーラインにどのような編曲を施すべきか、どのような前奏や間奏をつけるべきか考える。
不意に、先日書き留めた4編の歌詞を持ち出した。
メロディーラインの譜割とその歌詞を合わせてみる。
「おおお…まぢか…」
局長が先日書いた歌詞のうち「始まりの終末~ファーストエンド」と「街灯の光」の2曲が、守山の作ったメロディーラインにピッタリと当てはまった。
おそらく守山がサビを想定した箇所と局長がサビになるであろうと想定して書いた個所がピタリと重なるのだ。
「こんなことがあるのか…」
採用するかどうかと言う問題ではなかった。
この曲の為に書き下ろしたとしか思えない2編の歌詞。
局長は早速そのまま守山の弾いているメロディーラインを楽譜に起こし、コードを付けていった。
昨夜、「付喪神」を読み返し続けて徹夜したことなど忘れていたかのように、局長は一心不乱に守山の作った2曲を採譜していった。
この段階に来ても自身では新しい曲が作り切れなかった局長は、思い立ったかのように以前制作していた「楽しい日々は過ぎ去りて」の譜割を修正して、「ランナウェイ」の歌詞を当て込んでみた。
想像以上にすんなりと当てはまり、新しい曲として「楽しい日々は過ぎ去りて」は生まれ変わってしまった。
「こんなことが出来たのか!」
そのままの勢いで、残る最後の1編「約束の場所で」を「森を抜けた先にある闇」の曲を修正して当てはめてみると、何とこちらもピッタリ。
想定外にも、局長は目標にしていた4曲の新曲を作り上げることが出来たのだ。
その4曲を何度も何度も部屋に置いてあった安物のYAMAHA製のキーボードで繰り返し弾き続ける。
「めっちゃ良い4曲が出来てしまった…やっぱりオレは紛う事ない天才だ…」
局長は信じて疑わないその思い込みを、更に強烈な確認に変えつつ呟いた。
2曲は守山の作曲だったが、そんな事は些細な問題だ。
あとは、タクヤが作ると言っていた1曲で何とかなるだろう。
気が付くと今日も夜が明けていた。
「さて、睡眠をとりに学校に行くか。」
つぶやきながら制服に着替えていた。
夜には魔物が存在している。
魔物は普段は逆立ちしても出てこないような不思議な文章やメロディーを突然脳裏に落として去っていく。
落ちてきた言葉、文章やメロディーは、夜の魔物によってどうしようもなく素晴らしい作品の様に強烈に思い込まされてしまう。
そして、その幻想は朝日と共に流れ落ち、冷静になるとなかなかどうして恥ずかしい何とも稚拙な文章がそこに存在しているものだ。
だが、信じると言う行為がひとつ入り込むことにより、夜の魔物が持ち出した幻想が流れ落ちなくなる場合がある。
そうやって葬られなかった作品群こそ、のちの世に「黒歴史」と呼ばれるようになるのだろう。
週末、犬小屋にシータのメンバーが緊急招集された。
「この前の文化祭はどうだった?僕のいないライブはダメだっただろう?」
眼鏡をクイッと上げながら啓司がニヤニヤと聞いてきた。
「タクヤがまだ来てないのか…」
予定調和の様に啓司の話を無視して局長が話す。
遅刻しかした事がないと言っても過言ではない局長とは違い、基本的に約束の時間などに遅れることがほぼないタクヤが約束の時間を過ぎても現れない。
「珍しい事もあるね」
ウルオも不思議に周りを見渡す。
「うむ。」
ムラヤンが頷いた。
しばらくして、バタバタと足音がして「悪い悪い…」とつぶやきながらタクヤがやってきた。
目の下には見たこともないほど激しいどす黒いクマが出来ている。
「どうしたんだ?珍しく遅かったな。」
自分の事を棚に上げて、局長が話しかける。
「曲をさ…オレも作るって言っただろ?今日、どうしてもみんなに聞いてほしくて仕上げてきたんだよ。楽譜が書けなくて家のピアノで1音ずつ音探していて、昨日の夜から寝てないんだ。」
タクヤはそういうと少し目をこする仕草をした。
「採譜とコードはやってやるのに…」
「いや、お前もずっと徹夜しているって言っていたから悪いなと思って…あと、初めての自分の曲だから全部自分でやりたかったのもあるけど。」
ニヤッとしたタクヤは、背負っていたリュックから楽譜と歌詞を取り出した。
「と言う事は相当いい曲が出来たんだろうな」
「どうだろう…でも、オレは良いと思う。」
「新曲?またライブがあると言うのかい?」
事情を知らない啓司が口をはさんだ。
「え?歌詞も書いたのか?」
「ほほう。いつも通りの無視と言うわけだね。」
そう言うと啓司はくるりと背中を向けて、アンプにつないでいないギターでシャカシャカと何かの曲を弾き始めた。
「書いたよ。曲名は『シューティングオブハート』だ。チョッと、まずは聞いてみてくれよ。」
「しゅ…シューティングオブハートだとぉ…」
そのタイトルを聞いた瞬間、局長の脳裏にはピナツボ火山並みに言いたい事が溢れ出した。
だが、今、ここでその思いをそのまま口にしてしまえば、100%喧嘩になる事は分かっている。
ただでさえタクヤは寝ていないのだ。
普段より早く、そして激しい喧嘩になる事は想像に難くない。
別に喧嘩をしても良いと言えば良いのだが、この後に自分の曲と守山の曲の話もしなければいけない。
自分が必死で作ったものを否定されることの悲しさも経験してきたつもりだ。
局長は、止めどなく溢れてくる言いたい事をグッと飲み込む選択をした。
少しだけ大人になれた瞬間かも知れない。
「ほほう…ハートを狙い撃ちってことですね。」
ウルオも何か言いたそうに、それだけ呟いた。
夜の魔物は、局長だけではなくタクヤのところにも現れたのだろう。
「まぁ、まずは聞いてくれよ。」
おもむろに局長のフォークギターを手にしたタクヤは、自身初のオリジナル楽曲「シューティングオブハート」を声高に歌い出した。
良く言えばGLAYのオマージュ。悪く言えばGLAYのパクリだった。
曲自体は悪くない。
むしろ潔くパクった分、局長の作る曲よりもしっかりとしたメロディーラインがあり、聴きやすい。
これまでのシータの楽曲とは明らかに一線を画す曲だった。
歌詞はよく聞き取れない。
唯一しっかりと聞き取れた歌詞はサビの「君のピュアなハートをバンディット」と言う部分だった。
衝撃を受けた。
アホでも書ける安易で薄っぺらな恋愛ネタ、取り敢えず英語を織り交ぜた意味のない言葉の羅列。
それは、局長が普段から唾棄すべきものとして見下していた対象そのものだった。
タクヤが寝ずに書いた歌詞の中にその対象が存在していたのだ。
一体タクヤはどんな気持ちで「君のピュアなハートをバンディット」と書いたのだろうか。
本気だったのか。
ギャグだったのか。
もし、心の底から本気で書いたのであれば…
その可能性が残っている以上は優しい気持ちで否定はしないであげたいと思う…
でも、ライブで演奏するなら、せめてもう少しマシな形に歌詞だけでも書き直したい。
局長は苦々しい思いを顔に出さないようにしつつ、朗々と歌われるタクヤの曲を聞いていた。
多少なりとも顔には出ていただろう。
タクヤが寝ずに必死で作ってきた「シューティングオブハート」。
寝ないで作ったからこうなってしまったのか「シューティングオブハート」。
良い意味でも、悪い意味でも確実に局長のピュアなハートをバンディットしていた。
ひとしきり歌い終わった後、少し顔を赤らめながら「どうだ?」と言う顔でタクヤは局長たちの方を見た。
「素晴らしい!良い曲だね!」
音楽に対するこだわりを1ミクロンも持ち合わせていない啓司は称賛した。
「良いと思うよ。」
「そうだね。」
ウルオとムラヤンは当たり障りない評価を口にする。
「お前は?」
タクヤが局長にも評価を促す。
「……………」
「……………………・」
「…いいんじゃね。この曲もライブやろう。」
作品に対して妥協しない事を信条にしていた局長は初めて心の底から嘘をついた。
こうして次のライブでやる曲は「楽しい日々は過ぎ去りて~ランナウェイ」「始まりの終末~ファーストエンド」「約束の場所で」「街灯の光」「シューティングオブハート」「the super finish」の全6曲に決まったのだった。
夜の魔物はその情景を不遜な笑みを浮かべて眺めていたに違いないだろう。
ただし、どうしても演劇の経験が少ない局長の書いたものだった事もあり、守山による加筆修正が条件とされた。
せっかくやる気を出した局長の書いてきたものを否定しないようにと言う、今でいう忖度に似た空気感が演劇部内に流れていたことは否めない。
それであっても、どうしてもダメなものはダメ。
その意味で(あくまでも及第点だったとしても)「付喪神」は採用に足るだけのクオリティーではあった。
週明けまでに、守山によって加筆修正が行われ、そして、月曜日から総文祭に向けた「付喪神」の練習が始まることになった。
局長は自分の作った作品に人の手が入る事に対して嫌悪感を持ってはいたが、それについて強く否定できる立場でもない事は分かっている。
しぶしぶではあるが、その条件を受け入れた。
兎にも角にも局長の作り出した物語が初めて、公に発表されることになったのだ。
その事を考えると、どうしたってニヤニヤが止まらない。
ニヤニヤと気持ち悪い笑みを浮かべながらの下校となった。
その日の夜。
台本執筆が一区切りした局長は、先日守山からもらったMDをコンポにセットしていた。
自分の作品を認めてくれた守山の作った曲を自分が没にすることなど出来るはずがない。
採用するしかない。
しかし、それでもどうしても自分として許せないものだったらどうしよう。
タクヤが好きなaikoのような曲調だったらどうしよう。
そんな不安を抱えながら、再生ボタンを押した。
デモテープは、ピアノの単音でメロディーラインだけが淡々と流れるだけのものだった。
努めて冷静にそのメロディーラインを聴く。
その単調なメロディーラインだけでどう判断するべきなのか。
メロディーはマイナー調で重暗いイメージだった。
かなり局長が好きなメロディーだったことは間違いない。
まずはホッと一安心。
次に、そのメロディーラインにどのような編曲を施すべきか、どのような前奏や間奏をつけるべきか考える。
不意に、先日書き留めた4編の歌詞を持ち出した。
メロディーラインの譜割とその歌詞を合わせてみる。
「おおお…まぢか…」
局長が先日書いた歌詞のうち「始まりの終末~ファーストエンド」と「街灯の光」の2曲が、守山の作ったメロディーラインにピッタリと当てはまった。
おそらく守山がサビを想定した箇所と局長がサビになるであろうと想定して書いた個所がピタリと重なるのだ。
「こんなことがあるのか…」
採用するかどうかと言う問題ではなかった。
この曲の為に書き下ろしたとしか思えない2編の歌詞。
局長は早速そのまま守山の弾いているメロディーラインを楽譜に起こし、コードを付けていった。
昨夜、「付喪神」を読み返し続けて徹夜したことなど忘れていたかのように、局長は一心不乱に守山の作った2曲を採譜していった。
この段階に来ても自身では新しい曲が作り切れなかった局長は、思い立ったかのように以前制作していた「楽しい日々は過ぎ去りて」の譜割を修正して、「ランナウェイ」の歌詞を当て込んでみた。
想像以上にすんなりと当てはまり、新しい曲として「楽しい日々は過ぎ去りて」は生まれ変わってしまった。
「こんなことが出来たのか!」
そのままの勢いで、残る最後の1編「約束の場所で」を「森を抜けた先にある闇」の曲を修正して当てはめてみると、何とこちらもピッタリ。
想定外にも、局長は目標にしていた4曲の新曲を作り上げることが出来たのだ。
その4曲を何度も何度も部屋に置いてあった安物のYAMAHA製のキーボードで繰り返し弾き続ける。
「めっちゃ良い4曲が出来てしまった…やっぱりオレは紛う事ない天才だ…」
局長は信じて疑わないその思い込みを、更に強烈な確認に変えつつ呟いた。
2曲は守山の作曲だったが、そんな事は些細な問題だ。
あとは、タクヤが作ると言っていた1曲で何とかなるだろう。
気が付くと今日も夜が明けていた。
「さて、睡眠をとりに学校に行くか。」
つぶやきながら制服に着替えていた。
夜には魔物が存在している。
魔物は普段は逆立ちしても出てこないような不思議な文章やメロディーを突然脳裏に落として去っていく。
落ちてきた言葉、文章やメロディーは、夜の魔物によってどうしようもなく素晴らしい作品の様に強烈に思い込まされてしまう。
そして、その幻想は朝日と共に流れ落ち、冷静になるとなかなかどうして恥ずかしい何とも稚拙な文章がそこに存在しているものだ。
だが、信じると言う行為がひとつ入り込むことにより、夜の魔物が持ち出した幻想が流れ落ちなくなる場合がある。
そうやって葬られなかった作品群こそ、のちの世に「黒歴史」と呼ばれるようになるのだろう。
週末、犬小屋にシータのメンバーが緊急招集された。
「この前の文化祭はどうだった?僕のいないライブはダメだっただろう?」
眼鏡をクイッと上げながら啓司がニヤニヤと聞いてきた。
「タクヤがまだ来てないのか…」
予定調和の様に啓司の話を無視して局長が話す。
遅刻しかした事がないと言っても過言ではない局長とは違い、基本的に約束の時間などに遅れることがほぼないタクヤが約束の時間を過ぎても現れない。
「珍しい事もあるね」
ウルオも不思議に周りを見渡す。
「うむ。」
ムラヤンが頷いた。
しばらくして、バタバタと足音がして「悪い悪い…」とつぶやきながらタクヤがやってきた。
目の下には見たこともないほど激しいどす黒いクマが出来ている。
「どうしたんだ?珍しく遅かったな。」
自分の事を棚に上げて、局長が話しかける。
「曲をさ…オレも作るって言っただろ?今日、どうしてもみんなに聞いてほしくて仕上げてきたんだよ。楽譜が書けなくて家のピアノで1音ずつ音探していて、昨日の夜から寝てないんだ。」
タクヤはそういうと少し目をこする仕草をした。
「採譜とコードはやってやるのに…」
「いや、お前もずっと徹夜しているって言っていたから悪いなと思って…あと、初めての自分の曲だから全部自分でやりたかったのもあるけど。」
ニヤッとしたタクヤは、背負っていたリュックから楽譜と歌詞を取り出した。
「と言う事は相当いい曲が出来たんだろうな」
「どうだろう…でも、オレは良いと思う。」
「新曲?またライブがあると言うのかい?」
事情を知らない啓司が口をはさんだ。
「え?歌詞も書いたのか?」
「ほほう。いつも通りの無視と言うわけだね。」
そう言うと啓司はくるりと背中を向けて、アンプにつないでいないギターでシャカシャカと何かの曲を弾き始めた。
「書いたよ。曲名は『シューティングオブハート』だ。チョッと、まずは聞いてみてくれよ。」
「しゅ…シューティングオブハートだとぉ…」
そのタイトルを聞いた瞬間、局長の脳裏にはピナツボ火山並みに言いたい事が溢れ出した。
だが、今、ここでその思いをそのまま口にしてしまえば、100%喧嘩になる事は分かっている。
ただでさえタクヤは寝ていないのだ。
普段より早く、そして激しい喧嘩になる事は想像に難くない。
別に喧嘩をしても良いと言えば良いのだが、この後に自分の曲と守山の曲の話もしなければいけない。
自分が必死で作ったものを否定されることの悲しさも経験してきたつもりだ。
局長は、止めどなく溢れてくる言いたい事をグッと飲み込む選択をした。
少しだけ大人になれた瞬間かも知れない。
「ほほう…ハートを狙い撃ちってことですね。」
ウルオも何か言いたそうに、それだけ呟いた。
夜の魔物は、局長だけではなくタクヤのところにも現れたのだろう。
「まぁ、まずは聞いてくれよ。」
おもむろに局長のフォークギターを手にしたタクヤは、自身初のオリジナル楽曲「シューティングオブハート」を声高に歌い出した。
良く言えばGLAYのオマージュ。悪く言えばGLAYのパクリだった。
曲自体は悪くない。
むしろ潔くパクった分、局長の作る曲よりもしっかりとしたメロディーラインがあり、聴きやすい。
これまでのシータの楽曲とは明らかに一線を画す曲だった。
歌詞はよく聞き取れない。
唯一しっかりと聞き取れた歌詞はサビの「君のピュアなハートをバンディット」と言う部分だった。
衝撃を受けた。
アホでも書ける安易で薄っぺらな恋愛ネタ、取り敢えず英語を織り交ぜた意味のない言葉の羅列。
それは、局長が普段から唾棄すべきものとして見下していた対象そのものだった。
タクヤが寝ずに書いた歌詞の中にその対象が存在していたのだ。
一体タクヤはどんな気持ちで「君のピュアなハートをバンディット」と書いたのだろうか。
本気だったのか。
ギャグだったのか。
もし、心の底から本気で書いたのであれば…
その可能性が残っている以上は優しい気持ちで否定はしないであげたいと思う…
でも、ライブで演奏するなら、せめてもう少しマシな形に歌詞だけでも書き直したい。
局長は苦々しい思いを顔に出さないようにしつつ、朗々と歌われるタクヤの曲を聞いていた。
多少なりとも顔には出ていただろう。
タクヤが寝ずに必死で作ってきた「シューティングオブハート」。
寝ないで作ったからこうなってしまったのか「シューティングオブハート」。
良い意味でも、悪い意味でも確実に局長のピュアなハートをバンディットしていた。
ひとしきり歌い終わった後、少し顔を赤らめながら「どうだ?」と言う顔でタクヤは局長たちの方を見た。
「素晴らしい!良い曲だね!」
音楽に対するこだわりを1ミクロンも持ち合わせていない啓司は称賛した。
「良いと思うよ。」
「そうだね。」
ウルオとムラヤンは当たり障りない評価を口にする。
「お前は?」
タクヤが局長にも評価を促す。
「……………」
「……………………・」
「…いいんじゃね。この曲もライブやろう。」
作品に対して妥協しない事を信条にしていた局長は初めて心の底から嘘をついた。
こうして次のライブでやる曲は「楽しい日々は過ぎ去りて~ランナウェイ」「始まりの終末~ファーストエンド」「約束の場所で」「街灯の光」「シューティングオブハート」「the super finish」の全6曲に決まったのだった。
夜の魔物はその情景を不遜な笑みを浮かべて眺めていたに違いないだろう。

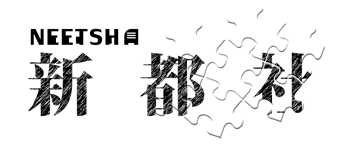

しもたろうに 先生に励ましのお便りを送ろう!!
〒みんなの感想を読む