ひとときの暗がり
作:しもたろうに
[website]
![]()

+
「書けた…」
局長はそうつぶやくと、かれこれ5年以上愛用し続けているpilot製0.3mmの油性ボールペン「HI-TEC-C」をコロンと机の上に転がした。
遂に、付喪神を最後まで書き切ったのだ。
書き始めてから実に1か月と少し。
前作の「マリオネット」を一晩で書き上げる程度には速筆の局長にとって、1つの話の執筆に1ヶ月以上かけたのは人生で初めてのことだった。
書き直した物語をもう一度初めから読み直してみる。
「…面白い…」
もう一度最初から読み直してみる。
「このセリフの掛け合い最高だ…」
もう一度最初から読み直してみる。
「このぬいぐるみを捨てられた女の子のシーン素晴らしい…」
何度読み直しても素晴らしい。
そもそも、自分が面白い思うものを、時間をかけて書いている以上、自分にとって面白くないと言う結論が出るはずはない。
その上でも、過去に書いたどの作品よりも面白いと局長は感じていた。
正直、このネタを演劇の台本にしてしまうことが勿体ないと思う。
そのくらい文句のない出来だった。
明日、この物語を部活にもっていこう。
そして、感想を貰おう。
そう考えると、不安になり、もう一度読み直す。
そして自画自賛。
局長は、広くはない自分の部屋の中をくるくると周回しながら、同じ思考と同じ行為を何度も何度も繰り返した。
一晩中繰り返した。
気が付くと、窓の外は薄明るくなっていた。
「やばい…寝ていない…けど、まぁ、授業中に寝ればいいか。」
今更になり襲ってきた眠気と闘いながら、局長はノロノロと制服に着替え、学校へと向かった。
それからの時間は記憶がほぼない。
授業開始と終了の挨拶以外全て寝ていたのだろう。
昼休みになり、いつものようにタクヤが迎えに来た。
「行こうぜ…って、おい…大丈夫か?」
タクヤが心配するレベルで、土のような顔色をしている。
「あぁ、昨日チョッと寝てなくて…でも、完成したよ。」
「おお!新曲か?オレは、まだできてないんだけど…」
「いや、そっちじゃなくて台本の方。」
「あぁ…そっちもやっていたのか。良く両方同時に進められるよな。」
「まぁ、控えめに言っても天才だからな。」
「そりゃよかったな…」
そんな事を話しながら、いつも昼食をとっているトイレの裏までやってきた。
「おっす!」
そこにはすでに守山が座って待っていた。
「時々来てもいい?」と言っていた守山だったが、タクヤの予想通り次の日から、毎日ここに弁当持参でやってくるようになっていた。
「部長!こいつ見てくださいよ。顔色悪いでしょ。」
唐突にタクヤが守山に話し始める。
局長は何だか嫌な予感がしていた。
「そう言えば…高井君顔色悪いね…大丈夫?」
「こいつね。昨日の夜、前から書いていた新作台本を完成させていて、寝不足なんですよ。」
局長の予感は的中した。
ここまでデリカシーのない人間がこの世に存在していいのか。
こいつはうんこ人間だ。
紛う事なきうんこ人間だ。
そもそも、こいつほど無思慮に生きている人間は、出来上がった作品を人にどう評価されようとも何の感慨も浮かばないに決まっている。
だからいつまで経っても成長しないんだ。
だからaikoとか聴いているんだ。
心の中でひとしきりタクヤのことを罵倒した局長は、この後の流れが必ず「今すぐ読ませてよ!」となるであろうことに絶望した。
少なくとも部活の時間まで引き延ばせるはずの審判が、無理やり今この瞬間に執行される。
それを絶望と言わずに何というべきであろうか。
「え!ホント!すごい!すごいよ!高井君!それ見せてよ!今、持っている?」
守山は予定調和を乱すことなく、流れるように話す。
「いや…弁当しか持ってなくて…教室にあるんです。」
「持ってきてよ。今、ゆっくり読みたいよ。」
局長のやんわりとした拒絶など瞬時に吹き飛ばして守山は言ってのけた。
「行って来いよ。どうせ、部活の時間に見せるつもりだったんだろう?」
タクヤの容赦ない援護も飛んでくる。
局長は諦めた様子で、少しだけ天を仰ぎ「ちょっと待ってくださいよ。」そう言って、踵を返した。
デリカシーのかけらもない2人に何を言っても無駄だ。
こっちの気持ちなど何も考慮することが出来ない短絡的で本能的な言動の数々。
いっそのこと、このままバックレてやろうか。
ついでに部活もさぼってやろうか。
局長はささくれながら、しかし何故か早足で教室へ戻っていった。
本心では、早くこの圧倒的自信作を読んでもらいたい。
だた、圧倒的自信作であるために、否定的評価をされることに対してかつてない恐怖も感じている。
二律背反した理性が局長の中でせめぎあっていた。
最終的には小走りになり、少し息を切らせながら局長は台本を手に戻ってきた。
「ふぅ…これです。」
いつも通りの小汚いしわくちゃになったルーズリーフ約30枚を守山に手渡した。
「今から読むから、高井君たちは気にしないで、ご飯食べてて。」
そう言うと、守山はルーズリーフに目を落とした。
「今回の話はどうなんだ?」
弁当を頬張りながら、タクヤが話しかけてくる。
「…」
「……」
「…………」
「おい、何か言えよ。」
「部長が読んでいるからまた後で。」
「何だよ…それ?」
守山の評価が気になりすぎてタクヤの言動など歯牙にもかけない。
数分だったか、十数分だったか、数十分だったか。
局長にとっては永遠にも等しい沈黙の時間が流れる。
最後のルーズリーフを読み終えた守山が局長の方を向いた。
「読んだよ。」
「……」
局長は自分の心音が大きすぎて聞こえなくなる位には緊張していた。
心臓はもうどこかに行ってしまったのかもしれない。
「部長?面白いですか?」
何も話さない局長に変わって、タクヤが投げかける。
「うん。そうだなぁ…」
少し間をおいてから守山は局長の目を見て話し始めた。
「少し気になるところはあるけど、全体的には良いと思うよ。テーマも展開も面白いし。今日の部活でくーちゃん達に読んでもらってからにはなるけど、次の高文祭は、この話でやっていいんじゃないかな?少なくともあたしはこの話をやりたい。」
守山の返答を聴きながら、局長は目の前が真っ白になっていく感覚に襲われていた。
じわじわじわじわじわじわじわじわじわ…
目の前の光景が、白色のペンキで少しずつ塗りつぶされていくような。
意識はしっかりとあるのに、ゆっくりと意識が遠のいていくような。
これまで経験した事がないような実に不思議な感覚だ。
指先がびりびりと痺れている事だけは分かる。
自分が例えこれから50年、100年生きたとしても、人生最良の日はいつですかと聞かれたら、迷いなく今日だと答えるだろう。
その位の感激が局長を襲った。
指先が震えている事を悟られないように、静かに、少しずつ細かい呼吸を何度も行う。
「そうですか。今回は使って貰えそうで良かったっす。」
限界まで冷静を装ってそう話したが、はち切れんばかりの喜びは溢れに溢れ、粗い鼻息と気持ち悪いニヤケ顔になっていた。
「おおお!すげぇ!やったな。オレにも読ませてくれよ。」
そう言うと、タクヤは守山から渡されたルーズリーフを読み始める。
「タイトルは、付喪神って言うのか…」
そのタイミングで昼休みの終わりを告げるチャイムが鳴り始めた。
「まぢかぁ~」
タクヤはつぶやきつつ、そのまま台本を読み続けていた。
「あぁ~お昼食べ損ねちゃった。部活の時に食べようかなぁ~」
台本を読んでいた守山は、昼食を取れなかったようだ。
「あれ?高井君も食べなかったの?」
「ええ…なんか、悪いなと思って。」
「別に気にしなくても良いのに…浦沢君は全部食べているよ。」
「まぁ、良いんですよ。こいつは圧倒的無思慮人間なので。」
「何それ。」
少しだけ笑みを浮かべた守山は「じゃあ、部活で!」と言うと、自分の教室へ戻っていった。
「オレ達も戻るか。」
局長はそう言って、タクヤの手からルーズリーフを奪い取った。
「おい!まだ読んでいる途中なんだよ。」
「いいんだよ。別にお前は全部読まなくても。」
そう言うと、局長も自分の教室へ歩き出した。
「しゃあねえな。」
釈然としないながらも、タクヤも後に続く。
その足取りは、まるで羽でもついているのかと言うほどに軽いものだった。
そして、午後の授業も引き続き、当然のように睡眠時間となった。
局長はそうつぶやくと、かれこれ5年以上愛用し続けているpilot製0.3mmの油性ボールペン「HI-TEC-C」をコロンと机の上に転がした。
遂に、付喪神を最後まで書き切ったのだ。
書き始めてから実に1か月と少し。
前作の「マリオネット」を一晩で書き上げる程度には速筆の局長にとって、1つの話の執筆に1ヶ月以上かけたのは人生で初めてのことだった。
書き直した物語をもう一度初めから読み直してみる。
「…面白い…」
もう一度最初から読み直してみる。
「このセリフの掛け合い最高だ…」
もう一度最初から読み直してみる。
「このぬいぐるみを捨てられた女の子のシーン素晴らしい…」
何度読み直しても素晴らしい。
そもそも、自分が面白い思うものを、時間をかけて書いている以上、自分にとって面白くないと言う結論が出るはずはない。
その上でも、過去に書いたどの作品よりも面白いと局長は感じていた。
正直、このネタを演劇の台本にしてしまうことが勿体ないと思う。
そのくらい文句のない出来だった。
明日、この物語を部活にもっていこう。
そして、感想を貰おう。
そう考えると、不安になり、もう一度読み直す。
そして自画自賛。
局長は、広くはない自分の部屋の中をくるくると周回しながら、同じ思考と同じ行為を何度も何度も繰り返した。
一晩中繰り返した。
気が付くと、窓の外は薄明るくなっていた。
「やばい…寝ていない…けど、まぁ、授業中に寝ればいいか。」
今更になり襲ってきた眠気と闘いながら、局長はノロノロと制服に着替え、学校へと向かった。
それからの時間は記憶がほぼない。
授業開始と終了の挨拶以外全て寝ていたのだろう。
昼休みになり、いつものようにタクヤが迎えに来た。
「行こうぜ…って、おい…大丈夫か?」
タクヤが心配するレベルで、土のような顔色をしている。
「あぁ、昨日チョッと寝てなくて…でも、完成したよ。」
「おお!新曲か?オレは、まだできてないんだけど…」
「いや、そっちじゃなくて台本の方。」
「あぁ…そっちもやっていたのか。良く両方同時に進められるよな。」
「まぁ、控えめに言っても天才だからな。」
「そりゃよかったな…」
そんな事を話しながら、いつも昼食をとっているトイレの裏までやってきた。
「おっす!」
そこにはすでに守山が座って待っていた。
「時々来てもいい?」と言っていた守山だったが、タクヤの予想通り次の日から、毎日ここに弁当持参でやってくるようになっていた。
「部長!こいつ見てくださいよ。顔色悪いでしょ。」
唐突にタクヤが守山に話し始める。
局長は何だか嫌な予感がしていた。
「そう言えば…高井君顔色悪いね…大丈夫?」
「こいつね。昨日の夜、前から書いていた新作台本を完成させていて、寝不足なんですよ。」
局長の予感は的中した。
ここまでデリカシーのない人間がこの世に存在していいのか。
こいつはうんこ人間だ。
紛う事なきうんこ人間だ。
そもそも、こいつほど無思慮に生きている人間は、出来上がった作品を人にどう評価されようとも何の感慨も浮かばないに決まっている。
だからいつまで経っても成長しないんだ。
だからaikoとか聴いているんだ。
心の中でひとしきりタクヤのことを罵倒した局長は、この後の流れが必ず「今すぐ読ませてよ!」となるであろうことに絶望した。
少なくとも部活の時間まで引き延ばせるはずの審判が、無理やり今この瞬間に執行される。
それを絶望と言わずに何というべきであろうか。
「え!ホント!すごい!すごいよ!高井君!それ見せてよ!今、持っている?」
守山は予定調和を乱すことなく、流れるように話す。
「いや…弁当しか持ってなくて…教室にあるんです。」
「持ってきてよ。今、ゆっくり読みたいよ。」
局長のやんわりとした拒絶など瞬時に吹き飛ばして守山は言ってのけた。
「行って来いよ。どうせ、部活の時間に見せるつもりだったんだろう?」
タクヤの容赦ない援護も飛んでくる。
局長は諦めた様子で、少しだけ天を仰ぎ「ちょっと待ってくださいよ。」そう言って、踵を返した。
デリカシーのかけらもない2人に何を言っても無駄だ。
こっちの気持ちなど何も考慮することが出来ない短絡的で本能的な言動の数々。
いっそのこと、このままバックレてやろうか。
ついでに部活もさぼってやろうか。
局長はささくれながら、しかし何故か早足で教室へ戻っていった。
本心では、早くこの圧倒的自信作を読んでもらいたい。
だた、圧倒的自信作であるために、否定的評価をされることに対してかつてない恐怖も感じている。
二律背反した理性が局長の中でせめぎあっていた。
最終的には小走りになり、少し息を切らせながら局長は台本を手に戻ってきた。
「ふぅ…これです。」
いつも通りの小汚いしわくちゃになったルーズリーフ約30枚を守山に手渡した。
「今から読むから、高井君たちは気にしないで、ご飯食べてて。」
そう言うと、守山はルーズリーフに目を落とした。
「今回の話はどうなんだ?」
弁当を頬張りながら、タクヤが話しかけてくる。
「…」
「……」
「…………」
「おい、何か言えよ。」
「部長が読んでいるからまた後で。」
「何だよ…それ?」
守山の評価が気になりすぎてタクヤの言動など歯牙にもかけない。
数分だったか、十数分だったか、数十分だったか。
局長にとっては永遠にも等しい沈黙の時間が流れる。
最後のルーズリーフを読み終えた守山が局長の方を向いた。
「読んだよ。」
「……」
局長は自分の心音が大きすぎて聞こえなくなる位には緊張していた。
心臓はもうどこかに行ってしまったのかもしれない。
「部長?面白いですか?」
何も話さない局長に変わって、タクヤが投げかける。
「うん。そうだなぁ…」
少し間をおいてから守山は局長の目を見て話し始めた。
「少し気になるところはあるけど、全体的には良いと思うよ。テーマも展開も面白いし。今日の部活でくーちゃん達に読んでもらってからにはなるけど、次の高文祭は、この話でやっていいんじゃないかな?少なくともあたしはこの話をやりたい。」
守山の返答を聴きながら、局長は目の前が真っ白になっていく感覚に襲われていた。
じわじわじわじわじわじわじわじわじわ…
目の前の光景が、白色のペンキで少しずつ塗りつぶされていくような。
意識はしっかりとあるのに、ゆっくりと意識が遠のいていくような。
これまで経験した事がないような実に不思議な感覚だ。
指先がびりびりと痺れている事だけは分かる。
自分が例えこれから50年、100年生きたとしても、人生最良の日はいつですかと聞かれたら、迷いなく今日だと答えるだろう。
その位の感激が局長を襲った。
指先が震えている事を悟られないように、静かに、少しずつ細かい呼吸を何度も行う。
「そうですか。今回は使って貰えそうで良かったっす。」
限界まで冷静を装ってそう話したが、はち切れんばかりの喜びは溢れに溢れ、粗い鼻息と気持ち悪いニヤケ顔になっていた。
「おおお!すげぇ!やったな。オレにも読ませてくれよ。」
そう言うと、タクヤは守山から渡されたルーズリーフを読み始める。
「タイトルは、付喪神って言うのか…」
そのタイミングで昼休みの終わりを告げるチャイムが鳴り始めた。
「まぢかぁ~」
タクヤはつぶやきつつ、そのまま台本を読み続けていた。
「あぁ~お昼食べ損ねちゃった。部活の時に食べようかなぁ~」
台本を読んでいた守山は、昼食を取れなかったようだ。
「あれ?高井君も食べなかったの?」
「ええ…なんか、悪いなと思って。」
「別に気にしなくても良いのに…浦沢君は全部食べているよ。」
「まぁ、良いんですよ。こいつは圧倒的無思慮人間なので。」
「何それ。」
少しだけ笑みを浮かべた守山は「じゃあ、部活で!」と言うと、自分の教室へ戻っていった。
「オレ達も戻るか。」
局長はそう言って、タクヤの手からルーズリーフを奪い取った。
「おい!まだ読んでいる途中なんだよ。」
「いいんだよ。別にお前は全部読まなくても。」
そう言うと、局長も自分の教室へ歩き出した。
「しゃあねえな。」
釈然としないながらも、タクヤも後に続く。
その足取りは、まるで羽でもついているのかと言うほどに軽いものだった。
そして、午後の授業も引き続き、当然のように睡眠時間となった。

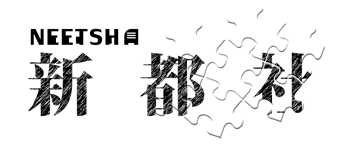

しもたろうに 先生に励ましのお便りを送ろう!!
〒みんなの感想を読む