ひとときの暗がり
作:しもたろうに
[website]
![]()
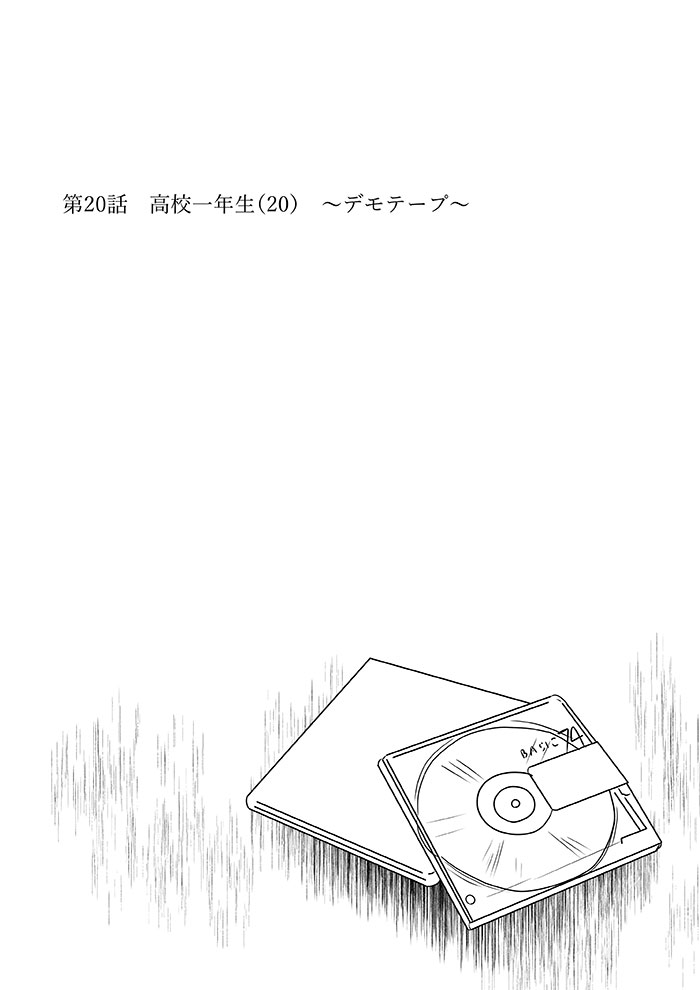
+
文化祭では、かなりの人数の前で演劇公演と、バンドとしてライブ演奏を行った。
あの日、一高生の中で一番長い時間ステージに立っていたのは、どう考えても局長をはじめとしたシータのメンバーだっただろう。
でも、その後の日常は何も変わらなかった。
「砂漠の砂鉄」のような扱いは相も変わらず。
クラスに居場所のないタクヤと局長は、いつもと同じようにトイレの裏のこじんまりとしたスペースで、お昼の弁当を食べている。
一高の校舎は三階建てで、1年生は3階、2年生は1階、3年生は2階と少し変則的な割り振りになっていた。
三階の隅にあるトイレ裏からは、校門を入ってすぐのエントランス部分を一望することが出来る。
「まぁそんなもんだよな。」
エントランス部分で楽しそうに話している女生徒たちを眺めながらタクヤはつぶやいた。
局長も同じ気分だ。
演劇だろうと、バンドだろうと、手段は問題ではない。
人前で目立てばチヤホヤされるはずだ。
そんな妄想に憑りつかれていた。
しかし現実は何も変わることがない。
元々モテていた白石は、バンド演奏後出待ちの女の子に囲まれていた。
元々歯牙にもかけてもらえない局長たちは、どれだけ人前に立とうが、誰からも見向きもされない。
そんな絶対的事実を前に、あの熱気は何だったのか。と、やはり考えずにはいられなかったのだ。
「おおおおおおおおお!ホントにいたいた!」
不意に聞こえた声に振り向いた局長とタクヤの目線の先に、チョッと息を切らせた守山が立っていた。
「あれ?部長?どうしたんですか?」
タクヤが驚いたように尋ねた。
「この前部活の時に栗山くんに教えてもらったんだ。2人はいつも昼休み、ここでお弁当食べているって。」
「まぁ、それはそうですけど…」
突然の出来事に挙動不審になる2人を横目に、守山は「聞いて聞いて」と息を整えながら呟く。
「実は…チョッとだけ、お願い事があるんだけど…」
守山は1枚のMDを差し出した。
「??これは何ですが?」
「あのさぁ。…え~とぉ…実は…あの…その…私もチョッと前から作曲…?と言うか、メロディーを作ったりしているんだよね。それでさぁ…それがいっぱい溜まってきたから…繋げて曲にしてみて…これ、私が作った曲なんだけど…もし…もしだよ…2人が聴いてみて使えそうだったら、バンドで…やってみてくれたり…しない…かな…?」
「は・・?」
唐突な守山の提案に固まる2人。
「いや、ほんと聞いてダメだったら全然ダメって言って貰って良いから!でもさぁ、ほら…何て言うのかなぁ…バンドのああ言うの憧れなんだよね…でも自分でバンドとかできないし…でね…もし、私の曲をやってもらえたらこんなうれしい事ないなぁとか思っちゃって…それでさ、ほんと聞くに堪えないとは思うんだけど、頑張って録ってみたんだよ…そりゃあ、バンドずっとやってる2人とは比べられるレベルじゃないと思うけど…もし…もし使えそうなら…」
守山は異常なほど謙虚になりながら、珍しくたどたどしいしゃべりを続ける。
手を胸の前において前後しながら話している。
守山が緊張した時に出るいつもの挙動だった。
「一応、2曲入っているから聴いてみて…くれない…?」
「いや!そりゃあもちろん!聴かせてもらいますよ!ありがとうございます!なぁ!局長!」
「あ…あぁ…それはもう。ありがとうございます!と言うか、絶対使わせてもらうと思いますよ。」
「お前、それは大丈夫なのか…?」
「良かったぁ!でもほんとに、ダメだったら使わなくて良いからね…それからぁ…もう一つお願いがあるんだけど…」
今度は落ち着いた様子で話し始める。
「何ですか?」
「2人はいつもここでご飯食べているの?」
「まぁほぼ100%ここですね。オレらクラスで浮きまくってて、もう9月だってのに、友達クラスに居ないんすよ。」
タクヤが馬鹿笑いをしながら答えた。
「あのさぁ…あたしも時々ここで一緒にご飯食べてもいい?…実は、あたしもクラスにあんまり居場所なくってさ。」
そう言うと、守山は少し照れたように頭をポリポリとかいた。
「だって…局長どうする…?オレは別に全然いいけど…」
タクヤは何故かニヤニヤしながら局長の方を振り返る。
「オ…オレも別に良いよ。」
「やったぁ~嬉しいぃ。じゃあ、今日はもうお昼食べちゃったから明日から来させてね!」
そう言うと、守山はいつものようにぴょんと軽く跳ねたあと、「じゃあね。お邪魔しましたぁ。」と言って戻っていった。
……
……………
……………………
少しの沈黙。
「お前すげぇ人見知りなのに、良いって言うと思わなかったよ。」
沈黙を破ってタクヤが話しかける。
「なぁ?」
局長は苦笑いをしながら答える。
「時々って言っていたけど、明日からって事は、あれは毎日来るな。」
「どうする?ここに女がいたら、もうでっかい声で『おまんこぉおおおお!!』って絶叫できなくなるけど…」
「そんなことした事あったっけ。」
「いつもやってるだろ…おまんこおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお!!」
「バカ!やめろって!!!ほら、あの凄い可愛いおまんこおおおおおおおおおおおお!!が睨んできてるじゃないか!おい!やめろよぉ!!」
「おまんこおおおおおおおおおおおおおおお!!」
エントランスに居た数名の女の子たちは怪訝そうな表情で局長たちを見上げている。
そんな年頃の女の子を見下ろしながら局長は恐ろしく気持ち悪い表情でニヤニヤ。
その横で、止めるそぶりを見せつつタクヤは馬鹿笑いしている。
最低の童貞2人だった。
クラスに居場所など出来るはずもない。
「さて。じゃあ、そのデモテープはお前に渡しておくよ。」
そう言うと、守山から渡されたMDを局長に渡した。
先日、文化祭のあと、今度の「ゆ~ぷらざ」でのライブの詳細を聞いたタクヤは、もちろん出演を快諾した。
その上で、「オリジナル曲を評価されての出演である以上、オリジナル曲でのライブは致し方なし」と言う結論に落ち着いた。
文化祭のライブでコピー曲を行い、過去最高の盛り上がりを経験した事で、ある程度満足した部分もあったかも知れない。
それでも、この結論に落ち着くまで、文化祭の日以降、2人は何度も議論を交わしてはいた。
決まっていても取り合えず言い争う。
2人はそんな関係だった。
「お前、曲足りないって言っていたよな?この部長の2曲をやるとしたらどうなんだ?」
「どうだろう…オレも何曲か作ってはいるんだけど、イマイチ良いのができなくて。この2曲が使えるとしても、あと1曲は作らないと…」
指折り考える局長。
「部長も曲作ってくれたし、オレも1曲作ってみて良いかな?」
「まぢか?!!」
あれだけオリジナル曲をやりたがらなかったタクヤが、自分で曲を作る。
タクヤの想定外の提案に局長は驚いた。
「ただ、オレ楽譜とか全然分からないから、作った曲を良い感じに修正してくれたらだけど…」
「もちろん!全然違う曲に書き換えてやるよ。」
「お前ふざけんなよ!」
そう言うと2人はまたゲラゲラと馬鹿笑いしあった。
その時、昼休みを終えるチャイムが鳴り響いた。
それは奇しくも、へっぽこバンド「シータ」第2章の始まりを告げるチャイムのようでもあった。
あの日、一高生の中で一番長い時間ステージに立っていたのは、どう考えても局長をはじめとしたシータのメンバーだっただろう。
でも、その後の日常は何も変わらなかった。
「砂漠の砂鉄」のような扱いは相も変わらず。
クラスに居場所のないタクヤと局長は、いつもと同じようにトイレの裏のこじんまりとしたスペースで、お昼の弁当を食べている。
一高の校舎は三階建てで、1年生は3階、2年生は1階、3年生は2階と少し変則的な割り振りになっていた。
三階の隅にあるトイレ裏からは、校門を入ってすぐのエントランス部分を一望することが出来る。
「まぁそんなもんだよな。」
エントランス部分で楽しそうに話している女生徒たちを眺めながらタクヤはつぶやいた。
局長も同じ気分だ。
演劇だろうと、バンドだろうと、手段は問題ではない。
人前で目立てばチヤホヤされるはずだ。
そんな妄想に憑りつかれていた。
しかし現実は何も変わることがない。
元々モテていた白石は、バンド演奏後出待ちの女の子に囲まれていた。
元々歯牙にもかけてもらえない局長たちは、どれだけ人前に立とうが、誰からも見向きもされない。
そんな絶対的事実を前に、あの熱気は何だったのか。と、やはり考えずにはいられなかったのだ。
「おおおおおおおおお!ホントにいたいた!」
不意に聞こえた声に振り向いた局長とタクヤの目線の先に、チョッと息を切らせた守山が立っていた。
「あれ?部長?どうしたんですか?」
タクヤが驚いたように尋ねた。
「この前部活の時に栗山くんに教えてもらったんだ。2人はいつも昼休み、ここでお弁当食べているって。」
「まぁ、それはそうですけど…」
突然の出来事に挙動不審になる2人を横目に、守山は「聞いて聞いて」と息を整えながら呟く。
「実は…チョッとだけ、お願い事があるんだけど…」
守山は1枚のMDを差し出した。
「??これは何ですが?」
「あのさぁ。…え~とぉ…実は…あの…その…私もチョッと前から作曲…?と言うか、メロディーを作ったりしているんだよね。それでさぁ…それがいっぱい溜まってきたから…繋げて曲にしてみて…これ、私が作った曲なんだけど…もし…もしだよ…2人が聴いてみて使えそうだったら、バンドで…やってみてくれたり…しない…かな…?」
「は・・?」
唐突な守山の提案に固まる2人。
「いや、ほんと聞いてダメだったら全然ダメって言って貰って良いから!でもさぁ、ほら…何て言うのかなぁ…バンドのああ言うの憧れなんだよね…でも自分でバンドとかできないし…でね…もし、私の曲をやってもらえたらこんなうれしい事ないなぁとか思っちゃって…それでさ、ほんと聞くに堪えないとは思うんだけど、頑張って録ってみたんだよ…そりゃあ、バンドずっとやってる2人とは比べられるレベルじゃないと思うけど…もし…もし使えそうなら…」
守山は異常なほど謙虚になりながら、珍しくたどたどしいしゃべりを続ける。
手を胸の前において前後しながら話している。
守山が緊張した時に出るいつもの挙動だった。
「一応、2曲入っているから聴いてみて…くれない…?」
「いや!そりゃあもちろん!聴かせてもらいますよ!ありがとうございます!なぁ!局長!」
「あ…あぁ…それはもう。ありがとうございます!と言うか、絶対使わせてもらうと思いますよ。」
「お前、それは大丈夫なのか…?」
「良かったぁ!でもほんとに、ダメだったら使わなくて良いからね…それからぁ…もう一つお願いがあるんだけど…」
今度は落ち着いた様子で話し始める。
「何ですか?」
「2人はいつもここでご飯食べているの?」
「まぁほぼ100%ここですね。オレらクラスで浮きまくってて、もう9月だってのに、友達クラスに居ないんすよ。」
タクヤが馬鹿笑いをしながら答えた。
「あのさぁ…あたしも時々ここで一緒にご飯食べてもいい?…実は、あたしもクラスにあんまり居場所なくってさ。」
そう言うと、守山は少し照れたように頭をポリポリとかいた。
「だって…局長どうする…?オレは別に全然いいけど…」
タクヤは何故かニヤニヤしながら局長の方を振り返る。
「オ…オレも別に良いよ。」
「やったぁ~嬉しいぃ。じゃあ、今日はもうお昼食べちゃったから明日から来させてね!」
そう言うと、守山はいつものようにぴょんと軽く跳ねたあと、「じゃあね。お邪魔しましたぁ。」と言って戻っていった。
……
……………
……………………
少しの沈黙。
「お前すげぇ人見知りなのに、良いって言うと思わなかったよ。」
沈黙を破ってタクヤが話しかける。
「なぁ?」
局長は苦笑いをしながら答える。
「時々って言っていたけど、明日からって事は、あれは毎日来るな。」
「どうする?ここに女がいたら、もうでっかい声で『おまんこぉおおおお!!』って絶叫できなくなるけど…」
「そんなことした事あったっけ。」
「いつもやってるだろ…おまんこおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお!!」
「バカ!やめろって!!!ほら、あの凄い可愛いおまんこおおおおおおおおおおおお!!が睨んできてるじゃないか!おい!やめろよぉ!!」
「おまんこおおおおおおおおおおおおおおお!!」
エントランスに居た数名の女の子たちは怪訝そうな表情で局長たちを見上げている。
そんな年頃の女の子を見下ろしながら局長は恐ろしく気持ち悪い表情でニヤニヤ。
その横で、止めるそぶりを見せつつタクヤは馬鹿笑いしている。
最低の童貞2人だった。
クラスに居場所など出来るはずもない。
「さて。じゃあ、そのデモテープはお前に渡しておくよ。」
そう言うと、守山から渡されたMDを局長に渡した。
先日、文化祭のあと、今度の「ゆ~ぷらざ」でのライブの詳細を聞いたタクヤは、もちろん出演を快諾した。
その上で、「オリジナル曲を評価されての出演である以上、オリジナル曲でのライブは致し方なし」と言う結論に落ち着いた。
文化祭のライブでコピー曲を行い、過去最高の盛り上がりを経験した事で、ある程度満足した部分もあったかも知れない。
それでも、この結論に落ち着くまで、文化祭の日以降、2人は何度も議論を交わしてはいた。
決まっていても取り合えず言い争う。
2人はそんな関係だった。
「お前、曲足りないって言っていたよな?この部長の2曲をやるとしたらどうなんだ?」
「どうだろう…オレも何曲か作ってはいるんだけど、イマイチ良いのができなくて。この2曲が使えるとしても、あと1曲は作らないと…」
指折り考える局長。
「部長も曲作ってくれたし、オレも1曲作ってみて良いかな?」
「まぢか?!!」
あれだけオリジナル曲をやりたがらなかったタクヤが、自分で曲を作る。
タクヤの想定外の提案に局長は驚いた。
「ただ、オレ楽譜とか全然分からないから、作った曲を良い感じに修正してくれたらだけど…」
「もちろん!全然違う曲に書き換えてやるよ。」
「お前ふざけんなよ!」
そう言うと2人はまたゲラゲラと馬鹿笑いしあった。
その時、昼休みを終えるチャイムが鳴り響いた。
それは奇しくも、へっぽこバンド「シータ」第2章の始まりを告げるチャイムのようでもあった。

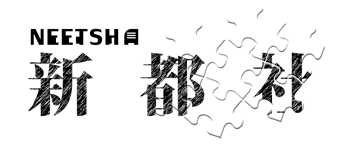

しもたろうに 先生に励ましのお便りを送ろう!!
〒みんなの感想を読む