ひとときの暗がり
作:しもたろうに
[website]
![]()

+
文化祭当日がやってきた。
この手の学校行事は、局長にとって耐えがたい拷問でしかない。
クラス内では、相も変わらず「砂漠の砂鉄」の如く、そこに居たとしても認識もされない扱いを受けている局長は、例年通りクラスの出し物には一切関わらせてもらえなかった。
局長の通っている「一高」の文化祭では、午前中はクラスの出し物を来訪者に見せるため全員自分の教室で待機し、午後から他クラスの出し物などを見るための自由時間になると言う謎のルールがあった。
楽しそうにはしゃいでいるクラスメートや、イチャイチャしているカップルを横目に1人、雲の流れを見上げるだけの時間が続く。
「今すぐUFOが降ってきて、西山カップルをキャトルミューティレーションで攫っていってくれないかな。西山は惨たらしく殺されて、佐山は気持ち悪い宇宙人の触手に子宮を突き破られて、内臓ごとレイプされれば良いのに。」
どす黒い妄想と共に、静かにささくれ立つ局長。
同じような妄想を持つものが数多く存在し、後年「触手」と言うエロジャンルが確立されることなど、この当時知る由もなかった。
何物にも耐えがたい苦痛の午前中が終わり、午後からの自由時間。
局長にとって、本当の意味での文化祭はここから始まる。
とは言え、もちろん仲のいい友達と他のクラスの出し物を見て回ると言った、俗物が画一的に行うどうしようもなく下賤な行為に時間を費やすわけではない。
午後1時から体育館で演劇公演があり、その後3時からはバンド演奏の時間があるのだ。
演劇部の待機場所になっていた体育館横の理科準備室に行くと、すでに演劇部の面々が本番に向けて衣装を着け、顔にドーランを塗っていた。
ムラヤンとウルオは、二人で台本を片手にセリフの確認を行っている。
「あ!高井君!高井君も早く神様の衣装を着て、準備して!」
局長を見つけた守山は自分の髪をセットしつつ、声をかけた。
「体育館見てきたか?なんか思ってる以上に人いるぞ…」
タクヤがチョッとニヤニヤしながら、余計な情報を伝えてくる。
バンドでのライブは、中学生の頃と先日の「ティーンズライブフェスタ」を経験しているものの、今回は少し事情が違う。
これまで、村人AやザリガニCなどの橋のも棒にもかからないような役柄しかやった事のなかった局長が、大勢の人の前に立ってセリフをしゃべり、演技をするのだ。
ライブでキーボードを弾く行為とは全然違った緊張感があった。
午後1時。
予定通り開演。
局長は舞台袖から、いつもの演劇部面々の演技を腕組みして見ていた。
「うむ。本番とは言え、皆いつも通りの力を発揮しているな」。
気分は蜷川幸雄だ。
そして、神様の出番。
意を決した局長は「うひょひょひょひょ」と言う謎の笑い声と共に光の中へと出ていった。
人生で初めての演劇公演は、当たり前のように進行し、終演に向かう。
そのまま、カーテンコールを行った。
大きな拍手と歓声が上がる。
想像以上に好評のまま、局長は初めての演劇公演を終えることが出来たようだ。
夏休みを通して、この公演までには色んな事があった。
「マリオネット」が不採用になった事も、「ティーンズライブフェスタ」に出演した事も、心が折れかけた事も、演劇を頑張ろうと決意した事も。
わずか2か月ほどとは言えない。
思春期の2か月は、成人諸兄の2か月とは訳が違うのだ。
本来ならそんな余韻に浸りつつも、今回の公演についての反省会を込めた話し合いがあるのだが、局長たちは30分後にバンドとしての出演が待っていた。
「じゃあ、浦沢君たちはもういいから早く次の準備をしてきて!」
予め、ライブ演奏のことを伝えていた守山が局長たちを促す。
「がんばってこいよぉ~!」
黒崎が大げさに手をブンブンと振りながら送り出した。
急ぎ足で、理科準備室にやってきた面々は、急いでバタバタとドーランを洗い流し、衣装を着替える。
照明係でメイクなどをしていなかったタクヤは、持ってきていたワックスで髪型を整え始めた。
今回だけのサポートギター白石も理科準備室にやってきた。
「タクヤ!行こう!」
「分かった。じゃあ、オレ先行ってセッティングしてくるよ!」
そう言って、タクヤと白石は先んじてステージに向かった。
局長、ムラヤン、ウルオはいそいそと自分の準備を完了させて、そのまま走ってステージに向かっていった。
緊張している暇もなく、何だか良く分からないまま、ライブは開演してしまった。
「これで良いのか?いや、これで良いのだ。」
さながらバカボンのパパになり切った局長は、そうつぶやきながら、鍵盤に手を置いた。
この日の出演バンドは3組。
その内、局長とタクヤ率いる「シータ」は運よくなのか、運悪くなのか1組目の出演だ。
ダダダダ・ダ・ダ・ダ・ダ・ダ・ダ・ダ・ダ!
1曲目、GLAYの大名曲「誘惑」イントロのドラムが鳴り響く。
「きゃあああああああああ!!」
クラスにファンがいるモテモテイケメン白石のお陰でステージ前に詰めかけていた女の子たちから悲鳴にも似た歓声が上がる。
その後も順調にGLAYの名曲を次々と演奏していった。
「皆さん…暑いですよね。次の曲は少し涼しくなってほしい思いを込めて歌います。聞いてください。Winter Again。」
さっきまで同じステージでミニスカートの女子高生を扮していたムラヤンに怖いものはない。
いつもとは違う軽快なムラヤンのMCにドッと笑いが起きている。
ライブは局長が経験したことがないほど大盛況のまま終わった。
ステージを降りると、体育館の出口には数人の女の子たちが出待ちしていた。
「かっこよかったです~」
「最高でした」
数人の女の子は白石を囲んで口々に褒めたたえている。
その光景を目の当たりにした4人。
「白石さんすげぇ~な」
「やっぱかっこいいよなぁ」
バンドマンは女にモテる。と、なぜか思春期の頃、特に童貞男子高校生は考えがちになる。
そして、実際にバンドを始める女に飢えた童貞男子高校生は世界中に数知れない。
だがしかし、現実は「バンドマンがモテる」のではなく、「モテる奴がバンドマンになれば尚モテる」だけなのだ。
モテない奴は何をやったってモテないと言う事実を、白石と自分たちの歴然とした状態を目の当たりにしつつ、今、この瞬間に体験していた。
「良かったよ!片付けとかあって、途中からしか見られなかったけど。」
そんな4人を見つけた守山が声をかけながら走り寄ってきた。
「見てくれたんですね!良かったぁ!何か、今日は公演の後だったのもあったのか、普通に楽しんでライブやれましたよ」
それでいてもライブ終わりの興奮状態にあったタクヤは早口にそう答えた。
確かに今回のライブは、前回とは違うと局長も感じていた。
しっかりと記憶が残っている。
熱気も、受けも、盛り上がりも、汗で鍵盤が滑って変な不協和音が出たことさえも。
「演劇部の皆で見てたんだよ。でね、今度ライブあったら、皆も見に行きたいって。」
「おおお!!すごい!まぢっすか!」
「恥ずかしい…です…」
「凄い凄い。」
タクヤ、ムラヤン、ウルオは守山の言葉に対して次々と喜びを口にする
「あの!実は!」
局長はそれをかき消すように大きな声を出した。
チョッと裏返っていた。
「今度、オレ達『ゆーぷらざ』でライブするんですけど…!」
「え?『ゆーぷらざ』ってあの、宇多津にある大きなホールの?」
「そう。キャパ1000人くらいらしい…」
「うそ!凄い凄い!シータも遂にホールでライブするようになったのかぁ~」
守山は嬉しそうにぴょんと飛び跳ねて「絶対見に行くよ」と答えた。
「ちょっと待て!なんだその話?オレ聞いてないぞ」
タクヤがさらに大きな声で局長に詰め寄る。
「あ…そういえば!」
演劇とライブの練習で結局このことを誰にも伝えていないまま、この日迎えていた事を局長は思い出した。
「悪い…言ってなかったかも…え~と…ライブ…あるよ。やる?」
完全に口だけの「悪い」と悪びれもしない局長の態度に、タクヤの表情筋はピクピクと痙攣している。
さっきまでの興奮は、別の興奮に移行したようだ。
「ちょっと、お前こっち来い」
タクヤは局長の首根っこをつかんで体育館裏に連れて行った。
「大丈夫かなぁ~」
守山は心配そうにその情景を眺めていた。
「なぁ~に、いつものことですよ。」
特に心配も何もしてないウルオがそうつぶやき、ムラヤンは静かに首を縦に振った。
すでに、後夜祭が始まろうとしている時間になっていた。
この手の学校行事は、局長にとって耐えがたい拷問でしかない。
クラス内では、相も変わらず「砂漠の砂鉄」の如く、そこに居たとしても認識もされない扱いを受けている局長は、例年通りクラスの出し物には一切関わらせてもらえなかった。
局長の通っている「一高」の文化祭では、午前中はクラスの出し物を来訪者に見せるため全員自分の教室で待機し、午後から他クラスの出し物などを見るための自由時間になると言う謎のルールがあった。
楽しそうにはしゃいでいるクラスメートや、イチャイチャしているカップルを横目に1人、雲の流れを見上げるだけの時間が続く。
「今すぐUFOが降ってきて、西山カップルをキャトルミューティレーションで攫っていってくれないかな。西山は惨たらしく殺されて、佐山は気持ち悪い宇宙人の触手に子宮を突き破られて、内臓ごとレイプされれば良いのに。」
どす黒い妄想と共に、静かにささくれ立つ局長。
同じような妄想を持つものが数多く存在し、後年「触手」と言うエロジャンルが確立されることなど、この当時知る由もなかった。
何物にも耐えがたい苦痛の午前中が終わり、午後からの自由時間。
局長にとって、本当の意味での文化祭はここから始まる。
とは言え、もちろん仲のいい友達と他のクラスの出し物を見て回ると言った、俗物が画一的に行うどうしようもなく下賤な行為に時間を費やすわけではない。
午後1時から体育館で演劇公演があり、その後3時からはバンド演奏の時間があるのだ。
演劇部の待機場所になっていた体育館横の理科準備室に行くと、すでに演劇部の面々が本番に向けて衣装を着け、顔にドーランを塗っていた。
ムラヤンとウルオは、二人で台本を片手にセリフの確認を行っている。
「あ!高井君!高井君も早く神様の衣装を着て、準備して!」
局長を見つけた守山は自分の髪をセットしつつ、声をかけた。
「体育館見てきたか?なんか思ってる以上に人いるぞ…」
タクヤがチョッとニヤニヤしながら、余計な情報を伝えてくる。
バンドでのライブは、中学生の頃と先日の「ティーンズライブフェスタ」を経験しているものの、今回は少し事情が違う。
これまで、村人AやザリガニCなどの橋のも棒にもかからないような役柄しかやった事のなかった局長が、大勢の人の前に立ってセリフをしゃべり、演技をするのだ。
ライブでキーボードを弾く行為とは全然違った緊張感があった。
午後1時。
予定通り開演。
局長は舞台袖から、いつもの演劇部面々の演技を腕組みして見ていた。
「うむ。本番とは言え、皆いつも通りの力を発揮しているな」。
気分は蜷川幸雄だ。
そして、神様の出番。
意を決した局長は「うひょひょひょひょ」と言う謎の笑い声と共に光の中へと出ていった。
人生で初めての演劇公演は、当たり前のように進行し、終演に向かう。
そのまま、カーテンコールを行った。
大きな拍手と歓声が上がる。
想像以上に好評のまま、局長は初めての演劇公演を終えることが出来たようだ。
夏休みを通して、この公演までには色んな事があった。
「マリオネット」が不採用になった事も、「ティーンズライブフェスタ」に出演した事も、心が折れかけた事も、演劇を頑張ろうと決意した事も。
わずか2か月ほどとは言えない。
思春期の2か月は、成人諸兄の2か月とは訳が違うのだ。
本来ならそんな余韻に浸りつつも、今回の公演についての反省会を込めた話し合いがあるのだが、局長たちは30分後にバンドとしての出演が待っていた。
「じゃあ、浦沢君たちはもういいから早く次の準備をしてきて!」
予め、ライブ演奏のことを伝えていた守山が局長たちを促す。
「がんばってこいよぉ~!」
黒崎が大げさに手をブンブンと振りながら送り出した。
急ぎ足で、理科準備室にやってきた面々は、急いでバタバタとドーランを洗い流し、衣装を着替える。
照明係でメイクなどをしていなかったタクヤは、持ってきていたワックスで髪型を整え始めた。
今回だけのサポートギター白石も理科準備室にやってきた。
「タクヤ!行こう!」
「分かった。じゃあ、オレ先行ってセッティングしてくるよ!」
そう言って、タクヤと白石は先んじてステージに向かった。
局長、ムラヤン、ウルオはいそいそと自分の準備を完了させて、そのまま走ってステージに向かっていった。
緊張している暇もなく、何だか良く分からないまま、ライブは開演してしまった。
「これで良いのか?いや、これで良いのだ。」
さながらバカボンのパパになり切った局長は、そうつぶやきながら、鍵盤に手を置いた。
この日の出演バンドは3組。
その内、局長とタクヤ率いる「シータ」は運よくなのか、運悪くなのか1組目の出演だ。
ダダダダ・ダ・ダ・ダ・ダ・ダ・ダ・ダ・ダ!
1曲目、GLAYの大名曲「誘惑」イントロのドラムが鳴り響く。
「きゃあああああああああ!!」
クラスにファンがいるモテモテイケメン白石のお陰でステージ前に詰めかけていた女の子たちから悲鳴にも似た歓声が上がる。
その後も順調にGLAYの名曲を次々と演奏していった。
「皆さん…暑いですよね。次の曲は少し涼しくなってほしい思いを込めて歌います。聞いてください。Winter Again。」
さっきまで同じステージでミニスカートの女子高生を扮していたムラヤンに怖いものはない。
いつもとは違う軽快なムラヤンのMCにドッと笑いが起きている。
ライブは局長が経験したことがないほど大盛況のまま終わった。
ステージを降りると、体育館の出口には数人の女の子たちが出待ちしていた。
「かっこよかったです~」
「最高でした」
数人の女の子は白石を囲んで口々に褒めたたえている。
その光景を目の当たりにした4人。
「白石さんすげぇ~な」
「やっぱかっこいいよなぁ」
バンドマンは女にモテる。と、なぜか思春期の頃、特に童貞男子高校生は考えがちになる。
そして、実際にバンドを始める女に飢えた童貞男子高校生は世界中に数知れない。
だがしかし、現実は「バンドマンがモテる」のではなく、「モテる奴がバンドマンになれば尚モテる」だけなのだ。
モテない奴は何をやったってモテないと言う事実を、白石と自分たちの歴然とした状態を目の当たりにしつつ、今、この瞬間に体験していた。
「良かったよ!片付けとかあって、途中からしか見られなかったけど。」
そんな4人を見つけた守山が声をかけながら走り寄ってきた。
「見てくれたんですね!良かったぁ!何か、今日は公演の後だったのもあったのか、普通に楽しんでライブやれましたよ」
それでいてもライブ終わりの興奮状態にあったタクヤは早口にそう答えた。
確かに今回のライブは、前回とは違うと局長も感じていた。
しっかりと記憶が残っている。
熱気も、受けも、盛り上がりも、汗で鍵盤が滑って変な不協和音が出たことさえも。
「演劇部の皆で見てたんだよ。でね、今度ライブあったら、皆も見に行きたいって。」
「おおお!!すごい!まぢっすか!」
「恥ずかしい…です…」
「凄い凄い。」
タクヤ、ムラヤン、ウルオは守山の言葉に対して次々と喜びを口にする
「あの!実は!」
局長はそれをかき消すように大きな声を出した。
チョッと裏返っていた。
「今度、オレ達『ゆーぷらざ』でライブするんですけど…!」
「え?『ゆーぷらざ』ってあの、宇多津にある大きなホールの?」
「そう。キャパ1000人くらいらしい…」
「うそ!凄い凄い!シータも遂にホールでライブするようになったのかぁ~」
守山は嬉しそうにぴょんと飛び跳ねて「絶対見に行くよ」と答えた。
「ちょっと待て!なんだその話?オレ聞いてないぞ」
タクヤがさらに大きな声で局長に詰め寄る。
「あ…そういえば!」
演劇とライブの練習で結局このことを誰にも伝えていないまま、この日迎えていた事を局長は思い出した。
「悪い…言ってなかったかも…え~と…ライブ…あるよ。やる?」
完全に口だけの「悪い」と悪びれもしない局長の態度に、タクヤの表情筋はピクピクと痙攣している。
さっきまでの興奮は、別の興奮に移行したようだ。
「ちょっと、お前こっち来い」
タクヤは局長の首根っこをつかんで体育館裏に連れて行った。
「大丈夫かなぁ~」
守山は心配そうにその情景を眺めていた。
「なぁ~に、いつものことですよ。」
特に心配も何もしてないウルオがそうつぶやき、ムラヤンは静かに首を縦に振った。
すでに、後夜祭が始まろうとしている時間になっていた。

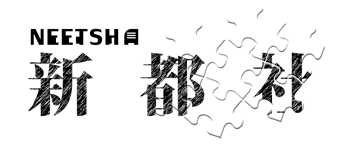

しもたろうに 先生に励ましのお便りを送ろう!!
〒みんなの感想を読む