ひとときの暗がり
作:しもたろうに
[website]
![]()

+
もう何日、演劇部の練習に参加していないのだろうか。
おそらく自分の代わりに新しい「神様」が誕生していて、自分なんかお払い箱になっている。
自分が無用の長物となっていることを確認することになると考えると、ただでさえ重い足がまるで鉛の塊となり、その一歩を踏み出すことが出来ない。
かと言って、練習に参加しなければ、お払い箱になっている確率はさらに高くなるに決まっている。
どちらにしても絶望。
絶望と絶望がくるくると交差する負のスパイラルの中で局長の心はドコまでもドコまでも落ち続けていた。
不意に、今練習している「すてふぁにー」の台本を手にとってみる。
物語は止まる事のない時間を食事する過食症の女子高生「弁当食い女」をテーマの軸に、女に飢えている男子校に通う2人の童貞男子がスネ毛を剃って女装し、女子高に潜入するところから始まる。
楽園だと思っていた女子高内で、生徒間のいじめや異性関係など学校問題、人の死を含めたこの世の不条理を見せつけられた2人の男子高校生が、少しずつ問題の核心に触れていく。
この作品を良しとして選んだ演劇部全員が言ってみれば「病んでいた」としか思えない。
そんな重苦しく、仄暗い物語だ。
読み終えたあと、今局長が執筆している「付喪神」を読んでみた。
負けていない。
いや、「付喪神」の方が面白い。
局長は、昔から自分が作った作品こそ最高に面白いと言う絶対の自信だけは常に持ち合わせており、それはもちろん今回の「付喪神」においても変わりない。
「この話を皆に見せれば、きっとオレの評価はくるりと180度位は変わるはず。何より、今辞めてしまえば、もうこの話を書いた意味も誰かに見せる機会自体もなくなってしまう…」
タクヤにライブの話を持っていくと言う、強引な理由付けをして決意した。
それでもなお、演劇部の練習に向かう一歩を踏み出すことが出来ない。
練習開始の時間を過ぎてしまった。
遅刻したとしても顔を出した方が良いのか。
今日は止めて明日にしようか。
練習時間は、いつも9時から12時。
午前中で終わってしまう。
あと3時間ほど。
家から学校までは、歩いて20分くらいかかる。
まずは制服に着替えよう。
そして、台本と財布を持って、靴を履くんだ。
そのまま流れに身を任せれば、何も考えずに体育館のステージまでたどり着けるはず。
きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。
飛び出るほどの心臓の鼓動を抑えながら、練習が行われているであろう体育館のステージを覗いくことが出来たのは、練習も終盤に差し掛かる11時30分頃だった。
体育館の中は明るい。
劇の練習中なら、真っ暗になっているはずなので劇の最中ではないようだ。
そっと入口から中の様子を伺っている局長に最初に気づいたのは白石加奈だった。
「あ~高井君だぁ!お久しぶりです!!」
大げさなほどペコっと頭を下げながら大きな声で挨拶をする。
「あ…どうも。」
どぎまぎしながら挨拶を返した局長に、小走りに守山が近づいてきた。
「良かった~。高井君来てくれたんだ。このままずっと来なくかったらどうしようかと思っていたよ。」
「お~!!!部長!良かったですね!」
後から黒崎もついてきて、守山の肩をポンと叩いた。
意外。
全く想定していない反応だった。
思い起こせば、中学生の頃から今に至るまでクラスの中では、そこに居たとしても誰もに認識されない「砂漠に散らばる砂鉄」のような扱いを受け続けてきた。
ずっと部活をさぼり続け、迷惑をかけた自分なんて、冷たく無視されるに決まっている。
結局誰からも存在を否定されて、そのまま体育館からを立ち去るんだ。
自分の居場所がもうないと言う事を認識し、もう二度とここには来ない。
その確認だ。
学校までの道すがらでは、そう言い聞かせ続けていた。
「今まで何してたの?」
黒崎は局長が何を話したいのか、まるで察しているかのように話しかけた。
「実は…今度また、劇をする機会があったらと思って台本を書いてたんすよ。一応…前に言われた所を踏まえて…いや、その前に…あの…すみませんでした…」
「え~!!凄い。凄い。新しい台本書いてくれているの!?くーちゃん!凄いね!」
「高井君やるねぇ!読みたい読みたい!この前のヤツも、演劇では難しかったけどお話は面白かったしね!」
局長が部活を辞めないようにと言う配慮が含めて、守山も黒崎も大げさに喜んで見せた。
局長は自分の意を決した謝罪が流された事と少しだけ複雑な思いを抱きつつも、この意外な反応に激しく戸惑う。
「どうしよう。今日の練習はもう一通り終わったんだけど、せっかく高井君来てくれたんだし、神様のシーンだけもう一回だけやる?」
黒崎に問いかける。
「もちろん!じゃあ、皆に話してきます!」
そう言って黒崎は他の部員たちのところに戻っていった。
「あの…オレ…まだ神様やる…らせて…もらえるんですか?」
局長は恐る恐る聞いてみる。
「当たり前だよ。高井君が神様やってくれないと誰がやるって言うんだよ!」
「じゃあ、今まではどうしてたんすか?」
「浦沢君がね、代役で神様やってくれたんだよ。」
少し離れたところでタクヤが手を振っている。
「やっと来たか。これでオレは本来の照明の仕事に集中できるな。」
わざとらしく大きな声でタクヤが語りかけた。
「浦沢君。ずっと代役やっていたから神様シーンの照明確認があんまりできてないんだよ。そのシーンだけ今からやろ?セリフ忘れてない?」
「え…いや、もちろん。覚えていますよ。」
「じゃ、決まりね。」
そう言うとくるりと回って守山はステージに歩いて行った。
局長もそれに続く。
そもそもの話、こんな人間は唾棄されて当然。
この1週間の間の局長の行動に対する非難を頭からぶちまけられればまだ良い方、おそらくは存在自体を否定されると思っていた。
もちろん局長に対して、負の感情を持つ部員がいなかったとは言わない。
それだけの迷惑をかけたのだ。
それでも、少なくとも迎え入れてくれる人がいた。
「ここはオレがいても良い場所なのかもしれない。」
局長が柄にもなく、人生において初めてそう思えた瞬間だった。
「付喪神」の物語を完成させよう。
そして明日からはちゃんと練習にも参加しよう。
こんな自分でも必要として、期待してくれている人がいるとすれば、その期待に1ミリでも答えられるように努力しよう。
そう強く心に誓い、この日、局長は1週間ぶりにステージに立ったのだった。
それは誰もが通る道なのかもしれない。
誰も通らないような下らない道なのかもしれない。
自分の存在を認めてもらう事で、誰かのために頑張れると言うある種の利他的ナルシズムの中で、局長の演劇部に対する認識はこの日確実に変化した。
その事に喜びを感じ過ぎたため、タクヤにライブのことを話す事をすっかり忘れていたが、そんな事は局長にとって実に些末な問題だったのだろう。
翌日、局長は普通に寝坊し、当たり前のように練習に遅刻した。
心に強く誓う事と寝坊しないことは別問題。
それが局長と言う心の底からどうしようもない人間なのだ。
「今日は来てくれないのかと思った…」
寂しそうにそうつぶやきつつも、ホッとした守山の表情は局長に尋常ならざる罪悪感を抱かせるに十分だった。
そして、長かった夏休みは終わりを告げた。
おそらく自分の代わりに新しい「神様」が誕生していて、自分なんかお払い箱になっている。
自分が無用の長物となっていることを確認することになると考えると、ただでさえ重い足がまるで鉛の塊となり、その一歩を踏み出すことが出来ない。
かと言って、練習に参加しなければ、お払い箱になっている確率はさらに高くなるに決まっている。
どちらにしても絶望。
絶望と絶望がくるくると交差する負のスパイラルの中で局長の心はドコまでもドコまでも落ち続けていた。
不意に、今練習している「すてふぁにー」の台本を手にとってみる。
物語は止まる事のない時間を食事する過食症の女子高生「弁当食い女」をテーマの軸に、女に飢えている男子校に通う2人の童貞男子がスネ毛を剃って女装し、女子高に潜入するところから始まる。
楽園だと思っていた女子高内で、生徒間のいじめや異性関係など学校問題、人の死を含めたこの世の不条理を見せつけられた2人の男子高校生が、少しずつ問題の核心に触れていく。
この作品を良しとして選んだ演劇部全員が言ってみれば「病んでいた」としか思えない。
そんな重苦しく、仄暗い物語だ。
読み終えたあと、今局長が執筆している「付喪神」を読んでみた。
負けていない。
いや、「付喪神」の方が面白い。
局長は、昔から自分が作った作品こそ最高に面白いと言う絶対の自信だけは常に持ち合わせており、それはもちろん今回の「付喪神」においても変わりない。
「この話を皆に見せれば、きっとオレの評価はくるりと180度位は変わるはず。何より、今辞めてしまえば、もうこの話を書いた意味も誰かに見せる機会自体もなくなってしまう…」
タクヤにライブの話を持っていくと言う、強引な理由付けをして決意した。
それでもなお、演劇部の練習に向かう一歩を踏み出すことが出来ない。
練習開始の時間を過ぎてしまった。
遅刻したとしても顔を出した方が良いのか。
今日は止めて明日にしようか。
練習時間は、いつも9時から12時。
午前中で終わってしまう。
あと3時間ほど。
家から学校までは、歩いて20分くらいかかる。
まずは制服に着替えよう。
そして、台本と財布を持って、靴を履くんだ。
そのまま流れに身を任せれば、何も考えずに体育館のステージまでたどり着けるはず。
きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。きっとできる。
飛び出るほどの心臓の鼓動を抑えながら、練習が行われているであろう体育館のステージを覗いくことが出来たのは、練習も終盤に差し掛かる11時30分頃だった。
体育館の中は明るい。
劇の練習中なら、真っ暗になっているはずなので劇の最中ではないようだ。
そっと入口から中の様子を伺っている局長に最初に気づいたのは白石加奈だった。
「あ~高井君だぁ!お久しぶりです!!」
大げさなほどペコっと頭を下げながら大きな声で挨拶をする。
「あ…どうも。」
どぎまぎしながら挨拶を返した局長に、小走りに守山が近づいてきた。
「良かった~。高井君来てくれたんだ。このままずっと来なくかったらどうしようかと思っていたよ。」
「お~!!!部長!良かったですね!」
後から黒崎もついてきて、守山の肩をポンと叩いた。
意外。
全く想定していない反応だった。
思い起こせば、中学生の頃から今に至るまでクラスの中では、そこに居たとしても誰もに認識されない「砂漠に散らばる砂鉄」のような扱いを受け続けてきた。
ずっと部活をさぼり続け、迷惑をかけた自分なんて、冷たく無視されるに決まっている。
結局誰からも存在を否定されて、そのまま体育館からを立ち去るんだ。
自分の居場所がもうないと言う事を認識し、もう二度とここには来ない。
その確認だ。
学校までの道すがらでは、そう言い聞かせ続けていた。
「今まで何してたの?」
黒崎は局長が何を話したいのか、まるで察しているかのように話しかけた。
「実は…今度また、劇をする機会があったらと思って台本を書いてたんすよ。一応…前に言われた所を踏まえて…いや、その前に…あの…すみませんでした…」
「え~!!凄い。凄い。新しい台本書いてくれているの!?くーちゃん!凄いね!」
「高井君やるねぇ!読みたい読みたい!この前のヤツも、演劇では難しかったけどお話は面白かったしね!」
局長が部活を辞めないようにと言う配慮が含めて、守山も黒崎も大げさに喜んで見せた。
局長は自分の意を決した謝罪が流された事と少しだけ複雑な思いを抱きつつも、この意外な反応に激しく戸惑う。
「どうしよう。今日の練習はもう一通り終わったんだけど、せっかく高井君来てくれたんだし、神様のシーンだけもう一回だけやる?」
黒崎に問いかける。
「もちろん!じゃあ、皆に話してきます!」
そう言って黒崎は他の部員たちのところに戻っていった。
「あの…オレ…まだ神様やる…らせて…もらえるんですか?」
局長は恐る恐る聞いてみる。
「当たり前だよ。高井君が神様やってくれないと誰がやるって言うんだよ!」
「じゃあ、今まではどうしてたんすか?」
「浦沢君がね、代役で神様やってくれたんだよ。」
少し離れたところでタクヤが手を振っている。
「やっと来たか。これでオレは本来の照明の仕事に集中できるな。」
わざとらしく大きな声でタクヤが語りかけた。
「浦沢君。ずっと代役やっていたから神様シーンの照明確認があんまりできてないんだよ。そのシーンだけ今からやろ?セリフ忘れてない?」
「え…いや、もちろん。覚えていますよ。」
「じゃ、決まりね。」
そう言うとくるりと回って守山はステージに歩いて行った。
局長もそれに続く。
そもそもの話、こんな人間は唾棄されて当然。
この1週間の間の局長の行動に対する非難を頭からぶちまけられればまだ良い方、おそらくは存在自体を否定されると思っていた。
もちろん局長に対して、負の感情を持つ部員がいなかったとは言わない。
それだけの迷惑をかけたのだ。
それでも、少なくとも迎え入れてくれる人がいた。
「ここはオレがいても良い場所なのかもしれない。」
局長が柄にもなく、人生において初めてそう思えた瞬間だった。
「付喪神」の物語を完成させよう。
そして明日からはちゃんと練習にも参加しよう。
こんな自分でも必要として、期待してくれている人がいるとすれば、その期待に1ミリでも答えられるように努力しよう。
そう強く心に誓い、この日、局長は1週間ぶりにステージに立ったのだった。
それは誰もが通る道なのかもしれない。
誰も通らないような下らない道なのかもしれない。
自分の存在を認めてもらう事で、誰かのために頑張れると言うある種の利他的ナルシズムの中で、局長の演劇部に対する認識はこの日確実に変化した。
その事に喜びを感じ過ぎたため、タクヤにライブのことを話す事をすっかり忘れていたが、そんな事は局長にとって実に些末な問題だったのだろう。
翌日、局長は普通に寝坊し、当たり前のように練習に遅刻した。
心に強く誓う事と寝坊しないことは別問題。
それが局長と言う心の底からどうしようもない人間なのだ。
「今日は来てくれないのかと思った…」
寂しそうにそうつぶやきつつも、ホッとした守山の表情は局長に尋常ならざる罪悪感を抱かせるに十分だった。
そして、長かった夏休みは終わりを告げた。

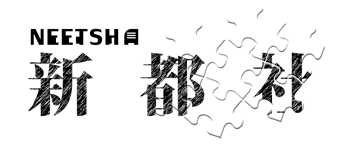

しもたろうに 先生に励ましのお便りを送ろう!!
〒みんなの感想を読む