ひとときの暗がり
作:しもたろうに
[website]
![]()

+
夏休みのある日、こんな出来事があった。
その日演劇部の面々は、うだるような暑さの中、締め切った体育館の中で、汗だくになりながら文化祭で講演する演劇「すてふぁにー」の練習をしていた。
本読みや流れの確認、演出作業などは滞りなく終了し、本番と同じ流れで劇自体を通して練習するいわゆる「通し稽古」の段階だ。
例えチョイ役であったとしても、役者として出る以上部活をサボってしまえば、その日1日の通し稽古(特に出演部分)が無駄になってしまう。そんな理由から局長もセコセコと皆勤で練習に参加していた。
ただ、局長の出番は序盤と終盤の少しだけ。
それ以外は、舞台袖で出番を待っていなくてはいけない。
狭い空間で、部員の皆と一緒に居る事に辟易していた局長は、この日、こっそり舞台袖から抜け出して、今回照明担当になったためスポットライトの確認をしているタクヤの所へ遊びに行った。
もちろん同じフロアでの事。
ステージの上での役者部員たちの演技を見ることはできる。
全体の流れを把握していた局長は、自分の出番の少し前に戻ればいいと安易に考えていた。
その間タクヤの照明の確認がおろそかになると言う事については頭の中にはなかった。
どこまでも自己中心的な男だ。
タクヤはそんな局長を注意するでもなく快く迎え入れた。
タクヤ自体もこの繰り返される確認作業に飽きてきていたのだ。
2人は初めこそ小声で会話をする程度だったが、段々話が盛り上がり始め、ケラケラと笑いながら無駄話に花を咲かせ始める。
「高井君!!何してんの!?」
不意に、守山の大きな声が体育館に響いた。
ビックリした局長は、ステージに目をやった。
劇が止まっている。
どうやら、タクヤとの会話に夢中になってしまい、自分の出番に気が付かなかったようだ。
本人がいる以上は代役など存在しない。
出番になっても舞台袖から出てこない局長のため、劇は止まってしまい、本来なら舞台袖にいるはずの局長を役者部員みんなで探しすことになる。
そこに、局長とタクヤの緊張感のない高笑いがケラケラケラケラ。
蒸し暑い体育館の中、本番まで日が迫っていたことも相まって、普段温和な部長の守山とは思えないような怒号が体育館内に響いたのだった。
「あ…すんません…」
タクヤに軽く背中を押された局長はペコペコと頭を下げながら、小走りに舞台袖まで走っていった。
「すんません…気が付かなくて…」
「気が付かなかったじゃなくてさ…高井君だって出番少ないと言っても役者なんだよ。 チョッと目を話したら居なくなってるとか困るよ。暑い中、夏休みに学校来てもらってるからさ、やる気無いのはまぁしょうがないけど、でも皆に迷惑かけるのはどうかと思う。」
守山はいつもよりもキツい言葉を局長に投げかけた。
それに対して一番ビックリしたのは局長だった。
局長は演劇部内ですら孤立し、他の部員(と言うか、主に女)から顰蹙を買い始めていた。
そんな中にあって(例え部長と言う立場ゆえだとしても)、守山は局長に対して唯一入部当初から変わらない態度で接していたのだ。
局長はその事実を勝手に曲解し、自分と言う有能な部員を失いたくない部長は、多少舐めた態度を取ったとしても許してくれるだろうと考えていた。
そして実際に守山はそんな局長の態度にも理解を示してくれている。と、思い込んでいた。
その守山に、きつい言葉をかけられたのだ。
客観的に見れば20000%局長が悪い。
どれだけ敏腕の弁護士であっても局長を擁護することはできないだろう。
当たり前のようにどこに行っても爪弾きにされる。
客観的に自分の行っている行為を見ることのできない局長にとって、この現状を納得するための唯一の方法は周囲の人間を非難することしかなかった。
小学生のころからそうして、何とかアイデンティティを保ってきた。
10年以上ずっと。
そんな中、優しく接してくれていた守山の存在は、「ほらな。守山部長のような出来てる人はオレの事を爪弾きにしないだろう。」と言う、自分の考えを後押しする根拠にまでなっていたのだ。
至極迷惑な話である。
反対に守山の対応は20000000000000000%正しい。
むしろここで局長を叱責しなければ、それは他の部員のモチベーションの定価。ひいては劇自体の完成度さえも左右するだろう。
弛んできている局長が多少なりとも良くなってくれるはずと言う期待すら持っていたかも知れない。
普通の人間なら、これを機に「確かに最近やる気なくなってたな。心を入れ替えて頑張ろう!」となるはずだ。
だがしかし、局長はこのあまりにも尊大な態度とは裏腹に、硝子細工よりも繊細な心をしていた。
この出来事は、守山の想像の遥か斜め上を行くほど強烈な衝撃として局長の尋常じゃないグラスハートに襲い掛かったのだ。
「さぁさぁ高井君も戻ってきたし、じゃあ、続きからやろうよ。」
黒崎が場の空気を変えようと局長の肩をポンと叩き無理からに明るくそう言った。
黒崎の奮闘むなしく、その日の練習は何とも言われぬじっとりとした重い空気のまま終わっていった。
夏の熱気がさらにそれを助長していたことは想像に難くない。
そして、この日を境に局長は演劇部の練習に一切顔を出さなくなってしまった。
それほどにこの日の出来事のショックは凄まじかったのだ。
やる気が無いどころか、練習態度も最悪。皆に迷惑をかけ、チョッと怒ればふて腐れて練習に来なくなる。
そんな最悪の部員と言う烙印が嫌がおうにも局長に押し付けられた事は言うまでも無い。
局長不在のまま劇の練習は日々続いていた。
「もうどうなっても良いや…」
皆が蒸し暑い体育館で練習をしている中、エアコンのついた涼しい部屋の中で漫画を描きながら局長はつぶやいた。
本当にどうしようもなく、信じられない位打たれ弱い男だった。
その日演劇部の面々は、うだるような暑さの中、締め切った体育館の中で、汗だくになりながら文化祭で講演する演劇「すてふぁにー」の練習をしていた。
本読みや流れの確認、演出作業などは滞りなく終了し、本番と同じ流れで劇自体を通して練習するいわゆる「通し稽古」の段階だ。
例えチョイ役であったとしても、役者として出る以上部活をサボってしまえば、その日1日の通し稽古(特に出演部分)が無駄になってしまう。そんな理由から局長もセコセコと皆勤で練習に参加していた。
ただ、局長の出番は序盤と終盤の少しだけ。
それ以外は、舞台袖で出番を待っていなくてはいけない。
狭い空間で、部員の皆と一緒に居る事に辟易していた局長は、この日、こっそり舞台袖から抜け出して、今回照明担当になったためスポットライトの確認をしているタクヤの所へ遊びに行った。
もちろん同じフロアでの事。
ステージの上での役者部員たちの演技を見ることはできる。
全体の流れを把握していた局長は、自分の出番の少し前に戻ればいいと安易に考えていた。
その間タクヤの照明の確認がおろそかになると言う事については頭の中にはなかった。
どこまでも自己中心的な男だ。
タクヤはそんな局長を注意するでもなく快く迎え入れた。
タクヤ自体もこの繰り返される確認作業に飽きてきていたのだ。
2人は初めこそ小声で会話をする程度だったが、段々話が盛り上がり始め、ケラケラと笑いながら無駄話に花を咲かせ始める。
「高井君!!何してんの!?」
不意に、守山の大きな声が体育館に響いた。
ビックリした局長は、ステージに目をやった。
劇が止まっている。
どうやら、タクヤとの会話に夢中になってしまい、自分の出番に気が付かなかったようだ。
本人がいる以上は代役など存在しない。
出番になっても舞台袖から出てこない局長のため、劇は止まってしまい、本来なら舞台袖にいるはずの局長を役者部員みんなで探しすことになる。
そこに、局長とタクヤの緊張感のない高笑いがケラケラケラケラ。
蒸し暑い体育館の中、本番まで日が迫っていたことも相まって、普段温和な部長の守山とは思えないような怒号が体育館内に響いたのだった。
「あ…すんません…」
タクヤに軽く背中を押された局長はペコペコと頭を下げながら、小走りに舞台袖まで走っていった。
「すんません…気が付かなくて…」
「気が付かなかったじゃなくてさ…高井君だって出番少ないと言っても役者なんだよ。 チョッと目を話したら居なくなってるとか困るよ。暑い中、夏休みに学校来てもらってるからさ、やる気無いのはまぁしょうがないけど、でも皆に迷惑かけるのはどうかと思う。」
守山はいつもよりもキツい言葉を局長に投げかけた。
それに対して一番ビックリしたのは局長だった。
局長は演劇部内ですら孤立し、他の部員(と言うか、主に女)から顰蹙を買い始めていた。
そんな中にあって(例え部長と言う立場ゆえだとしても)、守山は局長に対して唯一入部当初から変わらない態度で接していたのだ。
局長はその事実を勝手に曲解し、自分と言う有能な部員を失いたくない部長は、多少舐めた態度を取ったとしても許してくれるだろうと考えていた。
そして実際に守山はそんな局長の態度にも理解を示してくれている。と、思い込んでいた。
その守山に、きつい言葉をかけられたのだ。
客観的に見れば20000%局長が悪い。
どれだけ敏腕の弁護士であっても局長を擁護することはできないだろう。
当たり前のようにどこに行っても爪弾きにされる。
客観的に自分の行っている行為を見ることのできない局長にとって、この現状を納得するための唯一の方法は周囲の人間を非難することしかなかった。
小学生のころからそうして、何とかアイデンティティを保ってきた。
10年以上ずっと。
そんな中、優しく接してくれていた守山の存在は、「ほらな。守山部長のような出来てる人はオレの事を爪弾きにしないだろう。」と言う、自分の考えを後押しする根拠にまでなっていたのだ。
至極迷惑な話である。
反対に守山の対応は20000000000000000%正しい。
むしろここで局長を叱責しなければ、それは他の部員のモチベーションの定価。ひいては劇自体の完成度さえも左右するだろう。
弛んできている局長が多少なりとも良くなってくれるはずと言う期待すら持っていたかも知れない。
普通の人間なら、これを機に「確かに最近やる気なくなってたな。心を入れ替えて頑張ろう!」となるはずだ。
だがしかし、局長はこのあまりにも尊大な態度とは裏腹に、硝子細工よりも繊細な心をしていた。
この出来事は、守山の想像の遥か斜め上を行くほど強烈な衝撃として局長の尋常じゃないグラスハートに襲い掛かったのだ。
「さぁさぁ高井君も戻ってきたし、じゃあ、続きからやろうよ。」
黒崎が場の空気を変えようと局長の肩をポンと叩き無理からに明るくそう言った。
黒崎の奮闘むなしく、その日の練習は何とも言われぬじっとりとした重い空気のまま終わっていった。
夏の熱気がさらにそれを助長していたことは想像に難くない。
そして、この日を境に局長は演劇部の練習に一切顔を出さなくなってしまった。
それほどにこの日の出来事のショックは凄まじかったのだ。
やる気が無いどころか、練習態度も最悪。皆に迷惑をかけ、チョッと怒ればふて腐れて練習に来なくなる。
そんな最悪の部員と言う烙印が嫌がおうにも局長に押し付けられた事は言うまでも無い。
局長不在のまま劇の練習は日々続いていた。
「もうどうなっても良いや…」
皆が蒸し暑い体育館で練習をしている中、エアコンのついた涼しい部屋の中で漫画を描きながら局長はつぶやいた。
本当にどうしようもなく、信じられない位打たれ弱い男だった。

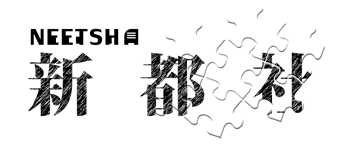

しもたろうに 先生に励ましのお便りを送ろう!!
〒みんなの感想を読む