ひとときの暗がり
作:しもたろうに
[website]
![]()

+
こんな事があった。
それは何の事はない日常会話。
体育の授業で、体操服に着替えている時の出来事。
局長のクラスメート西山が他の数人と話をしていた。
局長と距離が近かったため、その会話の内容がどうしたって耳に入ってきてしまう。
会話の内容は、その日たまたま学校を休んでいた田上と西山が喧嘩をしたと言う話だったようだ。
「ホント、オレあいつにはついていけないよ…。」
西山が田上を毒づく。
「どうしてあいつあんなに自分勝手なんだよ。あいつには絶対的に優しさとか思いやりがないって。そもそも思うんだけど…あいつは女の子とエッチした事無いから全然そういう気遣いとか出来ないんだよな。」
しかめっ面の西山がそう言うと、周りの何人かは「確かに!」と爆笑していた。
西山には、物凄く仲のいい彼女がいた。
佐山絵里というその彼女は、休み時間になる度に隣のクラスから西山を訪ねてきて、西山のひざの上にちょこんと小さなお尻を乗っけていちゃついていた。時々、周りの目をはばからずにキスをしたりもしていた。
とは言え。
とは言えだ。
それは所詮高校1年生の恋愛。
それどまりだ。そうに決まっている。
と局長は信じていたし、なぜかそれを願っていた。
そんな局長にとって、この耳に入ってきた当たり障りない会話は別の思考を巡らせる。
田上に思いやりが有るとか無いとか、そんな事はこの際どうでも良い。
問題なのは、「あの話題で笑い転げれるって事は、あの連中はみんな経験済みなのか!?」と言うことである。「確かに」ってどういう意味だよ。「確かに」ってよぉおおおおお。
言うまでも無く局長は童貞街道まっしぐらだ。
このままのペースでいけば、かなりの高確率で敬虔なキリスト教の神父さん、もしくは世の中に跋扈する魔法使いとなった男性諸兄と同じ人生を歩む事になるだろう。
高井家は、局長の代で途絶える事になる。
そんな局長が目の当たりにしたどうしようもない現実。
性教育の授業でしか聞いた事のない非現実であり実現するはずもない(つまり性器の中に性器を入れるという)あり得ない行為を、やったことがある人間がこの世に存在する。
それも複数いる。
同級生の中に。
途轍もない劣等感を感じていた。
なぜか考える事が恐くて仕方がない未来。
局長は生涯童貞と言う言葉に対して、尋常ではない恐怖を感じていた。
これは局長にとって触れてはならないパンドラの箱だったのだ。
そこにズカズカと裸足で踏み込まれた気分だった。
そんな局長だったが実は一度だけ女の子と付き合った事があった。(少なくとも局長は、付き合ったことがあると言い張っていた)
女子との総合計会話時間が10分にも満たない漆黒の中学生時代を過ごした局長を、クラスの女子たちは、その辺に落ちている石ころどころか、普段はその存在に気付きもしない砂場の中の砂鉄位にしか見ていなかった。
そんなある日、局長は告白される。
相手は違う学校の「遠山美智子」と言う女の子だ。
局長は思った。
「そうか、確かに学校の中でいる限りオレはあんな扱いだけど、外に出ればオレがあんな扱いをされてる事なんか誰も知らないんだ。先入観さえなければ、オレの事を好きになってくれる子だっていてもおかしくはない。当たり前田のクラッカーだ。」
当時まだ藤田まことはご存命だったはず。
そして、その子は一回目のデートの時に「勘違いしてました。」と言う名言を残して局長のもとを去った。
何も自分に欠点が無いと信じて疑わない局長は、先入観を排除した上で、それでもうまくいかなかったことに酷く傷付いた。
例えデートの内容が局長の読みたい本を探しての古本屋巡りで、本屋ではひたすら局長が黙々と本を探すだけ。その間、一切の説明も会話もなかったとしても。
例え局長が、当時オタクの象徴として鼻で笑われるためのファッションであったチェック柄のシャツを当たり前のようにズボンに入れ、紐の長いショルダーバックを肩から真っ直ぐかけていたとしても。
例え移動中、本の事で頭がいっぱいの局長が、その子が話しかけても「ああ」とか「うん」とか「ちょっと黙ってて」としか返事しなかったとしても。
昼食後に待ち合わせをしてから3件目の古本屋を出て「勘違いしてました」が出るまで。局長の彼女がいた時間の合計2時間41分3秒。3時間にも満たなかった。
放課後、局長はいつも以上に重い足を引き釣りながら部活に向かった。
ステージでは、守山が書いてきた創作台本「南国」を白石を含めた部員何人かで廻し読みしている。
その輪の中にはあろうことか、タクヤやウルオも混じっていた。
ムラヤンは今日も新作ゲームをやっているのか、来ていないようだ。
口々に、「面白~い。さすが部長だね。」と惜しみない賛辞を送っている。
少し照れながらも、局長に気が付いた守山は局長の所に小走りでやってきて
「高井君。何か…え~と…浦沢君に聞いたんだけど、中学生の時に劇の台本書いたことあるんだって?」
と聞いてきた。
後ろでタクヤがニヤニヤと局長を見ている。タクヤが守山に余計なことを話したようだ。
「はぁ…まぁ、あるけ…りますけど…」
局長が通っていた中学校では人権について考える授業の一環として「人権劇公演」と言うものを行っていた。
国語の成績だけはチョッと良かった局長は中学3年生の時、なぜかその劇の台本執筆に抜擢された事があったのだ。
ただそれは、担当の教員からお題を渡され、それを適当にセリフ考えて構成するだけ。
その上、結局その台本の9割を先生が加筆修正したので、局長としては自分が描いたものだという認識はほぼなかった。
台本を執筆したことがあると胸を張れるような体験ではない。
「さっき…くーちゃんを話してて、『すてふぁにー』もいいけど、今年の文化祭は創作台本で行こうって話になったの。それでね…え~と…皆で台本を書いて、コンペみたいなのやってみようってことになって。だから、高井君も書いてきてくれない?」
一息で少し早口にそう言うと、大きく空気を吸って局長の返事を待った。
「…いいっすよぉ。」
普段から物語を作ったり、妄想ばかりしていた局長は、不意にそれを承知してしまった。
「すごーい。やった~。加奈ちゃんも、浦沢君や栗山君も断られたんだよね。さすが、高井君だ。それで何か構想はあるの?」
少し逡巡しつつ、そう言えば漫画として最後まで描き切った比較的短い物語があることを思い出した。
部長に褒められた局長は少し照れながらつぶやく。
「はぁ…一応、『マリオネット』っていう話があります…けど…」
「ふふふ~ん。マリオネットか~勇気ある題名つけるね。」
守山は少し含みのあるニヤニヤ顔を浮かべつつ「じゃあ、それ。近いうちに書いてきてね」と言い、ステージの中央に戻っていった。
その日の夜。
局長はドキドキしながら、真っ白なルーズリーフに向かっていた。
そのルーズリーフの一番上には「タイトル『マリオネット』」とだけ書かれてあった。
小学生の頃から、局長はずっとマンガを描いてきた。だが、それを誰かに見せた事はなかった。
物語を描くことは大好きだったが人に見せることは恥ずかしくてしょうがない。
この台本を書き上げて、それを守山に渡すという事は、人生で初めて自分の考えた物語を人に読ませるという事になる。
そう考えるとガチガチに緊張してしまい、遂に1行も書くことが出来なかった。
人に見せる物語なんて、平常心で書ける訳ない。
諦めてベッドに入ったが、その日はいつも以上に寝付けなかった。
しょうがないのでオナニーをしてみたが、賢者タイムになっても一向に寝付けなかった。
それは何の事はない日常会話。
体育の授業で、体操服に着替えている時の出来事。
局長のクラスメート西山が他の数人と話をしていた。
局長と距離が近かったため、その会話の内容がどうしたって耳に入ってきてしまう。
会話の内容は、その日たまたま学校を休んでいた田上と西山が喧嘩をしたと言う話だったようだ。
「ホント、オレあいつにはついていけないよ…。」
西山が田上を毒づく。
「どうしてあいつあんなに自分勝手なんだよ。あいつには絶対的に優しさとか思いやりがないって。そもそも思うんだけど…あいつは女の子とエッチした事無いから全然そういう気遣いとか出来ないんだよな。」
しかめっ面の西山がそう言うと、周りの何人かは「確かに!」と爆笑していた。
西山には、物凄く仲のいい彼女がいた。
佐山絵里というその彼女は、休み時間になる度に隣のクラスから西山を訪ねてきて、西山のひざの上にちょこんと小さなお尻を乗っけていちゃついていた。時々、周りの目をはばからずにキスをしたりもしていた。
とは言え。
とは言えだ。
それは所詮高校1年生の恋愛。
それどまりだ。そうに決まっている。
と局長は信じていたし、なぜかそれを願っていた。
そんな局長にとって、この耳に入ってきた当たり障りない会話は別の思考を巡らせる。
田上に思いやりが有るとか無いとか、そんな事はこの際どうでも良い。
問題なのは、「あの話題で笑い転げれるって事は、あの連中はみんな経験済みなのか!?」と言うことである。「確かに」ってどういう意味だよ。「確かに」ってよぉおおおおお。
言うまでも無く局長は童貞街道まっしぐらだ。
このままのペースでいけば、かなりの高確率で敬虔なキリスト教の神父さん、もしくは世の中に跋扈する魔法使いとなった男性諸兄と同じ人生を歩む事になるだろう。
高井家は、局長の代で途絶える事になる。
そんな局長が目の当たりにしたどうしようもない現実。
性教育の授業でしか聞いた事のない非現実であり実現するはずもない(つまり性器の中に性器を入れるという)あり得ない行為を、やったことがある人間がこの世に存在する。
それも複数いる。
同級生の中に。
途轍もない劣等感を感じていた。
なぜか考える事が恐くて仕方がない未来。
局長は生涯童貞と言う言葉に対して、尋常ではない恐怖を感じていた。
これは局長にとって触れてはならないパンドラの箱だったのだ。
そこにズカズカと裸足で踏み込まれた気分だった。
そんな局長だったが実は一度だけ女の子と付き合った事があった。(少なくとも局長は、付き合ったことがあると言い張っていた)
女子との総合計会話時間が10分にも満たない漆黒の中学生時代を過ごした局長を、クラスの女子たちは、その辺に落ちている石ころどころか、普段はその存在に気付きもしない砂場の中の砂鉄位にしか見ていなかった。
そんなある日、局長は告白される。
相手は違う学校の「遠山美智子」と言う女の子だ。
局長は思った。
「そうか、確かに学校の中でいる限りオレはあんな扱いだけど、外に出ればオレがあんな扱いをされてる事なんか誰も知らないんだ。先入観さえなければ、オレの事を好きになってくれる子だっていてもおかしくはない。当たり前田のクラッカーだ。」
当時まだ藤田まことはご存命だったはず。
そして、その子は一回目のデートの時に「勘違いしてました。」と言う名言を残して局長のもとを去った。
何も自分に欠点が無いと信じて疑わない局長は、先入観を排除した上で、それでもうまくいかなかったことに酷く傷付いた。
例えデートの内容が局長の読みたい本を探しての古本屋巡りで、本屋ではひたすら局長が黙々と本を探すだけ。その間、一切の説明も会話もなかったとしても。
例え局長が、当時オタクの象徴として鼻で笑われるためのファッションであったチェック柄のシャツを当たり前のようにズボンに入れ、紐の長いショルダーバックを肩から真っ直ぐかけていたとしても。
例え移動中、本の事で頭がいっぱいの局長が、その子が話しかけても「ああ」とか「うん」とか「ちょっと黙ってて」としか返事しなかったとしても。
昼食後に待ち合わせをしてから3件目の古本屋を出て「勘違いしてました」が出るまで。局長の彼女がいた時間の合計2時間41分3秒。3時間にも満たなかった。
放課後、局長はいつも以上に重い足を引き釣りながら部活に向かった。
ステージでは、守山が書いてきた創作台本「南国」を白石を含めた部員何人かで廻し読みしている。
その輪の中にはあろうことか、タクヤやウルオも混じっていた。
ムラヤンは今日も新作ゲームをやっているのか、来ていないようだ。
口々に、「面白~い。さすが部長だね。」と惜しみない賛辞を送っている。
少し照れながらも、局長に気が付いた守山は局長の所に小走りでやってきて
「高井君。何か…え~と…浦沢君に聞いたんだけど、中学生の時に劇の台本書いたことあるんだって?」
と聞いてきた。
後ろでタクヤがニヤニヤと局長を見ている。タクヤが守山に余計なことを話したようだ。
「はぁ…まぁ、あるけ…りますけど…」
局長が通っていた中学校では人権について考える授業の一環として「人権劇公演」と言うものを行っていた。
国語の成績だけはチョッと良かった局長は中学3年生の時、なぜかその劇の台本執筆に抜擢された事があったのだ。
ただそれは、担当の教員からお題を渡され、それを適当にセリフ考えて構成するだけ。
その上、結局その台本の9割を先生が加筆修正したので、局長としては自分が描いたものだという認識はほぼなかった。
台本を執筆したことがあると胸を張れるような体験ではない。
「さっき…くーちゃんを話してて、『すてふぁにー』もいいけど、今年の文化祭は創作台本で行こうって話になったの。それでね…え~と…皆で台本を書いて、コンペみたいなのやってみようってことになって。だから、高井君も書いてきてくれない?」
一息で少し早口にそう言うと、大きく空気を吸って局長の返事を待った。
「…いいっすよぉ。」
普段から物語を作ったり、妄想ばかりしていた局長は、不意にそれを承知してしまった。
「すごーい。やった~。加奈ちゃんも、浦沢君や栗山君も断られたんだよね。さすが、高井君だ。それで何か構想はあるの?」
少し逡巡しつつ、そう言えば漫画として最後まで描き切った比較的短い物語があることを思い出した。
部長に褒められた局長は少し照れながらつぶやく。
「はぁ…一応、『マリオネット』っていう話があります…けど…」
「ふふふ~ん。マリオネットか~勇気ある題名つけるね。」
守山は少し含みのあるニヤニヤ顔を浮かべつつ「じゃあ、それ。近いうちに書いてきてね」と言い、ステージの中央に戻っていった。
その日の夜。
局長はドキドキしながら、真っ白なルーズリーフに向かっていた。
そのルーズリーフの一番上には「タイトル『マリオネット』」とだけ書かれてあった。
小学生の頃から、局長はずっとマンガを描いてきた。だが、それを誰かに見せた事はなかった。
物語を描くことは大好きだったが人に見せることは恥ずかしくてしょうがない。
この台本を書き上げて、それを守山に渡すという事は、人生で初めて自分の考えた物語を人に読ませるという事になる。
そう考えるとガチガチに緊張してしまい、遂に1行も書くことが出来なかった。
人に見せる物語なんて、平常心で書ける訳ない。
諦めてベッドに入ったが、その日はいつも以上に寝付けなかった。
しょうがないのでオナニーをしてみたが、賢者タイムになっても一向に寝付けなかった。

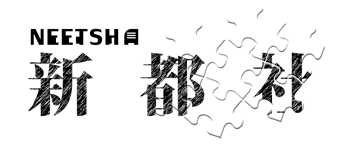

しもたろうに 先生に励ましのお便りを送ろう!!
〒みんなの感想を読む