ひとときの暗がり
作:しもたろうに
[website]
![]()

+
局長はこの春に高校生になったばかりの15歳。
高校に入学し、所属することになったクラスは言ってしまえば、凄く居心地の悪い空間だった。
中学生の時とにかく嫌いだったヤツや、話が合わなさ過ぎて苦手だったヤツばかりで構成されたクラス。挙句の果てには、担任の先生までまったく「そり」が合わないと言うなんとも言えない絶望感。
正直、学校に行くのが憂鬱で仕方がなかった。
高校デビューと言ってしまえば非常に語弊はあるが、当時はやっていたギャッツビーと言うメーカーのジェルでバリバリに髪を固め、ガクランのボタンも常に2つ開け、悪ぶったそぶりをして見せようと苦心惨憺の日々でもある。
中学時代のどこからどう見ても冴えないオタクだった自分とは違うのだ。
その効果が有ったかどうかは分からないが、中学生の頃と比べると周りの女の子からはよく声をかけられた。
だがしかし、周りの女の子から「汚物」のような扱いを受け半径1m以内に入って来る事すらない中学時代を歩んできた局長にとって、その対応は何よりも難しい問題でもある。
中学3年間の女子との総合計会話時間が10分に満たない局長をしては、「ああ・・・。」とか「うん・・・。」としゃべるだけと言う体たらくですら、自身のキャパシティーの限界をはるかに突破している。
しかしそれが何故か逆に「クール」ととられ始め、さらによく声をかけられるようになりつつある。
嬉しいやら困ったやら、どうしたものかと言う毎日をただ何の目的も無く、のんべんだらりんと過ごしていた。
元々人見知りだった局長にとって、高校で新しい友達を作る事など出来るはずもなく、クラスではよく一人 机に突っ伏して寝たフリばかりしてた。
「ピクッ」と動いた時だけ、周りの皆が相手にしてくれるので嘘でもピクピク動いていた。
局長ここにあり。と、皆に知ってもらいたい。
自分からは輪に入ろうとはしないけれども、存在を忘れられるわけにはいかない。複雑な心持ちを持っている。
もちろん、そんなもの無視される事の方が多かったが、それでも相手にされないよりはマシだった。
授業中は良い。
勉強がかったるいフリをしていれば良いのだから。
ただ、休み時間になる度 途方に暮れていた。
相手にしてくれる人は居ない。
自分から声をかけれるほどの勇気も当然持ち合わせてはいない。
唯一の救いは、1日に1回来るかどうかの浦沢タクヤ。
元々地黒だった タクヤは幼い頃「お前黒いんだよ」とからかっては泣かしてた頃からの付き合いで、中学時代に仲が良かった仲間内で同じ高校に進学した数少ない気の許せるヤツの一人だった。
とは言っても、それはあくまでも局長がそう思ってただけで、タクヤ自身はそんなに局長に気を許してはいない。
タクヤもまた回りに知り合いが居ない状態であり、無いよりはマシ程度の感覚で局長と付き合っていたのだが、そんな事は局長の知る由もない話だった。
局長は、自分が欠点だらけの人間だと言う事をあまり理解していない。
それが原因で孤立を深めている事も分からない。
ただ、周りのせいにする事で何とか自分のアイデンティティを保っていた。
タクヤと2人で話す内容は決まっている。
当時2人がやっていた「シータ」というバンドの事だ。
元々中学校の文化祭のために結成したバンド。
メンバーのほとんどが卓球部に所属していたため、周りからは「ピンポンバンド」と呼ばれ、揶揄されていた。
その名前について、本人たちは当然良しとしない。
ライブではメンバーをオブジェと称してステージに座らせたり、20秒ほどの前奏の後に「エ?終わり?」って戸惑うだけの「スーパーフィニッシュ」と言うオリジナル曲を作ったりと、誰の方向も向いていない、思春期特有の自己満足に浸るための演奏をしては、ブーイングを浴びていた。
「シータ」はボーカル1人、ギター3人、ベース2人、キーボード1人、ドラム1人、オブジェ2人、棒立ち1人の11人からなる大所帯バンド。
局長は曲作りとキーボード担当。タクヤはベースを担当していた。
局長とタクヤが中心となり、他のメンバーはそれにただ乗っかているだけという状態で活動していた。活動と言えるほど何かをしているわけではなかったが。
高校に入りメンバーの一部が別の学校に行くことになっため、日々の練習と言った当たり前の活動すらもままならず、完全停止状態に追い込まれていたため、2人の会話の内容は専ら「シータの活動について」と言うより、「この状態でまだ続けるのか?」についての話し合いばかりだった。
もうひとつ。
2人が良く話していた内容があった。
それは「何の部活動に入るか」。
高校時代を如何に有意義な青春にするかを決定付ける重要事項。
それについては2人とも共通意識として感じており、自らの高校生活をバラ色にする為、熱い議論を日夜交わしていた。
2人ともあまりメンド臭い事はしたくなく、また体育会系のノリに付いて行けるはずも無い。
煩悩の塊である2人の目指すものは、つまり「楽で簡単だけどおいしい部活」。
努力も苦労も不要で、気楽に続けられて、それでいて、喝采と称賛を浴びる事が出来、ちやほやされたい。もっと言えば、女の子と仲良くなりたい。
典型的ダメ人間の発想だった。
頑張りたくは無いけど、目立ちたい。大層に扱ってもらいたいと言うどうしようもない名誉欲と承認欲求にかられていたのだろう。
それでも、2人は真剣に考えた。
クラスの居心地が悪い以上部活動で失敗したら、一度しかない高校生活を棒に振る結果になりかねない。
練習もきつくなくて、割と誰にでも出来そうで、文化祭とかでは目立てそうと言う偏見に満ちた理由で、2人が選んだのは「演劇部」だった。
2人だけでは心細いので、取り合えず「シータ」メンバーで同じ学校に来ていたドラムの「ウルオ」とボーカルの「ムラヤン」を誘って見学に行く事にした。
体育館のステージで放課後に練習をしているという情報をタクヤが仕入れてきた。
見学に行く日。
別に演劇になんの興味も持っていないウルオとムラヤンを「誘う」と言う表現が酷く憚れる「拉致」のような形で無理やり連れだし、いざ体育館に。
ステージには誰も居なかった。
「今日はやってないのかな?」「帰ろうか」などと話をしていると、ゾロゾロと何人かの女の子が体育館に入ってきた。
そして、モソモソしている局長達4人に恐る恐る声をかけてきた。
「あの・・・見学ですか?」
女と言う生き物と会話する事が出来ない局長に代わってタクヤが答えた。
「僕ら、演劇部をチョッと見せてもらおうかなぁ~って思いました・・・」
それだけ言うと相手がざわざわし始めた。
「すご~い」とか「男子が来たよ」と言った声が聞こえた。
この時局長は心の中でこっそりガッツポーズをした。
なぜならここは「ハーレム」。
ここなら、オレみたいなヤツでも女の子と仲良くなれる。
「男子が来たよ。すご~い」と言う言い方から推察するに、きっと他に男はいない。いないという事は、この女の子は全て自分のもの。全員がオレの穴でしかない。
邪で不純に飛躍した動機に局長の心臓は震えに震えた。
タクヤの返事にその中の一人が答えた。
「え…と新入部員に説明する日は決まってて。だから、その日に1年4組の教室に来てくれますか?」
その日はそれで終わった。
帰りの道の上で4人は悩んだ。
行くか辞めるか。
4人で話をしていた。しかし、実際に悩んでいたのは3人だった。
局長の中では「ハーレムだ」と言う言葉がズ~っとクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルと回っており、結論などはるか昔に出ていたのだ。
この時局長が考えていたのは、入部するかどうかではなく、童貞卒業の是非とそのタイミングについてのみだった。
数日後。
局長は悩んでいた3人を説き伏せ、指定の教室に赴いた。
すでに何人か座っている。
やはり予想通り全員女の子だ。
局長は、思惑通りの展開に心躍らせながら、同時に今更ながらどうしようもない不安にも取り付かれていた。
「うまくこの子達とやっていけるんだろうか?」
しばらくして「そろそろ始めよ」と口々に言い始め、一人の女の子が教壇に立ち手で胸を抑え前後に体を揺らしながらしゃべり始める。
「え…と。私が今部長の『守山明美』です。」
局長の高校生活は本当の意味で始まりを告げた。
高校に入学し、所属することになったクラスは言ってしまえば、凄く居心地の悪い空間だった。
中学生の時とにかく嫌いだったヤツや、話が合わなさ過ぎて苦手だったヤツばかりで構成されたクラス。挙句の果てには、担任の先生までまったく「そり」が合わないと言うなんとも言えない絶望感。
正直、学校に行くのが憂鬱で仕方がなかった。
高校デビューと言ってしまえば非常に語弊はあるが、当時はやっていたギャッツビーと言うメーカーのジェルでバリバリに髪を固め、ガクランのボタンも常に2つ開け、悪ぶったそぶりをして見せようと苦心惨憺の日々でもある。
中学時代のどこからどう見ても冴えないオタクだった自分とは違うのだ。
その効果が有ったかどうかは分からないが、中学生の頃と比べると周りの女の子からはよく声をかけられた。
だがしかし、周りの女の子から「汚物」のような扱いを受け半径1m以内に入って来る事すらない中学時代を歩んできた局長にとって、その対応は何よりも難しい問題でもある。
中学3年間の女子との総合計会話時間が10分に満たない局長をしては、「ああ・・・。」とか「うん・・・。」としゃべるだけと言う体たらくですら、自身のキャパシティーの限界をはるかに突破している。
しかしそれが何故か逆に「クール」ととられ始め、さらによく声をかけられるようになりつつある。
嬉しいやら困ったやら、どうしたものかと言う毎日をただ何の目的も無く、のんべんだらりんと過ごしていた。
元々人見知りだった局長にとって、高校で新しい友達を作る事など出来るはずもなく、クラスではよく一人 机に突っ伏して寝たフリばかりしてた。
「ピクッ」と動いた時だけ、周りの皆が相手にしてくれるので嘘でもピクピク動いていた。
局長ここにあり。と、皆に知ってもらいたい。
自分からは輪に入ろうとはしないけれども、存在を忘れられるわけにはいかない。複雑な心持ちを持っている。
もちろん、そんなもの無視される事の方が多かったが、それでも相手にされないよりはマシだった。
授業中は良い。
勉強がかったるいフリをしていれば良いのだから。
ただ、休み時間になる度 途方に暮れていた。
相手にしてくれる人は居ない。
自分から声をかけれるほどの勇気も当然持ち合わせてはいない。
唯一の救いは、1日に1回来るかどうかの浦沢タクヤ。
元々地黒だった タクヤは幼い頃「お前黒いんだよ」とからかっては泣かしてた頃からの付き合いで、中学時代に仲が良かった仲間内で同じ高校に進学した数少ない気の許せるヤツの一人だった。
とは言っても、それはあくまでも局長がそう思ってただけで、タクヤ自身はそんなに局長に気を許してはいない。
タクヤもまた回りに知り合いが居ない状態であり、無いよりはマシ程度の感覚で局長と付き合っていたのだが、そんな事は局長の知る由もない話だった。
局長は、自分が欠点だらけの人間だと言う事をあまり理解していない。
それが原因で孤立を深めている事も分からない。
ただ、周りのせいにする事で何とか自分のアイデンティティを保っていた。
タクヤと2人で話す内容は決まっている。
当時2人がやっていた「シータ」というバンドの事だ。
元々中学校の文化祭のために結成したバンド。
メンバーのほとんどが卓球部に所属していたため、周りからは「ピンポンバンド」と呼ばれ、揶揄されていた。
その名前について、本人たちは当然良しとしない。
ライブではメンバーをオブジェと称してステージに座らせたり、20秒ほどの前奏の後に「エ?終わり?」って戸惑うだけの「スーパーフィニッシュ」と言うオリジナル曲を作ったりと、誰の方向も向いていない、思春期特有の自己満足に浸るための演奏をしては、ブーイングを浴びていた。
「シータ」はボーカル1人、ギター3人、ベース2人、キーボード1人、ドラム1人、オブジェ2人、棒立ち1人の11人からなる大所帯バンド。
局長は曲作りとキーボード担当。タクヤはベースを担当していた。
局長とタクヤが中心となり、他のメンバーはそれにただ乗っかているだけという状態で活動していた。活動と言えるほど何かをしているわけではなかったが。
高校に入りメンバーの一部が別の学校に行くことになっため、日々の練習と言った当たり前の活動すらもままならず、完全停止状態に追い込まれていたため、2人の会話の内容は専ら「シータの活動について」と言うより、「この状態でまだ続けるのか?」についての話し合いばかりだった。
もうひとつ。
2人が良く話していた内容があった。
それは「何の部活動に入るか」。
高校時代を如何に有意義な青春にするかを決定付ける重要事項。
それについては2人とも共通意識として感じており、自らの高校生活をバラ色にする為、熱い議論を日夜交わしていた。
2人ともあまりメンド臭い事はしたくなく、また体育会系のノリに付いて行けるはずも無い。
煩悩の塊である2人の目指すものは、つまり「楽で簡単だけどおいしい部活」。
努力も苦労も不要で、気楽に続けられて、それでいて、喝采と称賛を浴びる事が出来、ちやほやされたい。もっと言えば、女の子と仲良くなりたい。
典型的ダメ人間の発想だった。
頑張りたくは無いけど、目立ちたい。大層に扱ってもらいたいと言うどうしようもない名誉欲と承認欲求にかられていたのだろう。
それでも、2人は真剣に考えた。
クラスの居心地が悪い以上部活動で失敗したら、一度しかない高校生活を棒に振る結果になりかねない。
練習もきつくなくて、割と誰にでも出来そうで、文化祭とかでは目立てそうと言う偏見に満ちた理由で、2人が選んだのは「演劇部」だった。
2人だけでは心細いので、取り合えず「シータ」メンバーで同じ学校に来ていたドラムの「ウルオ」とボーカルの「ムラヤン」を誘って見学に行く事にした。
体育館のステージで放課後に練習をしているという情報をタクヤが仕入れてきた。
見学に行く日。
別に演劇になんの興味も持っていないウルオとムラヤンを「誘う」と言う表現が酷く憚れる「拉致」のような形で無理やり連れだし、いざ体育館に。
ステージには誰も居なかった。
「今日はやってないのかな?」「帰ろうか」などと話をしていると、ゾロゾロと何人かの女の子が体育館に入ってきた。
そして、モソモソしている局長達4人に恐る恐る声をかけてきた。
「あの・・・見学ですか?」
女と言う生き物と会話する事が出来ない局長に代わってタクヤが答えた。
「僕ら、演劇部をチョッと見せてもらおうかなぁ~って思いました・・・」
それだけ言うと相手がざわざわし始めた。
「すご~い」とか「男子が来たよ」と言った声が聞こえた。
この時局長は心の中でこっそりガッツポーズをした。
なぜならここは「ハーレム」。
ここなら、オレみたいなヤツでも女の子と仲良くなれる。
「男子が来たよ。すご~い」と言う言い方から推察するに、きっと他に男はいない。いないという事は、この女の子は全て自分のもの。全員がオレの穴でしかない。
邪で不純に飛躍した動機に局長の心臓は震えに震えた。
タクヤの返事にその中の一人が答えた。
「え…と新入部員に説明する日は決まってて。だから、その日に1年4組の教室に来てくれますか?」
その日はそれで終わった。
帰りの道の上で4人は悩んだ。
行くか辞めるか。
4人で話をしていた。しかし、実際に悩んでいたのは3人だった。
局長の中では「ハーレムだ」と言う言葉がズ~っとクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルと回っており、結論などはるか昔に出ていたのだ。
この時局長が考えていたのは、入部するかどうかではなく、童貞卒業の是非とそのタイミングについてのみだった。
数日後。
局長は悩んでいた3人を説き伏せ、指定の教室に赴いた。
すでに何人か座っている。
やはり予想通り全員女の子だ。
局長は、思惑通りの展開に心躍らせながら、同時に今更ながらどうしようもない不安にも取り付かれていた。
「うまくこの子達とやっていけるんだろうか?」
しばらくして「そろそろ始めよ」と口々に言い始め、一人の女の子が教壇に立ち手で胸を抑え前後に体を揺らしながらしゃべり始める。
「え…と。私が今部長の『守山明美』です。」
局長の高校生活は本当の意味で始まりを告げた。

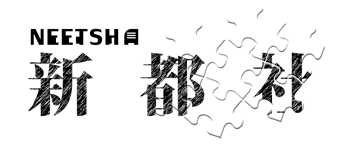

しもたろうに 先生に励ましのお便りを送ろう!!
〒みんなの感想を読む